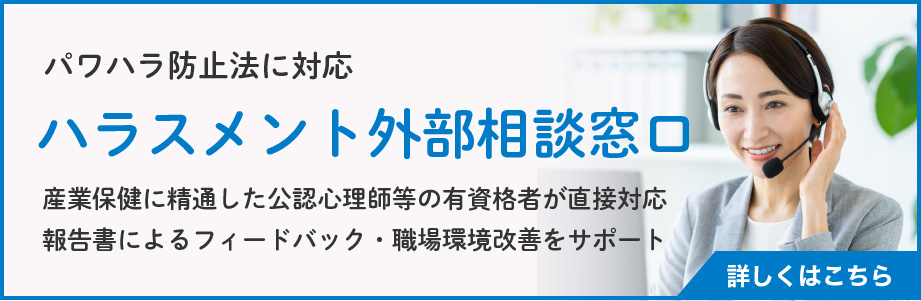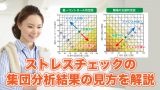2022年4月1日に全面的に施行された「パワハラ防止法」。中小企業を含む全ての企業には、職場でのハラスメント防止に向けた方針を明確に示し、相談窓口を整備するとともに、ハラスメントに関する労使間のトラブルを迅速に解決する体制を整える義務があります。
このように法律によって事業者にパワハラ防止措置が義務付けられていますが、実際にはパワーハラスメントは多くの企業において存在しています。
厚生労働省の調査によると、過去3年間に、職場において何らかのハラスメントを経験した労働者の割合は56.6%と高い割合を示しています。
企業としてハラスメントを予防・防止するためにはどのような取り組みをしていけばよいのでしょうか。今回は職場のハラスメントの予防・防止対策について基本的な流れと具体的な取り組み方法をお伝えします。
ハラスメントの原因
ハラスメントが発生する原因は複合的であり、個人的な要因や職場などの環境的な要因など様々な要因が連鎖するなかで発生します。
厚生労働省による調査(※)によれば、パワーハラスメント関連の相談がある職場に共通する特徴として次のように挙げられています。
残業が多い/休暇を取りづらい 24.8%
業績が低下している/低調である 20.2%
従業員の年代に偏りがある 31.9%
人手が常に不足している 45.4%
例えば、上司と部下のコミュニケーションが少ない職場の場合は、率直に意見を言うことは難しく、そのため誤解や不満も生じやすい環境となりハラスメントが起きやすくなります。
残業が多かったり、業績が低下していたりする職場の場合は、日常的に強いストレスがある環境にあるといえます。このような状況においては、八つ当たりや攻撃的な言葉により自分の感情が現れやすくなります。そのため、無意識的にハラスメントの加害者になるという可能性が高まります。
また従業員の年代に偏りがある職場の場合は、年代による価値観や常識が異なることにより無自覚にハラスメントが生じる可能性があります。
それでは具体的にどのように企業としてハラスメントの予防・防止対策を行っていけばよいのでしょうか。
(※)職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要(令和5年度 厚生労働省)
ハラスメントの予防・防止対策の基本
職場におけるハラスメントに対して、企業がどのように対応したらよいのでしょうか。
パワハラ防止法で全ての企業に義務付けられている防止措置
2020年6月から施行された「パワハラ防止法」は、2022年4月から従業員の規模を問わずすべての企業にパワハラ対策が義務化されています。
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
義務化されているパワハラ防止措置を踏まえ、企業によるハラスメントの予防・防止対策の基本的な流れと具体的な方法について確認していきましょう。
ハラスメント予防・防止対策の準備段階
企業がハラスメント予防に取り組む前に準備が必要です。
経営者のハラスメント理解
上層部の意識や姿勢は、企業風土に大きな影響を与えます。そのため、経営者や役員等、会社の上層部にハラスメントは重大な問題であるということを理解してもらうことが大切です。
研修等を実施しハラスメントについて理解を深めてもらうことがよいと思います。
現状の把握
アンケートの実施が難しい場合は、ストレスチェックの集団結果を利用するのもいいでしょう。
ハラスメント対策を策定し社内に周知する
ハラスメント対策について方針を策定し、社内に通知します。方針策定にあたっては、企業規模や実態に合ったより効果的な対策を構築することが重要です。
また従業員の意見を反映させることも社内での理解を得て効果的なハラスメント対策を講じるためにも大切です。
ハラスメント相談窓口の設置
実際にパワハラを受けている、発生の恐れがあるなどの場合に従業員が相談できる相談窓口を設置します。
相談窓口担当者は、内容や状況に応じて適切に対応できるようフォロー体制を講じることが重要です。
教育・研修の実施
従業員がハラスメントについての理解を深めるため、教育・研修を実施します。
研修を実施する際には、管理職向けと従業員向けで分けて実施することをおすすめします。
管理職向けハラスメント研修
職場におけるハラスメン卜の加害者は、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントともに被害者の上司である事例が多くなっています。
また管理職はハラスメントを防止する職場の責任者の役割も担います。
そのため管理職向け研修では、自身がハラスメントの当事者にならないこと、職場環境に配慮し適切な対応をとることに重きを置くような内容にするのがよいでしょう。
一般従業員向けハラスメント研修
ハラスメントが発覚した場合の措置
パワハラが発覚した場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認できた場合は、速やかに被害者への配慮のための措置・行為者に対する措置を適正に行い、再発防止に向けた措置を講じます。
プライバシー保護、不利益取扱いの禁止の徹底
パワハラの当事者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、そのことを労働者に周知徹底すること。また、相談したことや、事実関係の確認に協⼒したことなどで、不利益な取扱いをされないことを規定し、全従業員に周知・啓発します。
まとめ
ハラスメントの防止対策を講じる上で重要なのは、健全な人間関係を形成するための職場環境を整えることです。
社内研修などで、相手の気持ちを正しく理解する方法や、上司による部下への適切な指導方法などを伝え、会社全体のコミュニケーションを改善することが重要です。
参照
職場のハラスメントに関する実態調査報告書(厚生労働省)
職場におけるハラスメント防止ハンドブック(厚生労働省)