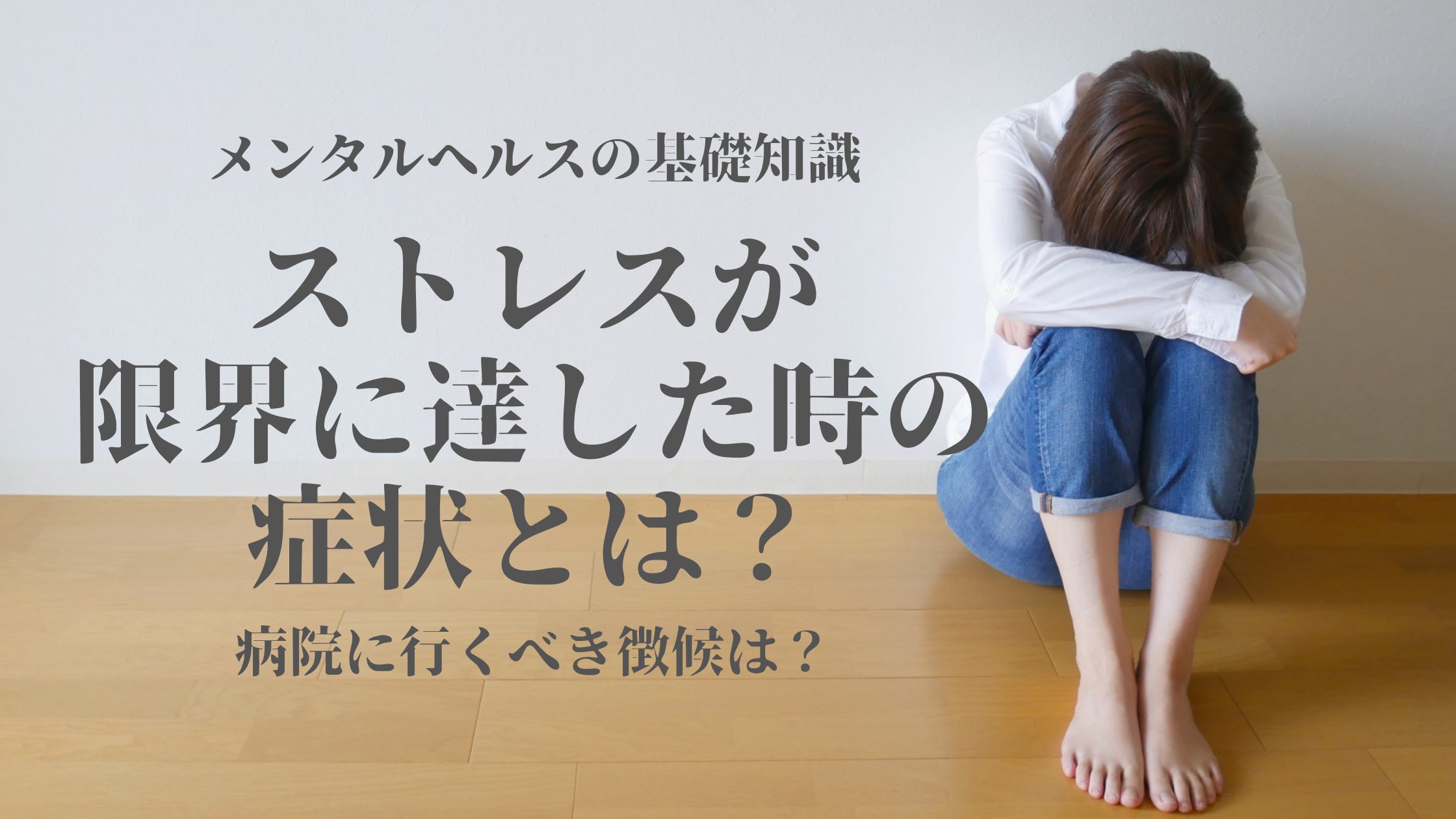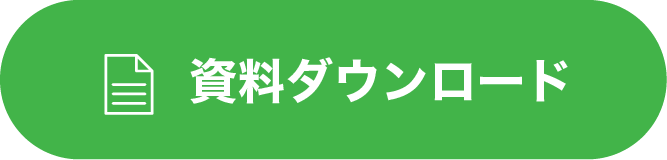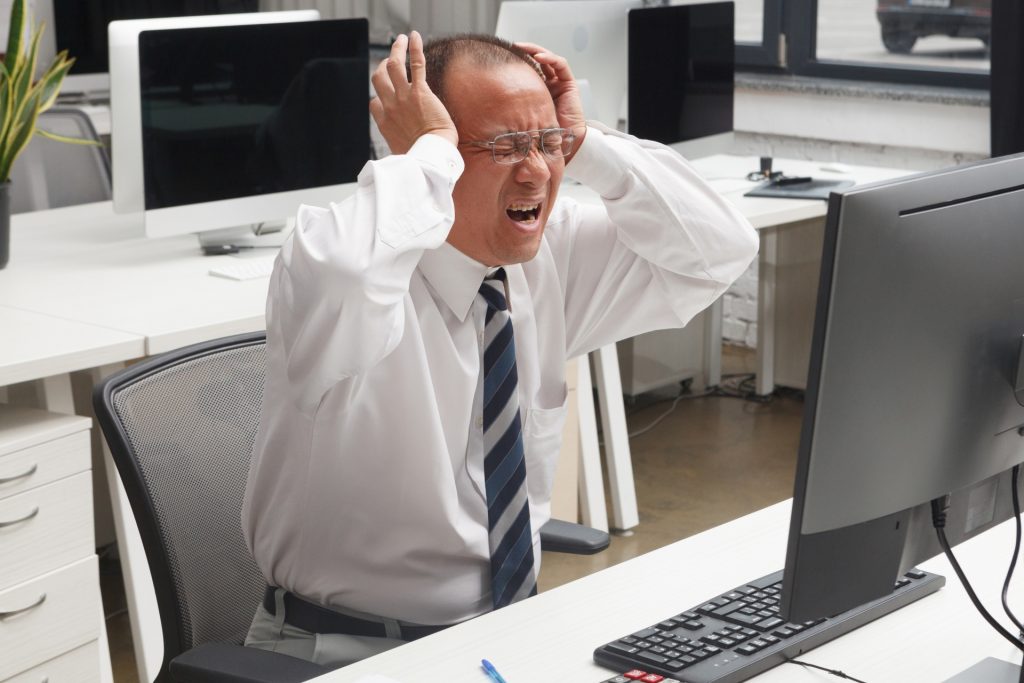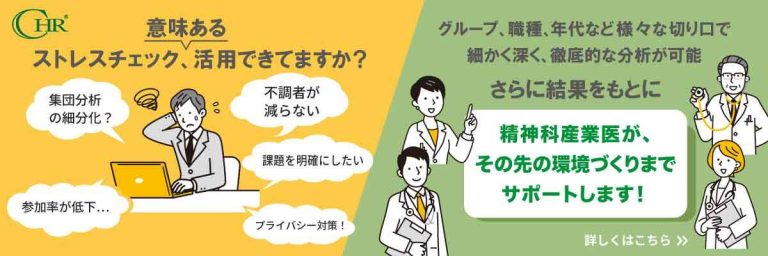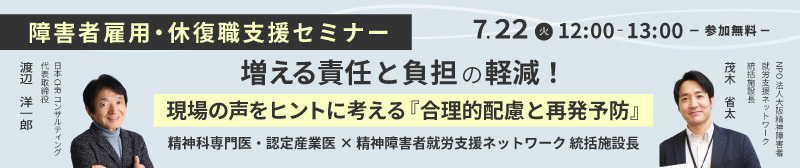「眠れない」「やる気がでない」「わけもなく不安になったり悲しくなる」「怒りっぽくなった」など、一般的によくみられる症状の原因は、ストレスかもしれません。
私たちは日々さまざまなストレスを抱えて生きています。
ストレスを自覚できていれば、それに対応することもできますが、自分でも気づかぬうちにストレスを溜め込み、ある日突然、心や身体に症状として現れることがあります。
「これくらい大丈夫」「みんなも我慢している」と心や体の不調を放っておくことは、不調の悪化につながる危険があります。
ストレスによる症状やストレスが限界に達したときの症状を知り、適切に対処をしていきましょう。

PR|ストレスマネージメント書籍紹介 (弊社代表・医師 渡辺洋一郎 著)
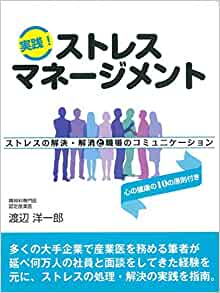
実践!ストレスマネージメントストレスの解決・解消と職場のコミュニケーション 心の健康10の原則付き
著者:渡辺 洋一郎 精神科専門医・認定産業医 弊社代表
出版社 : 公益財団法人日本生産性本部 労働情報センター
職場のコミュニケーションやチームワーク、ストレスを跳ね返す力であるレジリエンス、メンタル不調を防ぐためのストレスマネージメントとは何かについて、心の健康10の法則とともに解説しています。 ※クリックするとAmazonに飛びます。
Amazonで購入その背景には、職場環境やサポート体制の課題が潜んでいるかもしれません。
CHRでは、精神科産業医や外部相談窓口(EAP)、離職防止サービスなど、
企業の実情に合わせたメンタルヘルス対策をご提案しています。
ストレスによる症状
まずはじめに、ストレスによる一般的な症状について見ていきましょう。
例えば、眠れない、お腹の調子が悪いなどはストレスによる症状として現れることもあります。軽度に思われるかもしれませんが、それらは早めに対処することが大切です。
ストレスによる一般的な症状は、「身体」「考え方」「感情」「行動」に見られます。
ストレスによる症状「身体の症状」
- 眠れない、熟睡感がない、または寝すぎる
- 食欲がない、または食べ過ぎる
- 身体がだるい
- 元気が出ない
- 頭が重い
- 疲労感が強い
- 動悸や息苦しさがある
- お腹の調子が悪い
- ふらつく
- 便秘・下痢
- のぼせや冷え
- 肩こり・腰痛など身体の痛み
ストレスによる症状「考え方」

- どうせうまくいかないと考える
- 同じ事ばかり考える
- 悪い結果ばかり考える
- 呆然として何も考えられない
- 大事なことを考えるのを避ける
- 集中できない
- 自分は役に立たないと考える
- 自分を責める
ストレスによる症状「感情」

- 悲しく憂鬱
- 気持ちが沈む
- やる気が出ない
- 何をするのもおっくうに感じる
- さみしい、哀しい
- 不安でしかたない
- 落ち着かない、イライラする
- 絶望的に感じる
- いなくなりたいと感じる
- 何事にも興味がわかず、楽しくない
ストレスによる症状「行動」

- 睡眠リズムが崩れる
- 生活リズムが崩れる
- 家に閉じこもる、ずっと寝ている
- 過度に集中、没頭する
- 些細なことで腹をたてる
- アルコールや喫煙が増える
- 浪費が増える、ギャンブルに溺れる
- 運転が乱暴になる
このようにストレスによる症状は、さまざまです。
心身や感情に見られる症状は誰しも経験することかと思います。しかし、「誰でもあること」とそのままにしてしまっては、症状が悪化してしまう危険があるため、早めに適切な方法でストレスを処理することをおすすめします。
症状によっては、受診が急がれる場合もあります。次の項目で説明するような症状が見られた場合、ストレスが限界に達していると捉え、早急に医療機関に行く必要があります。
ではストレスが限界に達したときの症状とはどのような症状なのでしょうか?
ストレスが限界に達した時の症状
ストレスが限界に達したときに出る症状というと、例えば突然倒れたり、何もないのに涙が止まらないなど、誰の目からみてもわかりやすい症状を思い浮かべる方が多いかもしれません。
もし突然倒れたり、わけもなく涙が止まらないというようなことがある場合、できるだけ早く医療機関に相談してください。
しかしこのような症状に至る以前に、ストレスが限界に達していることを示す症状というものがあります。
ストレスが限界に達したときに出る症状すなわち、医療機関に行くべき徴候は、自分で気づく変化と、職場や家族など周りが気づく変化があります。
相談に早すぎるということはありません。一人で抱え込まず、専門家に話すことが大切です。
ストレスが限界に達した時の症状|自分で気づく変化
■好きなことが楽しめない
この2つの症状が、ほとんど1日中、毎日、1週間以上続く場合は、医療機関への相談が急がれます。
ストレスが限界に達した時の症状|周囲が気づく変化
医療機関へ行くべき徴候について周囲が気づく変化は、次のような感覚で気づく場合が多いです。
■「今まで○○だったのに、最近△△だ・・・」
具体的な様子は人によって様々ですが、ここでは一般的な様子の変化については職場・家族それぞれ次の様子の変化について見ていきます。
家族や友人が気づく変化
・酒を飲むと、性格や言動がまったく変わってしまう
・ささいなことに激しく怒り、乱暴を働く
・考え込むようになり、独り言やイライラすることが多くなる
・とりとめのないことを気にする
・ケガが多くなる
・表情が乏しく、口数が減って行動に正気がなくなる
・好きなことをしなくなる
・家にこもりがちになる
・服装や身だしなみがだらしなくなり、不潔になる
・自信がなくなり、自分の能力の低下を訴える など・・・
職場で気づく変化
・しばしば休んだり、突然休む
・大した理由もなく職場転換を希望したり、退職を訴える
・身体の具合が悪いといったり、とりとめのない訴えが多くなる
・以前はできたルーティンワークができない
・業務中に居眠りが目立ったり、ぼーっとしている
・関係者との言い争いや気分のムラがある
・職務上の義務を怠りがちになり、責任感に乏しくなる
・取引先や顧客からのクレームが多い
・同僚などと話し合うのを嫌がり、付き合いを避ける
・作業にミスが目立ったり、手こずっている など・・・
家族や友人の中に、このようなことが感じられる場合、ストレスへの気付きを促してみることをおすすめします。
涙が出るのはストレスのせい?対処法
なんでもないのに急に涙があふれてきたり、人前でこらえきれず泣いてしまったり――。そんな経験がある方は、もしかすると強いストレスが心や体に影響を及ぼしているサインかもしれません。
涙には「生理的な涙(目を保護するための涙)」と、「心理的な涙(感情による涙)」の2種類があります。ストレスによって出る涙は主に後者で、心の負担が大きくなったとき、副交感神経の働きによって自然にあふれ出すものです。
涙が出るときの背景にある心の状態
以下のような場面で、ストレスから涙が出ることがあります。
- プレッシャーや不安に押しつぶされそうなとき
- 頑張っても報われないと感じたとき
- 怒りや悔しさを言葉にできず、感情があふれたとき
- 誰にも相談できず、孤独を感じたとき
これらの涙は、感情やストレスが限界に達していることを示している場合があります。無理に止めようとせず、「自分は今、頑張りすぎているのかも」と気づくサインとして受け止めましょう。
対処法:涙が出る自分を責めず、ストレスをやわらげる工夫を
涙が出るほどのストレスを感じているときは、以下のような対処法を試してみてください。
休息をとる:まずは心身を休めることを最優先に。短時間でもよいので、意識的にリラックスする時間をつくりましょう。
感情を言語化する:日記に思いを綴る、信頼できる人に話すなど、自分の感情を表に出すことで、気持ちの整理がしやすくなります。
泣ける環境を整える:あえて泣ける映画を観るなど、安全な場所で涙を流すことで、心のデトックスにつながります。
深呼吸やストレッチ:副交感神経を優位にする呼吸や軽い運動は、気持ちを落ち着けるのに有効です。
「泣くことは悪いことではない」と受け止める:涙は心のバランスを整える自然な反応です。涙を流すことで、ストレスが軽くなることもあります。
ひとりで抱え込まず、専門家に相談することも大切です
真面目で責任感が強い方ほど、つらさを表に出すことが苦手で、「自分が悪い」「弱いから泣いてしまう」と責めてしまう傾向があります。しかし、本当に心やストレスが限界に近づいているときは、ひとりで解決しようとせず、医師や有資格の心理カウンセラーなど、専門家に相談することを検討してみてください。
話すだけでも気持ちが軽くなったり、自分では気づかなかった視点に出会えたりすることもあります。
涙は心からの大切なメッセージ。無理をせず、心と体を守る選択をしていきましょう。
ストレスとうつ病
私たちの日常生活には多くのストレス要因があり、それが心や体にさまざまな症状として現れることがよくあります。気分転換やセルフケアを行うことで、「気の持ちよう」で改善できる心理的な症状の場合、ストレスを発散するためのさまざまな方法が有効です。
心理的な症状の場合、ストレス要因から離れることで気分が落ち着き、症状が軽くなることが多いです。
しかし、症状が進行してうつ病などの脳に関わる問題に発展してしまった場合、「気の持ちよう」では改善できません。この場合は、医療的な対応が必要です。
もし「疲れているのに眠れない」「好きなことが楽しめない」といった状態が続くようであれば、精神科や心療内科に相談することをお勧めします。
ここまでストレスが限界になったときのサインと受診すべき徴候についてお伝えしました。症状として軽い場合も、早めに対処することが重要です。次にストレス解消法についてお伝えします。
ストレス解消法
ストレスを溜め込むことで、後々大きな心身の不調へとつながるおそれがあります。精神的に辛いときこそ、自分をいたわる対処法として、日頃からストレスを解消する習慣を持つことが大切です。
睡眠の質を上げ、しっかり休養する
睡眠は心身の疲労を回復させ、エネルギー充電に繋がり、ストレス解消のためにはとても重要です。質の良い睡眠によって、体内の修復を促す成長ホルモンが多く分泌され、疲労回復が促進されます。また自律神経も整いストレスが軽減されます。
考え事をして眠れない時の他、日中気分がザワザワする時、心を落ち着かせる効果がある自律訓練法もおすすめです。
心が落ち着く自律訓練法
①腹式呼吸を10回ほど行います
ベッドに仰向けになったり、椅子の背もたれにもたれかかったりするなど自分が楽だと感じられる姿勢をとります
②身体の感覚をイメージします
楽な呼吸をしながら次の言葉を心のなかで唱えながら、身体の感覚をイメージしていきます。
- 手足が重たい
- 手足が温かい
- 心臓が静かに脈打っている
- 楽に呼吸ができる
- お腹のあたりが温かい
- 額(ひたい)が涼しい
身体の感覚をイメージしていくうちに、思考の活動がおさまり、自然な眠りを導きます。
睡眠についての詳細は下記の記事において、眠れない原因や様々な不眠解消方法をお伝えしています。
食事内容を見直す
食事はメンタルヘルスにも影響を与えることが分かってきています。
メンタルヘルス不調の予防にはビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸などの栄養素を必要量摂取することが大事です。
ビタミンが不足することでうつ病の発症リスクを上げることになるといわれています。したがって、ビタミンB1、B2、B6、B12を多く含む卵や肉、大豆などの摂取が良いと思われます。
また、鉄や亜鉛の不足とうつ病に関連性があるという研究もありますのでミネラルの摂取も大事です。
さらに、うつ病に関係するといわれているセロトニンやドーパミン、ノルアドレナリンという脳内神経伝達物質はアミノ酸から作られています。したがって、アミノ酸が不足しないようにすることは重要です。アミノ酸はタンパク質から作られますから、たんぱく質をしっかりとることも重要です。
さらに、DHA (ドコサヘキサエン酸)やEPA (エイコサペンタエン酸)などの脂肪酸は魚に多く含まれており動脈硬化の予防効果のほか、神経保護作用や抗炎症作用などもあるとことが分かってきており、魚を多く食べている人は食べていない人に比べてうつ病のリスクが少ないという報告もあります。
バランスの取れた食事を続けることで、心身の安定につながります。
継続できる運動を取り入れる
ウォーキングや軽いランニングなど軽度な運動を継続的に行うことは、身体の健康だけではなく、ストレス解消に繋がりメンタルヘルス不調の緩和に効果的です。
外に出るのが難しい場合は、動画配信サイトなどで好みのエクササイズ動画を用いて運動を日常的に取り入れることをおすすめします。
自分の気持ちを「言葉にして吐き出す」
ストレスや不安、イライラ、悲しみといった感情は、心の中に溜め込んでいるだけでどんどん膨らみ、気づかないうちに心のキャパシティを超えてしまいます。特にストレスが限界に近づいているときは、思考が堂々巡りになりやすく、頭の中で考えれば考えるほど疲弊してしまうことがあります。
そんな時に効果的なのが、「気持ちを言葉にして外に出すこと」です。
言葉にすることで心が整う理由
言葉にすることには、次のような効果があります。
- 感情を客観的に見つめ直せる
- 思考の整理ができ、優先順位が明確になる
- 不安や混乱に「名前」がつくことで、心が落ち着く
- 自分の状態を受け入れやすくなる
たとえば、誰かに「なんだかしんどい」と話すだけでも、少し楽になることがあります。それは、言葉にすることで無意識の重荷が解放されるからです。
具体的な方法
日記やメモに書く:ネガティブなことも遠慮なく書き出してOKです。「今日イライラしたこと」「心配していること」など、書いて可視化するだけでも効果があります。
スマホのボイスメモに話す:誰かに話すように、思ったことを声に出して録音してみるのも有効です。
話を聞いてくれる人に話す:信頼できる家族や友人、同僚などに、愚痴や気持ちを共有してみましょう。
ポイントは「きれいにまとめようとしないこと」。感情はありのままに吐き出してよいのです。
ひとりで抱え込まない工夫を
責任感が強い人ほど、「弱音を吐くのはよくない」「周りに迷惑をかけたくない」「自分でなんとかしないと」と、無意識のうちに自分を追い込んでしまいがちです。しかし、限界を超えるまで我慢してしまうと、心や体に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
「助けを求める力」も、立派なストレス対処能力
一人で抱え込まず、人や専門機関に頼ることは「逃げ」ではありません。むしろ、自分を守るための大切なスキルです。
我慢を続けてしまう人は、「周囲に心配をかけたくない」「どうせ理解してもらえない」と感じていることも多いですが、話してみると想像以上に受け入れてもらえた、というケースも少なくありません。
こんなときは誰かに頼ってみましょう
- 泣くことが増えた
- 朝起きるのがつらい
- 気持ちがずっと沈んでいる
- ミスが増えて自己否定が止まらない
- 人と関わるのがしんどくなった
こうしたサインを感じたら、自分ひとりで何とかしようとせず、以下のような支援を頼ってみてください。
頼れる場所の例
身近な人に話す:家族、友人、職場の信頼できる人など
職場の産業医・メンタルヘルス窓口:匿名相談ができる場合もあります
医師・臨床心理士・公認心理師などの専門家:話を聞いてくれるだけでなく、専門的な対処法や選択肢を一緒に考えてくれます
自治体の相談窓口や電話相談:厚生労働省や都道府県でも24時間対応の相談窓口があります
自分が思っている以上に、助けを求めてもよいのです。
「今は少し弱っているだけ」「今はサポートを受ける時期なんだ」と、自分を責めず、必要なサポートを受けることが、回復への第一歩です。
それでも「誰にも頼れない」と感じるときは
中には、「そもそも頼れる人がいない」「家族にも友人にも話せない」「専門家に行くのも怖い」と感じている方もいるかもしれません。 そうした状況にいる方は、ストレスや苦しさを抱えながら、出口のない孤独の中にいるように感じているのではないでしょうか。
誰にも頼れないとき自分を支えるためには
書くことで、少しずつ自分を外に出す: 思ったことをメモやスマホに書き出すだけでも、気持ちの整理ができます。
“人ではない場所”を頼る: 匿名で利用できる電話やチャット相談を活用してみましょう。話すことで気持ちが和らぎます。
例えば厚生労働省では働く人の「こころの耳電話相談」を開設しています。
https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
小さなセルフケアを大切にする: 深呼吸、温かい飲み物、音楽、自然、散歩。誰にも頼らず、自分を少しだけ労わる時間も立派な回復の一歩です。
あなたは、ここまでよく頑張ってこられました。
「頼ってもいい」「休んでもいい」と、まずは自分に優しくすることから、次の一歩が始まります。
おわりに
以上、ストレスによる症状やストレスが限界に達したときの症状、ストレス解消方法についてお伝えしました。
生きている上でストレスは完全に避けることはできません。そのためストレスを溜めないように、自分にあったストレス対処法を取り入れることをおすすめします。
PR|ストレスマネージメント書籍紹介 (弊社代表・医師 渡辺洋一郎 著)
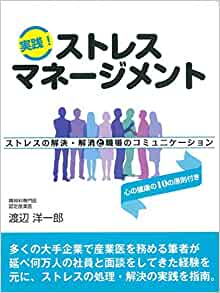
実践!ストレスマネージメントストレスの解決・解消と職場のコミュニケーション 心の健康10の原則付き
著者:渡辺 洋一郎 精神科専門医・認定産業医 弊社代表
出版社 : 公益財団法人日本生産性本部 労働情報センター
職場のコミュニケーションやチームワーク、ストレスを跳ね返す力であるレジリエンス、メンタル不調を防ぐためのストレスマネージメントとは何かについて、心の健康10の法則とともに解説しています。 ※クリックするとAmazonに飛びます。
Amazonで購入個人向け相談窓口(厚生労働省)
厚生労働省による「みんなのメンタルヘルス」では、こころの健康や病気、支援やサービス等、メンタルヘルス情報のポータルサイトです。相談窓口の案内等もあります。

出典
『実践!ストレスマネージメント』渡辺洋一郎
『こころに効く精神栄養学』功刀浩 (国立精神・神経医療研究センター)著,女子栄養大学出版部, 2016.3