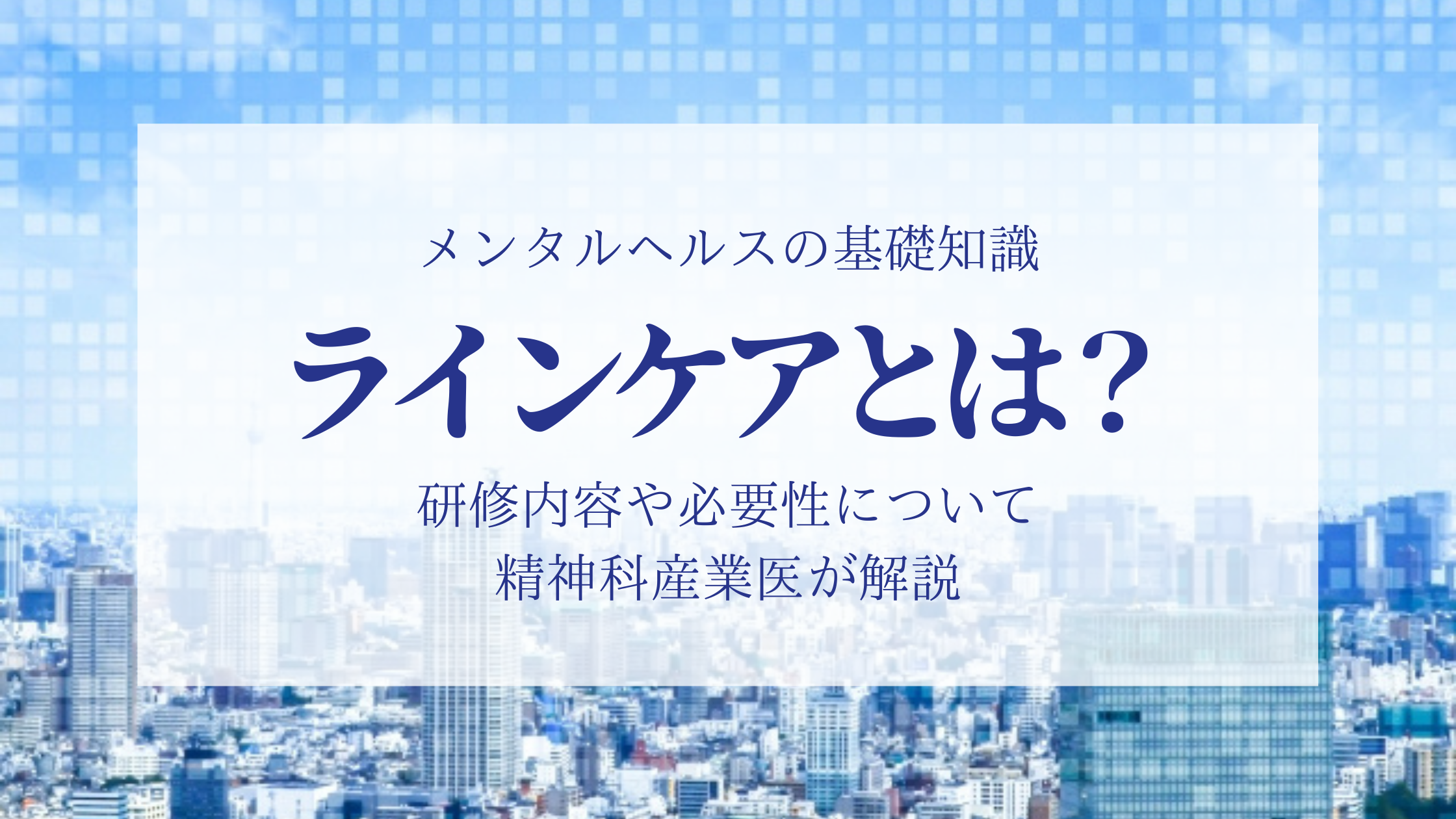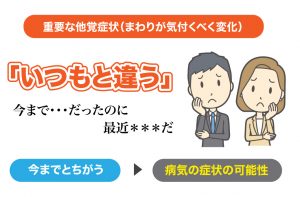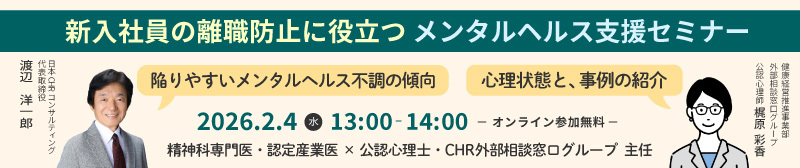「ラインケア」とは、職場でのメンタルヘルスケア対策において直属の上司など管理監督者が、部下のいつもとは違うという異変にいちはやく気づき、個別指導、面談、職場環境の改善を通じてストレスの軽減等に適切に対応することをいいます。
メンタルヘルスの不調は、本人も気づかぬうちに進行している場合もあり、ラインケアはとても重要です。
今回は、ラインケアとは何かについて説明するとともに、ラインケア研修内容やその必要性について精神科産業医が解説します。
ラインケアの具体的事例はこちらで解説しています。

ラインケアとは?
ラインケアとは、職場のライン上にいる直属の上司や管理者が、部下の普段とは異なる様子に早く気づき、その後に相談を行ったり職場環境を改善したりする取り組みのことです。
ラインケアの具体例として、上司が日常的に部下の様子に気を配り、様子がおかしいと感じる部下に対して適切に対応したり、部下からの相談に応じたり、メンタルヘルスに不調を抱える部下の職場復帰を支援したりすることが挙げられます。これらの取り組みによって、職場の心理的健康をサポートし、生産性の向上を図ることができます。
なぜラインケアが必要なのか
近年、職場におけるメンタルヘルス対策の必要性が高まる中で、「ラインケア」とその実践を支える「ラインケア研修」の重要性が急速に注目されています。これは一時的な流行ではなく、長期的に企業が健全な成長を目指すうえで、欠かすことのできない取り組みです。その背景には、社会構造や働き方の変化、そして企業のリスクマネジメントという観点があります。
メンタル不調の増加と職場への影響
うつ病や適応障害といったメンタル不調を抱える労働者は年々増加しており、それに伴う休職や退職は、企業にとって深刻な問題です。これらは単なる個人の健康問題にとどまらず、チームの生産性低下、業務停滞、人員の再配置による負担増加など、組織全体に大きな影響を及ぼします。特に中小企業においては、ひとりの不調が経営にも直結するケースも少なくありません。
管理職が第一線で担う「気づきと対応」
こうした状況において、最も重要な役割を果たすのが、現場の管理職です。部下と日常的に接しているからこそ、ちょっとした変化や異変にいち早く気づける立場にあります。しかし、多くの管理職が「どう対応していいかわからない」「声をかけるのが怖い」と感じており、対応を避けてしまうケースも少なくありません。だからこそ、ラインケアの考え方を理解し、具体的な対応スキルを学ぶ機会が必要なのです。
安全配慮義務と企業リスクの回避
さらに重要なのが、企業に課せられている「安全配慮義務」の存在です。従業員の心身の安全に配慮することは、企業の法的責任のひとつであり、これを怠った場合には、安全配慮義務違反として損害賠償や社会的信用の低下につながるリスクがあります。たとえば、部下の異変に気づきながら放置したことで、問題が深刻化した場合、管理職個人ではなく企業全体が責任を問われることもあります。
ラインケア研修は、こうした法的リスクを回避する意味でも有効です。管理職が「どのように対応すべきか」を理解し、行動に移せるようにすることで、企業のリスクマネジメント力が高まり、トラブルの未然防止にもつながります。
働き方の多様化と「心理的安全性」の確保
テレワークやフレックス制度の普及、業務のデジタル化といった働き方の変化により、従業員同士の関係性やマネジメントの在り方も大きく変わっています。直接顔を合わせる機会が減る中で、従来以上に「気づく力」や「丁寧な関わり」が求められるようになりました。
また、心理的安全性が確保されている職場は、従業員が自分の意見を安心して言える雰囲気を持ち、創造性やチームの一体感が高まりやすいことがわかっています。ラインケア研修を通じて、管理職が信頼関係を築き、風通しのよい職場づくりを実践できるようになることは、組織の活性化にも直結します。
こうした背景を受けて、国も職場におけるメンタルヘルス対策の重要性を重視しており、厚生労働省はその実践的な指針として「4つのケア」という枠組みを示しています。ラインケアはこの「4つのケア」のひとつとして位置づけられており、職場でのメンタルヘルスを支える重要な柱とされています。
それでは4つのケアについて簡単に見ていきましょう。
厚生労働省による「4つのケア」

厚生労働省による「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、4つのケアが事業場の中で1つのシステムとして機能することがメンタルヘルスケアにおいて効果的であるとしています。この4つのケアのうち、管理監督者が中心的な役割を果たす事業内のケアが「ラインケア」です。
まず、4つのケアの内容について見ていきます。
セルフケア
セルフケアとは、社員一人一人が主体的にストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解を身に着け、自分のストレスに気づいて対処することをいいます。
企業としては、社員が自身のメンタルの状況について把握できるような機会や、セルフケアを効率的に行えるような知識の提供、メンタル不調について相談できる体制づくりが重要となります。
ラインによるケア
ラインによるケアとは、職場の管理監督者が主体となり役割を果たす事業所内のケアのことを言います。例えば、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰における支援などが挙げられます。より詳しい具体的な内容については後述します。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内産業保健スタッフ等によるケアとは、産業医、保健師や人事労務管理スタッフ等によるケアのことをいいます。担当スタッフが社内の心の健康づくり計画の実施に関して、中心的な役割を担います。
具体的には、メンタルヘルスケアの実施に関する企画立案、個人の健康情報の取扱い、事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口、職場復帰における支援、などが挙げられ、現場と連携し職場環境改善を推進します。
事業外資源によるケア
事業外資源によるケアとは、第三者の専門的な機関や専門家を活用し、その支援を受けることをいいます。具体的には、外部相談窓口や外部の専門家による復職支援などが挙げられます。
ラインケアの具体的な取り組み内容

ラインケアの取り組み内容について具体的に見ていきます。
メンタル不調の兆候
メンタルヘルス不調の兆候としては、
・頭が重い,肩がこる,食欲がなくなる,眠りにくくなる,イライ
・口数が少なくなる,表情が乏しくなる,緊張しやすい,休みがち
さまざまな症状があります。これはだれしも経験するものです
重要なことは、「どうなったら医療を受けるべきか」「どうなった
という点です。
医療が必要なメンタルヘルス不調の見分け方
医療が必要なメンタルヘルス不調の見分けるには、周りからみて「いつもと違う」という気付きが重要です。
例えば・・・・・・
・今まで欠勤などなかったのに休みがちになっている。
・元気な人だったのに最近表情に乏しい。
・ミスがなかった人なのに簡単なミスが続くようになった。
・今まで穏やかな人だったのに、周囲に当たるような言動がみられる
以上の兆候が挙げられます。
今までできていたことができなくなる、あるいは、今までし
部下にこのような兆候が見られたとき、どのように対応したらよい
対応のポイント
部下に上記のような様子が見られたとき、まずは次のことを本人に確認します。
Q:「睡眠はとれてる?」
Q:「好きなこと楽しめてる?」
【YESの場合】
もし睡眠がとれていて、好きなことも楽しめているという言う場合は、その時点では一時的な落ち込みと捉え、本人の話を丁寧にきき、業務上の問題として支援や対応を考えます。またこのとき産業医と連携をとることも重要です。
【NOの場合】
睡眠がとれていない場合、また好きなことを楽しめていない場合は、メンタルヘルス不調や健康問題の可能性があります。原因の有無・内容に関わらず、産業医・医師への相談や受診を促します。
部下からの相談への対応
ラインケアにおいて管理監督者は、部下からの相談に対応することが重要です。自発的な相談はもちろん、相談しやすい雰囲気や環境を整えることが大切です。
長時間労働など付加がかかっており個別に対応が必要と思われる部下に対しては、管理者自ら声をかける対応も必要となります。管理監督者が部下の話を積極的に聴くことで、職場の人間関係の把握や、メンタルヘルス不調の早期発見・適切な対応をとることにも繋がります。
事業所としては、管理監督者が部下の話を聴く技術、積極的傾聴法などを習得するための研修の開催など重要となります。
メンタルヘルス不調の部下の職場復帰への支援
メンタルヘルス不調で部下が休職しその後職場復帰する場合、管理監督者は、復職者が安心して職場復帰できるよう支援する必要があります。
具体的な方法としては、復職者の話を積極的に聴くことで復職者との信頼関係を築きます。管理監督者と復職者との良好な関係は、職場の雰囲気をよりよくすることにも繋がります。
職場環境の改善を通じたストレスの軽減
職場環境によって様々なストレスをもたらすことがあります。例えば、職場の照明や温度、作業レイアウトを変えることで働く人の心理的ストレスを軽減することにつながる場合があります。
職場環境は物理的な環境だけではなく、仕事量や裁量権、報酬内容も挙げられます。仕事の量や責任に見合う裁量権や報酬が与えられることも職場環境改善に繋がります。
ラインケア研修とは?

すでにご紹介したように、ラインケアとは、管理職が部下のメンタルヘルスに配慮し、日常的なコミュニケーションや職場環境の調整を通じて不調を未然に防ぐ取り組みを指します。こうした取り組みを実効性あるものにするには、管理職が適切な知識とスキルを持っていることが前提です。
そこで注目されているのが「ラインケア研修」です。これは、管理職が職場でメンタルヘルスケアを実践できるようになるための教育プログラムであり、企業の健康経営やリスクマネジメントの要ともいえる施策です。
安全配慮義務とラインケアの関係
企業には、従業員が心身ともに安全に働けるように配慮する「安全配慮義務」が法律上課されています。もし、部下のメンタル不調の兆候を見逃し、必要な対応を怠った結果として重大な健康被害や自殺などにつながった場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
実際に、過去には「上司が異変に気づきながら何の対応も取らなかった」として企業の法的責任が問われた事例もあります。ラインケア研修は、こうしたリスクを軽減するために、管理職がどのように行動すべきかを具体的に学ぶ重要な機会となります。
ラインケア研修の目的と内容
ラインケア研修の主な目的は、管理職が部下のメンタル不調に「気づき」「声をかけ」「必要な対応につなげる」一連のスキルを習得することです。
研修ではまず、メンタルヘルスの基礎知識が提供されます。うつ病や適応障害などの代表的な疾患の特徴、ストレスの仕組み、メンタル不調の初期サインといった内容を学ぶことで、管理職が不調の兆しに早く気づけるようになります。
次に、部下との信頼関係構築に欠かせないコミュニケーションスキルの習得が行われます。日常の声かけや1on1面談での傾聴・共感・非指示的な対応など、相談しやすい環境をつくる方法がロールプレイなどを通して実践的に学べます。
また、実際に不調が疑われる部下がいた場合の対応も重要です。産業医や人事部門、社外のカウンセリング機関への適切な連携方法、本人への配慮と職場復帰支援の基本など、実務に即した対応の判断力を育てます。
さらに、職場のストレス要因を減らすためのマネジメント方法や、ハラスメント防止、心理的安全性の高い職場環境づくりについても触れるなど、単なる「不調対応」にとどまらない広範な内容が特徴です。
ラインケア研修の効果と企業にもたらすメリット
ラインケア研修を実施することで、企業や職場、そして従業員本人に対して多面的なメリットが生まれます。
部下の異変に気づく
まず、管理職が部下の異変に気づき、早期に声をかけ、必要な支援につなげる力を身につけることで、メンタル不調の深刻化を防ぐ一次予防が実現します。結果として、休職や離職の防止、医療コストの抑制につながり、企業の人的損失を最小限に抑えることが可能になります。
職場の心理的安全性を高める
次に、職場における「心理的安全性」が高まり、従業員が安心して働ける環境が整います。これは、職場のエンゲージメント向上や離職率の低下、チームの生産性向上といったプラスの波及効果をもたらします。信頼できる上司の存在は、従業員の満足度や定着率にも大きく関わってくるのです。
企業のリスクマネジメント
さらに重要なのが、企業のリスクマネジメントとしての側面です。前述した通り、対応の不備によって安全配慮義務違反とみなされれば、企業には多大な法的・社会的責任が生じます。ラインケア研修を導入し、管理職が適切な対応を習慣化することで、そうしたリスクを大幅に軽減することができます。
管理職自身のマネジメント力向上にもつながる
ラインケア研修は、部下対応のスキル習得にとどまらず、管理職自身のマネジメント力向上にもつながります。研修で学ぶ観察力や傾聴力は、日常の1on1やフィードバックの質を高め、信頼関係の構築に役立ちます。また、適切な判断力を身につけることで、トラブルやハラスメントの予防にもつながります。
さらに、自分のストレスや限界にも気づく視点が養われるため、自己管理力や持続可能なリーダーシップの形成にも効果的です。
こんな課題を感じたら、ラインケア研修導入のタイミング
ラインケア研修は、すべての企業にとって「今すぐ必要」といっても過言ではありませんが、特に以下のような課題や兆しが見られる場合は、導入のタイミングと捉えるべきです。放置すれば職場全体のモチベーションや生産性、そして企業のリスクにまで影響する可能性があります。
部下の不調に気づいても対応できない管理職が多い
「様子がおかしいとは思ったけれど、どう声をかけていいか分からなかった」「何をしたらいいか分からず、そのままにしてしまった」──こうした声は多くの現場で聞かれます。管理職が気づいていても対応できない、もしくは対応に自信がないという状態は、メンタル不調の見逃しや放置につながりかねません。
休職・離職者が増えている、またはその予兆がある
最近、メンタル不調を理由とする休職者が増えている、退職理由に「人間関係」や「精神的なストレス」が目立つ、といった状況は、職場のケア体制が十分でないサインです。未然に不調を防ぐ一次予防の仕組みを整えることが急務です。
管理職と部下の関係がギクシャクしている
1on1ミーティングが形骸化していたり、部下が上司に相談しづらい雰囲気がある場合、職場の心理的安全性が確保されていない可能性があります。ラインケア研修は、管理職のコミュニケーション力を底上げし、信頼関係の再構築にもつながります。
ハラスメントへの不安が高まっている
近年はコンプライアンス意識の高まりから、ハラスメントリスクへの懸念が強まっています。「どこまでが適切な指導か分からない」といった不安を抱える管理職が多い場合、ラインケア研修によって“適切な関わり方”を学ぶことが予防策となります。
組織としてメンタルヘルス対策が属人的になっている
産業医や人事担当者が対応に追われているものの、管理職の理解や協力が不十分で、全体としてのメンタルヘルス体制が脆弱になっているケースもよく見られます。ラインケア研修は、組織全体で支える体制づくりの第一歩として有効です。
このような課題に心当たりがある場合、ラインケア研修は「対症療法」ではなく「体質改善」の一手になります。早めの導入が、健全で持続可能な職場づくりにつながるはずです。
自社に合ったラインケア研修の選び方
ラインケア研修を導入しようと考えたとき、まず悩むのが「どの研修を選べばよいのか」という点です。ラインケアの重要性が認識される一方で、提供している団体や内容、形式は多種多様です。自社にとって効果的な研修を選ぶためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
研修の目的が明確になっているか
まず大切なのは、「何のために研修を実施するのか」という目的を明確にすることです。
たとえば、「部下とのコミュニケーションを改善したい」「メンタル不調の早期発見と対応力を高めたい」「ハラスメント防止につなげたい」など、自社の課題やゴールに合った内容を選ぶことが重要です。目的が不明確なままだと、研修内容と現場のニーズがかみ合わず、効果が薄れてしまうことがあります。
管理職が受けやすい形式になっているか
研修の形式(対面/オンライン/オンデマンド)も選定の重要なポイントです。忙しい管理職が受講しやすいように、時間や場所を柔軟に調整できる形式を選ぶことも有効です。特に最近は、録画視聴型のeラーニングを組み合わせることで、集合研修の負担を軽減しながら継続的な学びができる設計が人気です。
実践的な内容になっているか
「理論だけで終わる研修」では、現場に活かされにくくなります。具体的なケーススタディやロールプレイを含む実践的な研修であるかどうかを確認しましょう。受講者が「自分ごと」として捉えられる内容であることが、研修効果を高めるカギになります。
講師の専門性・実績
講師の専門性も見逃せません。精神科産業医や臨床心理士、企業内でのメンタルヘルス支援実績がある講師であれば、現場に即した具体的なアドバイスが期待できます。また、同業界での導入実績がある研修会社であれば、職場の実情に即した内容が提供されやすく、導入後のサポート体制にも安心感があります。
受講後のフォロー体制があるか
研修は「やりっぱなし」にせず、受講後の振り返りや実践サポートがあると、定着度が大きく変わります。社内で継続的な学びを促すツールや、必要に応じたフォローアップ研修、管理職同士の交流機会などを提供している研修会社を選ぶと、継続的な効果が期待できます。
ラインケア研修は、導入すれば終わりではありません。職場の文化として根づかせるためにも、「続けられる」「活かせる」研修を選ぶことが、成功のカギとなります。
おすすめの研修会社の選び方
ラインケア研修の内容が重要なのはもちろんですが、それを提供する「研修会社の質」も研修の成果を大きく左右します。多数ある中から信頼できるパートナーを選ぶために、以下の視点をチェックしておきましょう。
実績・信頼性があるか
まず確認したいのが、研修会社としての実績です。メンタルヘルス研修に特化しているか、また、これまでにどのような企業や業種への導入実績があるかをチェックしましょう。できれば、自社と似た業種・規模の導入事例がある会社だと、現場の実態に合った提案が期待できます。
また、精神科産業医や臨床心理士などの専門家と連携している会社であれば、より専門性の高いサポートを受けられる可能性があります。
カスタマイズ対応が可能か
企業によって抱える課題や職場の状況はさまざまです。テンプレート的な一斉講義だけでなく、自社の課題や階層に合わせた内容を柔軟に設計してくれる研修会社であるかどうかも大切です。たとえば、「初任管理職向け」と「ベテラン管理職向け」で、アプローチや事例を変えてくれると、受講者の満足度が高くなります。
アフターフォローや社内浸透の支援があるか
研修後のフォロー体制や、社内全体にラインケアを浸透させるサポートがある会社は、継続的な効果が期待できます。研修報告書の提供、アンケートによる効果測定、定期的なフォローアップ研修の提案など、実施後の伴走支援まで見据えているかも確認ポイントです。
ラインケア研修を選ぶときのチェックリスト
最後に、研修を選ぶ際に確認すべきポイントをチェックリストとして整理しました。導入前の検討に、ぜひお役立てください。
ラインケア研修チェックリスト
□ 自社の課題・目的に合った内容か(例:不調の早期発見、管理職の対応力向上など)
□ 研修形式は管理職が参加しやすいものか(例:対面/オンライン/オンデマンドなど)
□ 実践的な内容になっているか(例:ケーススタディ、ロールプレイなど)
□ 講師の専門性は信頼できるか(例:産業医、臨床心理士、現場経験者など)
□ 自社と同じ業種・規模への導入実績があるか
□ カスタマイズ対応が可能か(階層別や課題別に内容調整できるか)
□ 受講後の振り返りやフォロー体制が整っているか
□ 費用対効果が見込める内容か
□ 社内での定着・文化づくりまで支援してくれるか
「導入すること」ではなく「活かすこと」がゴールであることを意識して、ぜひ最適な研修を選んでください。
おわりに
メンタルヘルスへの対応は、今や一部の人だけの課題ではなく、すべての企業にとって避けて通れないテーマとなっています。その中で、日々部下と関わる管理職が適切な「気づき」と「対応」ができるかどうかは、職場全体の健全性を大きく左右します。
ラインケア研修は、単なる知識習得にとどまらず、管理職の成長、職場の信頼関係づくり、そして企業の持続的な発展にもつながる重要な取り組みです。
「うちの職場にも必要かもしれない」と感じた今こそが、第一歩を踏み出すベストなタイミングです。
従業員が安心して働ける職場づくりのために、ぜひこの機会にラインケア研修の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
(参照)厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
弊社では、精神科産業医が監修・登壇する「ラインケア研修」をはじめ、職場のメンタルヘルス課題に対応する各種研修プログラムを提供しています。管理職の対応力を高めたい、職場の心理的安全性を向上させたいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
詳しくは下記のボタンから無料資料をダウンロードください。