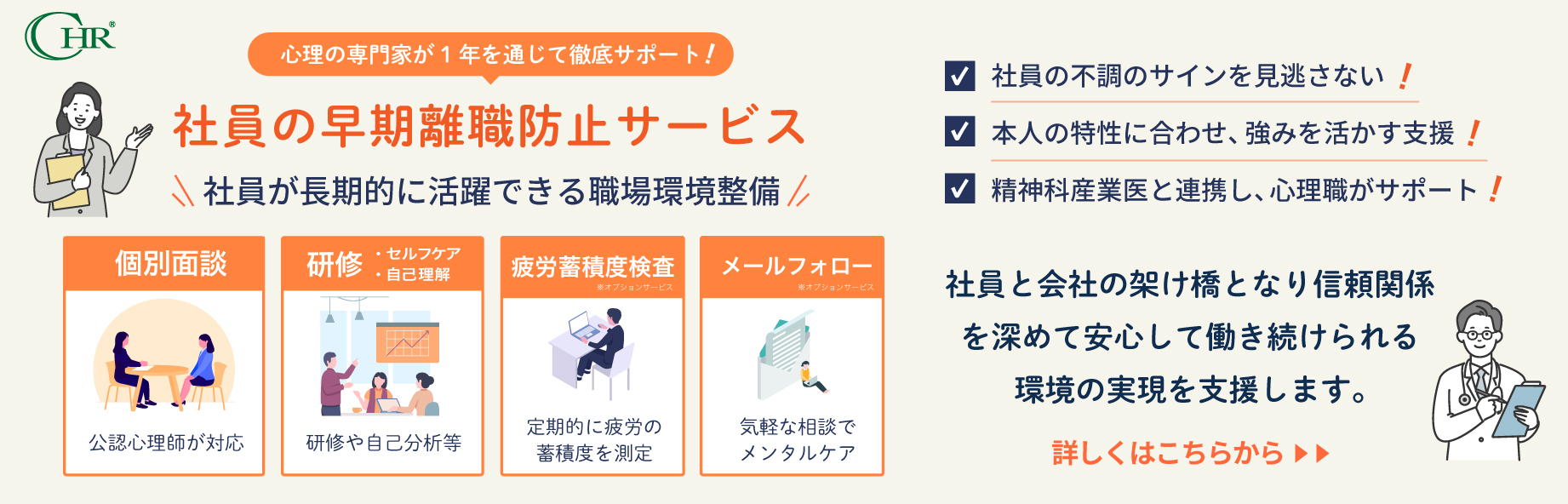職場で信頼され、成果を上げていた社員が突然退職を申し出た⋯⋯、そんな経験に驚いたことはありませんか?
実は、スキルが高く信頼されている辞めてほしくない人ほど、自らの将来や環境に敏感に反応し、思い切った決断をすることが少なくありません。
優秀な人材の離職は、単に戦力が減るだけでなく、チーム全体の士気や生産性の低下、さらには他の社員への連鎖的な影響を引き起こすリスクもあります。
そのため、企業としては彼らが辞める前にその兆候を把握し、的確な対応をとることが求められます。
今回は、辞めてほしくない人がなぜ辞めてしまうのか、その背景にある要因や行動の兆しを探るとともに、離職を未然に防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。
辞めてほしくない人の特徴とは?
優秀な社員の退職は、企業にとって大きな痛手となります。
ここでは、企業が「この人には辞めてほしくない」と感じる社員に共通する特徴を詳しく解説します。
高いパフォーマンスを発揮する社員
まず挙げられるのが、常に成果を出し続ける社員です。
業績目標の達成はもちろんのこと、周囲の業務を牽引する存在であり、いなくなることでプロジェクトの進行や売上に直結する影響を及ぼすケースもあります。
特に営業職やプロジェクトマネージャーなど、明確な成果指標があるポジションでは、その影響の大きさは計り知れません。
また、高い目標意識や自走力を持つため、周囲の社員にとっても刺激となり、チーム全体のレベルアップに貢献していることが多いのも特徴です。
専門性やスキルを持つ社員
社内に数人しかいない専門分野の技術者や、特定の顧客対応を長年担ってきた社員など、代替が難しいスキルを持つ人材も、会社としては絶対に手放したくない存在です。
このような社員が退職すると、後任の育成に時間とコストがかかり、引き継ぎもうまくいかなければ業務停滞や品質低下のリスクも伴います。
また、こうしたスキル人材は転職市場でも引く手あまたであり、自社にとどまってもらうためには、働きがいや待遇面での配慮が不可欠です。
チームのムードメーカー
一見、業務上のパフォーマンスに直接関係ないように見えて、実はとても重要なのが職場の空気を良くする人です。
例えば、自然とメンバーに声をかけて場を和ませたり、困っている人がいたらすぐに気づいてフォローしたりといった行動をとる社員は、チームの潤滑油のような存在です。
こうしたムードメーカーがいなくなると、メンバー同士の会話が減り、目に見えない形で職場の空気が悪化することがあります。
その結果として、他の社員の定着率にも影響が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。
辞めてほしくない人が辞める主な原因
単なる待遇不満だけではなく、働き方や価値観の多様化、職場との相性など、優秀な人材が離職を選ぶ理由はますます複雑化しています。
ここでは、現代の職場で起こりやすい見えにくい離職理由を含め、5つの主な原因を掘り下げて解説します。
正当に評価されない
成果を出しているにもかかわらず「誰からも認められていない」「頑張っても意味がない」と感じたとき、人は徐々に離職を意識します。
昇進や給与だけでなく、日々の「ありがとう」「助かった」といった声かけや、具体的なフィードバックがあるかどうかがカギです。
特に近年の若手社員はプロセス評価や存在承認を重視する傾向が強く、結果だけでなく自分の取り組み姿勢を見てほしいと感じていることが多いです。
評価制度の整備とともに、日常的なコミュニケーションの質も見直す必要があります。
成長実感が持てない
スキルアップにつながる仕事を任せてもらえない、フィードバックも研修もなく「このままでいいのか」と感じる。
このような環境では、成長志向の高い社員ほど不安を抱え、キャリアを見直す動きが加速します。
特に若い世代を中心に「自己実現」や「スキルポータビリティ(会社に依存しないキャリア)」への関心が高まっており、成長機会が乏しい職場は見切られやすいリスクがあります。
目先の業務だけでなく、中長期的にどんなスキルが身につき、どのように活躍できるのかを、企業側が提示していくことが求められています。
会社の将来性が見えない
事業の方向性が不明確、トップの発言に一貫性がない、新しい取り組みに消極的…。
このような経営上の不信感が積み重なると、社員は「自分の時間をこの会社に預ける価値があるのか」と疑問を抱くようになります。
また、環境・ダイバーシティ・働き方など社会的テーマへの取り組みにも関心が高まる中、「自分の価値観と企業の姿勢が合わない」と感じた瞬間に転職を考える若手も増えています。
企業理念や経営方針を内向きではなく、社員一人ひとりと共有・共感できる形で発信することが重要です。
ライフスタイルの変化に対応できない
働く人の生活スタイルは多様化しており、育児や介護、副業、病気治療など、それぞれに配慮が必要なケースが増えています。
にもかかわらず「みんな同じように働くべき」という旧来型の労働観を押しつけると、「ここでは無理」と離職を選ぶ人も出てきます。
特に女性や中高年層においては、柔軟な勤務体系や職場の理解が離職防止のカギとなる場合も多く、制度よりも実際に配慮してくれる風土があるかが問われます。
画一的な制度ではなく、個別事情に寄り添った対応が信頼関係を築くポイントです。
人間関係の問題・心理的安全性の欠如
上司からの圧力、同僚との摩擦、誰にも相談できない孤立感。
これらは一見些細なことに見えても、本人にとっては退職の大きな決断理由となります。
特に最近では、心理的安全性のある職場が注目されており、安心して自分の意見や悩みを打ち明けられる環境であるかが、社員の定着に直結します。
表面上はうまくやっているように見える社員ほど、本音を吐き出せずにストレスをため込んでいる場合もあり、マネジメント側の観察力と傾聴力が重要です。
辞めたいと言っている人を強引に引き止めることはできない
どれだけ会社にとって重要な人材であっても、本人が退職の意思を示した場合、その意志を尊重することが原則です。
労働者には退職の自由があり、会社側が一方的に引き止めることはできません。
退職はいつから可能か?法律上のルール
民法第627条第1項によれば、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職の申し入れができ、申し出から2週間が経過すれば契約を終了することができます。
つまり、原則として退職希望者は会社の合意がなくても、2週間の経過をもって法的に退職が可能です。
民法 第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条第1項
なお、就業規則で「1ヶ月前に申し出ること」などの規定がある場合でも、それが法的拘束力を持つとは限らず、基本的には民法の定めが優先されます。
ただし、業務の引き継ぎや円満退職を希望する場合は、実務上は1ヶ月程度前の申告が望ましいとされています。
「引き止め」ではなく「対話」が重要
大切なのは、無理に辞意を覆させようとすることではなく、「なぜその決断に至ったのか」を誠実に聞き取る姿勢です。
本人の思いに丁寧に耳を傾け、会社側に改善できる要因があれば、それを明確に示すことが、結果的に信頼関係を築き、引き止めにつながる可能性もあります。
辞めてほしくない人が辞めるのを引き止めるには?
突然、信頼していた社員から退職の意向を伝えられたとき、焦ってしまうのは当然のことです。しかし、そこで感情的になったり、強く引き止めようとすることは逆効果になることもあります。
大切なのは、「引き止めること」ではなく、「信頼に基づいた対話を通じて、本人の意思を尊重しながらも、選択肢を広げること」。
ここでは、辞めてほしくない人から退職の申し出を受けた際に取るべきステップを、順を追って紹介します。
ステップ1|まずは感情的にならず、冷静に話を聞く
突然の退職相談に驚いたとしても、まずは冷静に受け止めましょう。
「なぜ?」と問い詰めたり、「辞めないでほしい」とすぐに言ってしまうと、本人は圧を感じてしまいます。
ここで重要なのは、否定せずに最後まで話を聞く姿勢です。
ステップ2|退職理由を丁寧にヒアリングする
「ご自身のキャリアの中で何かお考えがあったのでしょうか?」「困っていることがあれば聞かせてください」といった、オープンな質問で本音を引き出しましょう。
退職理由が環境や人間関係、評価制度など会社側で改善できるものであれば、解決策を提案できる余地が見えてくるかもしれません。
ステップ3|代替案を提示する(異動・働き方・待遇の改善など)
本人の悩みに対して、辞める以外の選択肢があることを具体的に示しましょう。たとえば以下のような対応が考えられます。
- 負担のかかっている業務の見直し・軽減
- 部署異動や上司との配置転換
- 柔軟な勤務形態(在宅・時短など)の導入
- 評価・処遇の見直しの検討
ただし、条件を提示する際は取引材料のような言い方を避け、本人にとってより良い環境を提供したいという誠意を伝えることが重要です。
ステップ4|検討の時間を設け、最終判断は本人に委ねる
一度の面談で決断を急がせるのではなく、「いったん持ち帰って、数日考えてもらえますか?」と時間の猶予を与えましょう。
この間に、会社としてできる対応を整理し、再度面談の場を設けて丁寧に提案することが大切です。
最終的には本人の意思を尊重し、自律的な判断を後押しする姿勢が、長期的な信頼関係につながります。
ステップ5|退職の意思が固い場合は、前向きな見送りを
引き止めの結果、本人の気持ちが変わらなかったとしても、それを尊重し、これまでの貢献に感謝を伝えて送り出すことが大切です。
退職後の関係性や再雇用の可能性も視野に入れ、「辞めても縁が切れるわけではない」と伝えておくことで、将来的な再接点にもつながります。
このように、辞めてほしくない人への対応は「止める」ではなく、「共に考え、最善を模索すること」。
本人の考えや気持ちに寄り添い、可能な限り誠実な対応をすることで、結果的に引き止めにつながるケースも少なくありません。
次の項目では、辞めてほしくない人材の離職を防ぐために、企業としてできる具体的な対策を紹介します。
普段から備えておくべき取り組みを知ることで、「辞めたい」と言われる前にアクションを起こせる体制づくりを目指しましょう。
辞めてほしくない人を引き止めるための対策
優秀な社員の退職を防ぐには、「辞めたい」と言われたときだけでなく、日頃から離職リスクを下げる環境づくりが何より重要です。
ここでは、企業として実践可能な5つの主要な取り組みを紹介します。
適切な評価制度の導入
努力や成果がきちんと評価されているという実感が、社員のモチベーション維持に直結します。
「何を頑張れば評価されるのか」が明確になっていなかったり、上司の主観で判断されていると感じれば、やる気は徐々に失われていきます。
目標管理制度(MBO)や360度評価(多面評価)など、定量・定性の両面からの評価をバランスよく取り入れ、評価基準をオープンにすることで、納得感と公正性を担保できます。
キャリアパスの明確化
「自分がこの会社で将来どうなれるのか」「どんなスキルを身につけられるのか」が見えていないと、成長意欲が高い社員ほど離職を考えるようになります。
そこで、職種別のキャリアパスを提示したり、上司とのキャリア面談を定期的に実施するなど、社員一人ひとりに合った成長支援を行うことが大切です。
あわせて資格取得支援や社内公募制度など、チャレンジを後押しする仕組みも有効です。
柔軟な働き方の推進
ライフスタイルや価値観の多様化が進む中で、働く時間や場所の柔軟性があるかどうかは、社員の定着率に大きく影響します。
テレワーク、時短勤務、フレックス、副業許可など、状況に応じた働き方を選べる制度設計が求められます。
制度を整えるだけでなく、制度が使いやすい風土があることも非常に重要です。
制度があっても使えない雰囲気では、意味をなしません。
コミュニケーションの活性化
上司と部下の関係性が希薄だと、不満や悩みが表に出にくくなり、突然の退職につながりかねません。
1on1ミーティングや定期的なフィードバックの場を設けることで、気づきと信頼の接点を増やしていきましょう。
「最近どう?」の一言でも、部下にとっては相談のきっかけになる場合があります。
業務の話だけでなく、キャリアや気持ちの面にも触れる時間をつくることが理想です。
人間関係の改善
職場の人間関係は、退職理由として非常に多い要因です。
そのため、チームビルディング研修やリーダー向けのコミュニケーション研修を通じて、互いを尊重しやすい関係性を築く環境整備が欠かせません。
また、社内チャットや朝会など、日常的に気軽にやり取りできる場をつくることで、心理的な距離が縮まりやすくなります。
退職の兆候を見逃さないために
「突然辞めたいと言われた」と感じることもあるかもしれませんが、実はその前に、小さなサインや違和感が現れているケースが多くあります。
ここでは、日頃から意識すべき観察ポイントと対話の重要性について紹介します。
行動の変化に注目する
以下のような変化が見られた場合は、心の中で何かが起きているサインかもしれません。
- 遅刻・早退・欠勤が増えた
- 残業や休日出勤を極端に避けるようになった
- 明らかに業務への集中度が下がっている
- 社内での雑談や笑顔が減った
こうした変化に気づいたとき、「大丈夫?」と一言かけるだけでも、気持ちを軽くすることに繋がります。
定期的な面談の実施
1on1面談やキャリア面談を通じて、業務外の悩みや希望を把握することで、社員の変化にいち早く気づくことができます。
「何もないときでも話す習慣」をつくっておくことで、いざという時にも本音を話しやすい関係性が築かれます。
「忙しくて余裕がない」と放置してしまうと、気づいた時には手遅れということにもなりかねません。
日常的な対話をルーチンに組み込むことが、離職予防の第一歩です。
おわりに
企業の発展には、単に人手がそろっていることではなく、信頼され、活躍し続ける人材が定着していることが不可欠です。
特に成果を出していたり、チームの要となっている社員が突然退職することは、業務だけでなく職場全体の士気や組織文化にも大きな影響を与えかねません。
しかし、優秀な人材の離職はある日突然のように見えても、その前には必ず何らかのサインやきっかけが存在しています。
日頃から社員一人ひとりと向き合い、どんなことに不安を持っているのかに耳を傾けることが、最も効果的な離職防止策といえるでしょう。
「辞めたい」と言われてから動くのではなく、辞めようと思わせない組織をつくることが重要です。