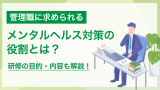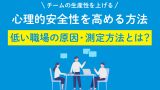近年、職場における「メンタルヘルス」は、人事労務や経営層にとって避けて通れないテーマとなっています。厚生労働省が公表した2023年(令和5年)の労働安全衛生調査によれば、労働者の8割以上が「強いストレスを感じている」と回答しており、その背景には長時間労働や人間関係の複雑化、働き方の多様化などがあります。
この記事では、職場でのメンタルヘルスの課題と有効な対策、さらに研修の活用ポイントについて解説します。
はじめに
厚生労働省の最新調査(令和6年)によれば、事業所全体の63.2%がメンタルヘルス対策に取り組んでいるとされています(令和5年は63.8%)。事業所規模別にみると、労働者50人以上の事業所では94.3%、30~49人規模では69.1%、10~29人規模では55.3%が実施しており、大企業を中心に対策はほぼ定着しています。
取り組み内容としては、
-
ストレスチェックの実施:65.3%
-
職場環境の評価・改善(集団分析を含む):54.7%
が上位を占め、形としての対策は着実に広がっています。
参考:厚生労働省 令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況
しかし、これだけ多くの事業所が取り組んでいるにもかかわらず、厚生労働省の統計によると、業務による精神障害の労災補償請求件数、決定件数、そして支給決定件数はいずれも増加傾向にあり、職場の心の健康問題が深刻化している現状が浮き彫りになっています。
取り組みの数は増えていても、社員の行動変容や管理職の支援力といった質の部分が十分でないため、効果が出にくいのが現状です。その解決策として注目されているのが 研修による職場メンタルヘルス対策です。本記事では、直近の課題や研修でできることを解説します。
メンタルヘルスとは?
メンタルヘルスは、人がいきいきと働き、仕事への意欲を保つ上で不可欠な、心の健康状態を指す言葉です。
一方、メンタルヘルスが損なわれると、メンタルヘルス不調と呼ばれる状態になります。これには、うつ病のような精神疾患だけでなく、ストレスや個人的な問題によって気分が落ち込む状態も含まれます。
企業は、従業員がこのような不調に陥らないよう、積極的にメンタルヘルス対策を講じ、支援体制を構築していくことが重要です。
職場メンタルヘルスの現状と課題
まず、現場でよく見られるメンタルヘルス不調に関する課題を整理してみましょう。
プレゼンティーイズム(心身不調を抱えたまま勤務する状態)
生産性の低下だけでなく、周囲への影響も大きく、企業全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。
休職・離職リスク
職場でのメンタル不調は、長期休職や退職につながりやすく、人員確保や職場全体のモチベーション低下といった課題を引き起こします。重要なのは、問題が顕在化してからの対応ではなく、予防的な仕組みの整備です。
管理職の対応負担
管理職は、日常業務に加え、部下のメンタル不調への対応も求められ、その負担は年々増加しています。適切な知識やスキル、相談先が整備されていない場合、管理職自身の疲弊やストレス増大につながり、組織全体の生産性低下や離職リスクの増加といった課題を引き起こす可能性があります。部下の変化に気づけない、声をかけてもどう対応していいかわからないといった声は少なくありません。
リモートワーク下の孤立感
リモートワークの普及により、従業員同士の直接的な交流が減り、孤立感や不安感を抱えるケースが増えています。特に新入社員や若手は職場の人間関係や業務上の情報共有が希薄になりやすく、心理的負担が大きくなる傾向があります。孤立感はモチベーション低下や業務効率の低下、さらには休職・離職リスクにもつながります。
こうした課題に対し、企業には単に制度づくりを行うだけでなく、従業員一人ひとりの行動や組織文化に変化をもたらす人と組織の力を高める教育や研修が求められています。なぜなら、メンタルヘルスの課題は制度だけでは十分に解決できず、現場での具体的な対応や同僚との関わり方、ストレスへの気づきと対処といった行動面が重要だからです。
次に、健康経営に不可欠な要素を見ていきましょう。
健康経営に欠かせない主要アプローチ
企業が持続的に成長していくためには、従業員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境づくりが欠かせません。その実現には、単なる制度整備にとどまらず、組織全体の文化や風土に根づくアプローチが重要です。
ウェルビーイング経営
ウェルビーイング(Well-being)は、心身ともに満たされた状態を意味する概念で、単なる病気の予防を超えて社員一人ひとりがいきいきと働ける状態をつくることに注目が集まっています。
職場のウェルビーイングは、以下のような要素から成り立ちます。
- 身体的健康(睡眠・運動・生活習慣)
- 精神的健康(ストレス対処・感情の安定)
- 社会的健康(人間関係・つながり)
ラインケアの強化
管理職によるラインケアは、職場メンタルヘルスの要とされています。
しかし実際には、
-
兆候に気づけない
-
声をかけるのが難しい
-
不調を訴えられても対応方法がわからない
といった課題が多く、十分に機能していないケースもあります。
そのため、最近の研修ではケーススタディやロールプレイを通じ、管理職が具体的なスキルを学べるようにする取り組みが増えています。
セルフケア教育の拡充
ストレスマネジメントなど、従業員一人ひとりが自分のメンタルを守る力を身につけることも欠かせません。
また、特に注目されているのが、認知行動療法(CBT)をベースにしたセルフケア研修です。
自分の思考や感情のパターンに気づき、前向きに修正していくスキルは、日常のストレス対処だけでなく、長期的なレジリエンス強化につながります。
心理的安全性の向上
Googleの研究でも注目された心理的安全性は、職場メンタルヘルスの重要テーマです。心理的安全性がもたらすメリットには以下があげられます。
-
一人ひとりの個性が活かせる
-
エンゲージメントの向上
-
人材の定着率向上
こうした文化が根づくことで、メンタル不調の早期発見や予防につながります。研修の場では傾聴やフィードバックの実践練習が効果的です。
企業ができる効果的な取り組み
メンタルヘルス教育の体系化
企業が従業員の心身の健康を守るには、メンタルヘルス教育の体系化が不可欠です。新入社員向けの基礎知識から管理職向けのラインケア、セルフケアの実践まで、段階的かつ継続的に学べる仕組みを整えることで、早期発見・予防の意識が職場全体に浸透します。
相談窓口の整備
従業員が安心して相談できる窓口の整備は、職場のメンタルヘルス対策において重要です。社内の相談窓口に加え、外部専門家との連携を設けることで、匿名性や専門性の高い支援を提供できます。相談しやすい環境が整うことで、問題の早期発見や適切な対応が可能となり、長期休職や離職リスクの低減にもつながります。加えて、管理職への周知や利用促進、相談内容に応じたフォロー体制を確立することが、組織全体の心理的安全性向上にも寄与します。
職場環境の改善
職場環境の改善は、従業員のメンタルヘルスを守るうえで欠かせません。業務量の適正化や柔軟な勤務制度の導入、ハラスメント防止や心理的安全性の確保など、働きやすい環境づくりが求められます。また、職場のコミュニケーション機会を増やし、孤立感やストレスの早期発見につなげることも重要です。
研修を導入するメリット
メンタルヘルス研修を導入するメリットは、従業員の健康維持だけにとどまりません。正しい知識や対処法を身につけることで、不調の早期発見や予防につながり、休職・離職といったリスクを減らすことができます。また、従業員が知っているだけでなく実際に行動するきっかけをつくれる点も重要です。行動変容を促すことで、互いに支え合う風土が生まれ、安心して働ける職場づくりに直結します。
● 社員が自分のストレスに気づき、早めに対処できる
● 組織全体の心理的安全性が高まる
● 結果として、生産性向上・離職防止につながる
単発の研修だけでなく、フォローアップを含めた継続的な教育が効果的です。
実際、研修や教育は以下の点で効果的です。
-
認知の向上:従業員がストレスの兆候や心理的リスクを理解できる。
-
行動変容の促進:適切な対応方法やコミュニケーションスキルを学ぶことで、現場での実践が可能になる。
-
組織文化の改善:管理職やチーム全体が心理的安全性や健康配慮を意識するようになり、職場環境全体が整う。
このように、研修は制度の運用を支える行動の力を高める手段として重要視されているのです。
まとめ
職場のメンタルヘルスは、もはや一部の企業だけの課題ではなく、あらゆる組織にとって経営上の必須テーマとなっています。
効果的な取り組みである「ウェルビーイング」「ラインケア」「セルフケア教育」「心理的安全性の向上」を踏まえた取り組みを行うことで、従業員の健康を守りながら、組織の成長を支えることが可能です。
弊社では、企業の状況に合わせた職場メンタルヘルス研修をご提供しています。実践的なワークを通じて、管理職・従業員双方が「気づき」「支え合い」「自分を守る力」を学べるプログラムです。
ご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。