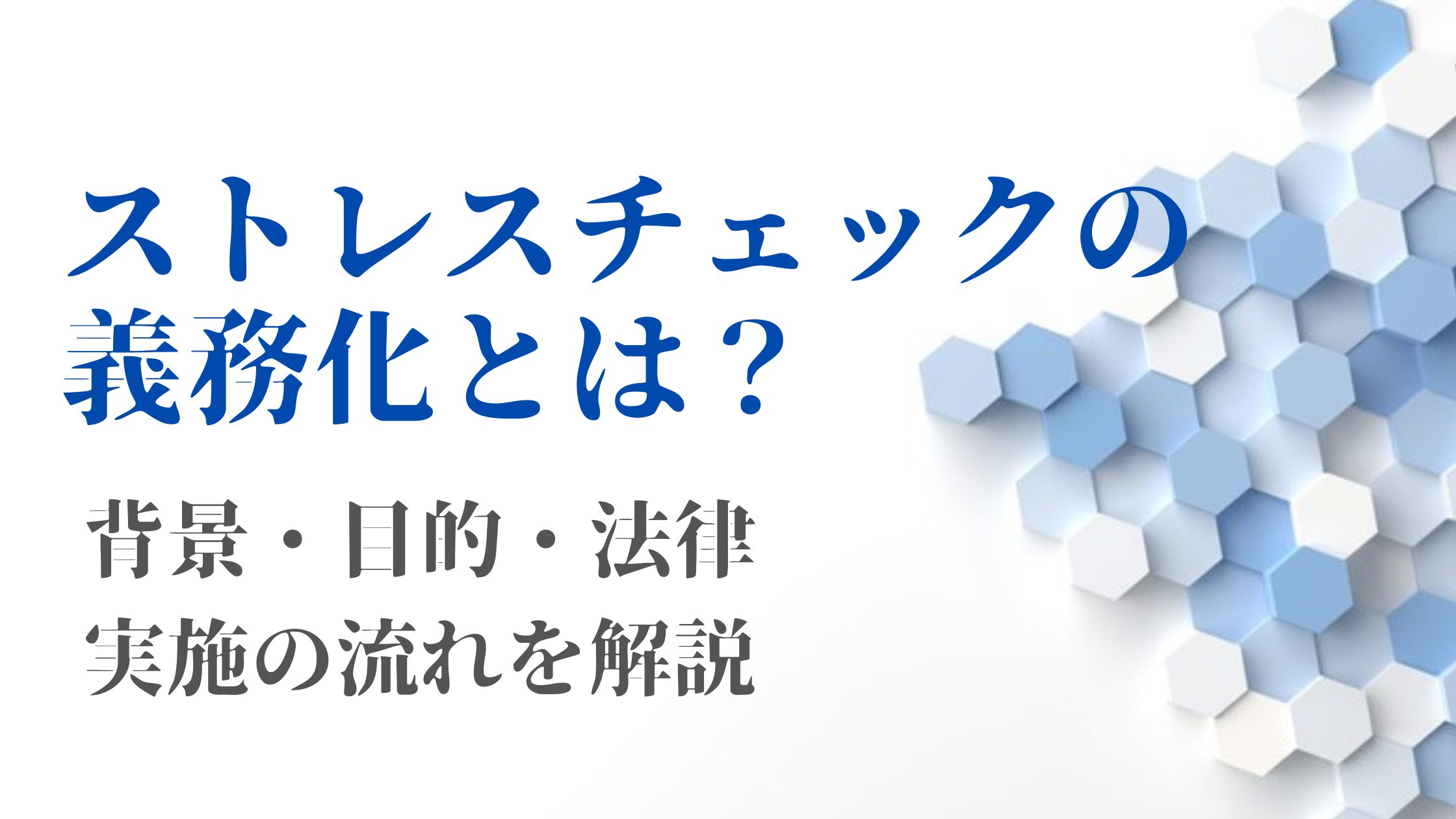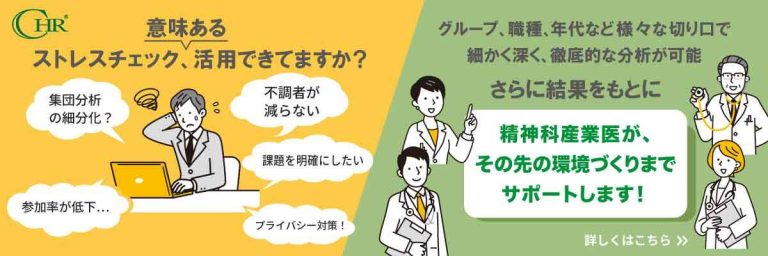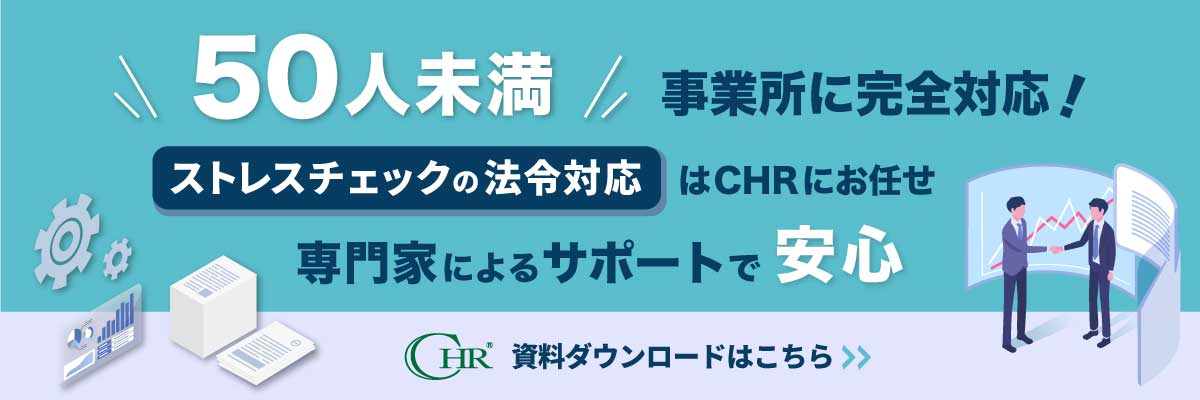2015年12月に従業員50名以上の事業場に実施が義務付けられたストレスチェック。
ストレスチェックが制度化され今年で10年が経過しましたが、改めてストレスチェック制度の義務化について解説していきます。
ストレスチェックの義務化とは?
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的として、2015年12月から労働安全衛生法の改正により導入されました。
この制度では、常時50人以上の労働者を雇用する事業場に対して、年に1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。
一方、50人未満の事業場については、当初は努力義務とされていましたが、2024年10月に厚生労働省はこの義務化の対象を全事業場に拡大する方針を示しました。
ストレスチェックの主な目的は、労働者自身が自分のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調の一次予防を図ることです。具体的には、労働者が質問票に回答し、その結果をもとに高ストレス者と判定された場合、本人の申し出により医師による面接指導が行われます。また、集団ごとの結果を分析することで、職場環境の改善にも役立てられます。
ストレスチェック義務化の背景
ストレスチェックが制度化され義務化された背景は、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新するなど、仕事での強いストレスを感じる労働者の割合が高い現状があります。
精神障害の労災認定件数の増加
2019年度の厚生労働省の調査によれば、ストレスなどによる精神障害の労災請求件数は2,060件となり、前年から240件増加し、調査開始以来、過去最高となっています。
精神障害が発症した理由としては「嫌がらせ、いじめ」が最も多く、「仕事内容や量の変化を生じさせる出来事」、「悲惨な事故や災害の体験や目撃」「2週間以上の連続勤務」などが挙げられています。
(参照:「令和元年度『過労死等の労災補償状況』についての報道発表」厚生労働省)
約6割が仕事での強いストレスを感じている
厚生労働省の調査によれば、仕事や職業生活において「強いストレスと感じる事柄がある」労働者の割合は58%であり、高い現状を示しています。
ストレスと感じる内容としては「仕事の質・量」が最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」、「パワハラ・セクハラを含む対人関係」となっています。
仕事や職業生活におけるストレスは近年増加傾向が見られ、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっていました。
(参照:「平成30年 労働安全衛生調査」厚生労働省)
以上のように職場におけるメンタルヘルス不調が増加傾向にあり、精神障害による労災認定件数が増加していることがあります。特に、パワーハラスメントや業務内容の大きな変化が主な原因とされています。
このような状況を受け、労働者自身がストレス状況に気づき、早期に対処することや、職場環境の改善を促進するため、ストレスチェック制度が導入されました。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェック制度の目的は、労働者が自分のストレス状態を把握し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことです。
職場でのストレスは日常的に蓄積されやすく、放置すると身体的・精神的な健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、労働者が定期的にストレスチェックを受けることで、自身のストレスレベルを認識し、早期に対策を講じることができます。
具体的には、労働者が質問票に回答し、その結果をもとに自身のストレスの度合いを客観的に評価します。特に、高ストレスと判定された場合は、本人の希望に応じて医師の面談を受けることができ、必要に応じて職場環境の改善や業務負担の調整が行われます。これにより、労働者が健康を維持し、ストレスによる生産性の低下や長期休職を防ぐことが可能となります。
さらに、ストレスチェックの結果を組織単位で分析することで、職場全体のストレス要因を明らかにし、環境改善に役立てることができます。例えば、業務量の偏りやハラスメントの有無などを見直すことで、労働環境の健全化を図ることが可能になります。これにより、労働者の健康を維持するだけでなく、職場の生産性向上や離職率の低下といった効果も期待されています。また、職場でのストレス対策が強化されることで、労働者がより安心して業務に取り組める環境が整います。
ストレスは自覚しにくく、特に強いストレスを抱えている人ほど、自分の状態に気づきにくい傾向があります。そのため、ストレスチェックを通じて自分の状況を把握することが重要です。また、必要に応じて医師の面談を受けることで、職場での配置転換や業務負担の軽減といった対策を講じることが可能となり、精神的な負担を和らげることにつながります。ストレスへの適切な対応を行うことで、個人の健康だけでなく、企業全体の働きやすさを向上させることにもつながるのです。
ストレスチェック制度の実施義務の要件は?
ストレスチェックが義務化となるのは、常時50人以上の労働者を雇用する事業場であり、年に1回以上の実施が法律で定められています。ただし、50人未満の事業場については当初努力義務とされていましたが、2024年10月から義務化の対象が拡大される予定です。
労働安全衛生法
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に適用されます。この「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や派遣先で働く派遣労働者も含まれます。具体的には、期間の定めのない労働契約、または契約期間が1年以上の労働契約で雇用されている者、さらに週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者が対象となります。したがって、これらの条件を満たす労働者が50人以上いる事業場は、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
(引用:『ストレスチェックマニュアル』厚生労働省)
現在、ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を雇用している事業場に限られています。一方、50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。
また、「ストレスチェック助成金」などの国の支援制度も用意されており、これらを活用することで、より働きやすい職場環境の整備が可能です。ぜひ助成金を活用し、職場のメンタルヘルス対策に取り組むことをおすすめします。
ストレスチェック助成金の詳細については、こちらの厚生労働省のページをご確認ください。
ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために実施される制度であり、職場のストレス要因を把握し、適切な対策を講じることを目的としています。以下の手順に沿って実施することで、効果的な運用が可能となります。
事前準備
ストレスチェックを実施する前に、企業としての方針を明確にし、衛生委員会などで具体的な実施方法について協議を行います。
協議では、実施者の選定、実施時期、使用する質問票の種類、高ストレス者の選定基準、面接指導の申出先、担当医師の選定、集団分析の方法、結果の保存管理などを決定します。これらの内容をもとに社内規程を整備し、全従業員に周知することが重要です。
実施体制の構築
ストレスチェックを適切に実施するために、医師や保健師、または研修を受けた看護師や精神保健福祉士などの専門的な知識を持つ人を実施者として選任します。
また、実施事務に関する担当者を配置し、質問票の配布や回収、データ入力、結果通知などの業務を担う体制を整えます。必要に応じて、外部の専門機関に委託することも可能です。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックでは、労働者に質問票を配布し、記入してもらいます。質問票には、「ストレスの原因」「ストレスによる心身の自覚症状」「職場でのサポート体制」に関する項目が含まれています。
標準的な「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」に加えて、「80項目版」も使用することができます。80項目版では、57項目に加えて「働きがい(ワークエンゲージメント)」「ハラスメント」「上司のマネジメント」「人事評価」などの項目が追加されており、より詳細な分析が可能になります。記入後、実施者が質問票を回収・評価し、結果を労働者本人に通知します。
事後対応
ストレスチェック実施後の事後対応は、労働者のメンタルヘルスを守りストレスチェックを効果的に行うために重要です。ストレスチェックの結果に応じた適切な対応を行うことで、労働者の健康維持や職場環境の改善につながります。
ストレス状況の結果の通知
ストレスチェックの結果は、本人に直接通知され、労働者が自身のストレス状況を認識できるようにします。結果の通知方法は、プライバシーに配慮した形で行う必要があります。特に、結果を事業者が直接知ることは原則としてなく、本人の同意がある場合のみ情報が共有されます。
医師の面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者に対しては、企業は本人の同意を確認の上、医師の面接指導を実施します。面接指導では、ストレスの要因、職場環境、業務負担、生活習慣などについて医師が詳しくヒアリングを行い、労働者の健康状態を確認します。必要に応じて、労働時間の短縮、業務内容の変更、休職などの対応策が検討されることもあります。
意見聴取
面接指導を実施した後は、事業者は1ヶ月以内に医師の意見を聞き、就業に関する対応について検討します。医師の助言に基づき、休職や配置転換、労働時間の短縮など、職場環境の改善が必要な場合は、適切な対応を検討し、実施します。
集団分析と職場環境改善
ストレスチェックの結果は、個人だけでなく、事業場全体の職場環境改善にも活用されます。
集団分析を行うことで、部署ごとのストレス要因を特定し、組織全体の問題点を明らかにすることができます。例えば、特定の部署で高ストレス者が多い場合、その部署の業務負担や人間関係に課題がある可能性が高いため、具体的な改善策を検討することが求められます。
職場環境改善のためには、以下のような施策が考えられます。
- 業務量の適正化
- ハラスメント防止対策の強化
- 休憩時間の確保と労働時間の見直し
- メンタルヘルス研修の実施
- 上司と部下のコミュニケーション強化
これらの施策を実施することで、労働者の健康維持と職場の生産性向上が期待されます。
結果の保存と報告
ストレスチェックの結果は、個人情報として適切に管理し、5年間の保存が義務付けられています。データの管理には十分な配慮が必要であり、関係者以外のアクセスを制限し、適切なセキュリティ対策を講じることが求められます。
また、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、1年以内ごとに1回、ストレスチェックの実施状況を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。報告書には、労働者数や面接指導を受けた労働者数などの情報を正確に記載し、記入漏れがないように注意します。報告書の様式は厚生労働省が定めており、適切なフォーマットを使用することが必要です。
ストレスチェックの適切な実施と事後対応を行うことで、労働者のメンタルヘルスを守り、職場環境の改善につなげることができます。特に、80項目版の活用や、面接指導・意見聴取・集団分析・職場環境改善の徹底により、ストレスチェックの効果を最大化することが可能です。また、結果の適切な保存と労基署への報告も忘れずに行い、制度の適正な運用を継続することが重要です。
おわりに
ストレスチェック制度義務化の背景から実施の流れまでを解説してきました。
ストレスチェック制度の目的は、従業員のストレス状況をチェックすることではなく、職場環境改善にあります。
現時点においては集団分析の実施や職場環境改善は義務付けられていません。しかし職場環境改善により従業員がいきいきと働くことができ生産性の向上にも繋がります。このことは企業にとっても大きなメリットといえます。
毎年行われるストレスチェック。実施だけで終わらせずより働きやすい職場づくりに生かすことが大切です。