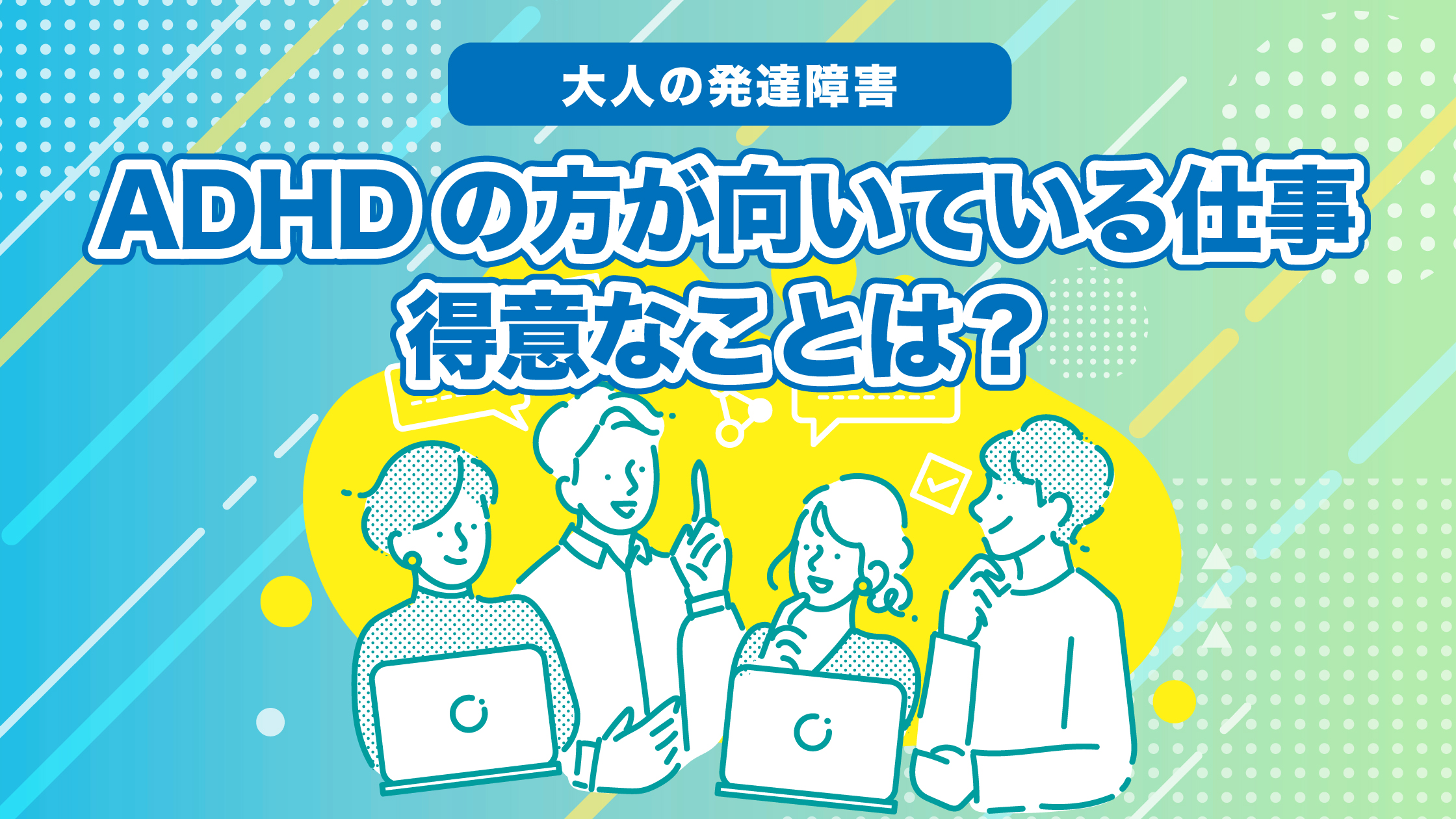近年、職場における多様な人材の活躍を支える「多様性(ダイバーシティ)」や「包摂(インクルージョン)」の考え方が重視されるようになってきました。
これは、性別や年齢、国籍だけでなく、障害や特性の有無にかかわらず、一人ひとりが自分の力を発揮できる職場づくりを目指す動きです。
こうした流れの中で、ADHD(注意欠如・多動症)をはじめとする発達障害のある方への理解や、職場での合理的配慮の必要性がますます注目されています。
ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」といった特性で知られていますが、その一方で、豊かな発想力や行動力、特定の分野での高い集中力など、本人の強みとなる特性も持ち合わせています。職場環境や業務の内容によっては、こうした強みが大きな力を発揮することも少なくありません。
今回は、ADHDの方が持つ強みや向いている仕事、苦手とされやすい業務の特徴、そして企業が取り組むべき合理的配慮の具体例について解説します。

以下、一般的な特徴としての記載もありますが、ADHDの方も当然一人ひとりに個性がありすべてが一律に該当するものではありません。特性のあり・なしや、その程度にかかわらず、安心してそれぞれの力を発揮できる職場づくりを進めるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。
ADHD(注意欠如・多動症)とは?大人のADHDの特徴
ADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症)は、発達障害のひとつであり、脳の働き方の特性として「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの側面が特徴です。子どもの発達段階で診断されることが多いものの、近年では成人後に診断を受けるケースも増えています。
その背景には、子どもの頃には「活発な性格」「少し不器用なだけ」と捉えられていた特性が、大人になり社会的責任や複雑なタスクが増えることで顕在化し、生活や仕事の中で困りごととして表れることがあります。
大人のADHDの主な特性
大人のADHDの特性は、次のような形で職場や日常生活に表れることがあります。
不注意の傾向
ADHDの方に見られる「不注意」の特性は、決して怠慢や集中力の欠如ではなく、注意を持続させたり切り替えたりする脳の働き方の特性によるものです。職場では、細かな事務作業や長時間の集中を必要とする業務において、この特性が課題として現れやすいことがあります。
- 会議や資料作成、事務作業中に集中力が続かず、ケアレスミスをする
- 約束や締め切りを忘れてしまう
- 書類や物品の管理が苦手で、探し物が多くなる
- 優先順位づけや段取りを立てることに苦手意識を持つ
多動性の傾向
「多動性」は、身体を動かしたい衝動や、頭の中に次々と新しいことが浮かんで落ち着かない状態として表れることがあります。大人のADHDの方でもこの特性が残る場合、職場での立ち居振る舞いや会議中の様子などに特徴が表れることがありますが、必ずしも「じっとしていられない」というだけではなく、内面的な落ち着かなさとして感じている方もいます。
- 落ち着いて座っていられず、身体を動かしたくなる
- 仕事中に気が散りやすく、他のことに意識が向いてしまう
- 思いついたことをすぐに話したくなる、余計な発言が増える
衝動性の傾向
「多動性」は、身体を動かしたい衝動や、頭の中に次々と新しいことが浮かんで落ち着かない状態として表れることがあります。大人のADHDの方でもこの特性が残る場合、職場での立ち居振る舞いや会議中の様子などに特徴が表れることがありますが、必ずしも「じっとしていられない」というだけではなく、内面的な落ち着かなさとして感じている方もいます。
- よく考えずにすぐ行動に移してしまう
- 発言や行動が先走り、後悔することがある
- 衝動的な買い物や計画外の行動をとってしまう
これらの特性は、職場での評価や人間関係、仕事の進め方に影響を与えることがあります。ただし、これは「本人の努力不足」や「性格の問題」ではなく、脳の特性によるものだという理解が重要です。
ADHDの特性によって生じやすい職場での困りごと
大人のADHDの方は、職場において以下のような困りごとを抱えることがあります。
- 長時間にわたる会議やデスクワークで集中力を維持できない
- 同時に複数の業務をこなす「マルチタスク」が苦手
- 突発的な予定変更や指示変更に混乱しやすい
- 業務の優先順位をつけることや進捗管理に苦手意識を持つ
- 書類やメールの整理、管理が追いつかない
こうした困難は、ADHDの特性と職場の環境や仕事のやり方がマッチしないことで顕在化することが多いです。特性に合わない業務や環境では、本人が過剰な努力を続け疲弊したり、職場での評価が下がって自己肯定感の低下につながることもあります。
ADHDの方が持つ強み・得意なこと
ADHDというと、「ミスが多い」「落ち着きがない」といった困りごとばかりが注目されがちです。しかし、その特性は見方を変えると、職場で価値ある力として発揮されることも少なくありません。ここでは、ADHDの方が持つ主な強みや得意なことを詳しく見ていきましょう。
発想力・創造性が豊か
ADHDの方は、従来の枠にとらわれない柔軟でユニークな発想をすることが得意です。頭の中でさまざまなアイデアが絶え間なく生まれるため、既存のやり方に新しい視点を加えたり、革新的な提案をしたりする場面でその力が発揮されます。
たとえば、企画職やデザイン、広告制作、商品開発など、クリエイティブな業務ではADHDの方の発想力が大きな武器となります。周囲が思いつかない斬新なアイデアを短時間で複数出せることもあり、プロジェクトに新たな価値を生む存在となることができます。
行動力がある
ADHDの方は、思い立ったらすぐに行動に移すスピード感を持っています。慎重に考えるよりもまずやってみる、という姿勢は、変化の激しいビジネス環境や即応性が求められる現場で強みになります。
たとえば、スタートアップ企業や新規事業の立ち上げ、現場の改善活動など、「スピード」「行動力」が求められる仕事では高い評価を得やすいです。この特性により、停滞しがちな組織に新しい風を吹き込む役割を果たすこともあります。
ハイパーフォーカス(過集中)
ADHDの方には、特定の興味・関心のあることに強い集中力を発揮する「ハイパーフォーカス(過集中)」の特性があります。この状態では、周囲の音や時間の経過も忘れるほどの没頭が可能です。
この特性は、研究職や開発職、IT関連のコーディング作業、クリエイティブ制作など、専門性が高く深い集中が求められる仕事で力を発揮します。ハイパーフォーカスの対象を業務の中に見つけることで、大きな成果につながる可能性があります。
社交的で人と関わるのが好き
ADHDの方の中には、人との関わりを楽しみ、周囲を明るくする社交的な方も少なくありません。多動性や衝動性が、エネルギッシュで親しみやすいキャラクターとして周囲に好印象を与えることもあります。
この特性は、営業職や接客業、チームリーダー的なポジションでの活躍に結びつきます。社内外の多様な人とコミュニケーションを取る場面で、その明るさや親しみやすさが信頼関係づくりに役立ちます。
ADHDの方に向いている仕事・業務例
ADHDの方が持つ強みを活かせる仕事は、職場環境や業務内容の特徴に大きく左右されます。特性をうまく活かせる仕事には、次のような特徴があります。
クリエイティブ職(デザイン、ライティング、広告制作など)
ADHDの方の発想力や創造性が存分に発揮できるのがクリエイティブ系の職種です。企画立案、商品開発、広告制作、Webデザイン、コピーライティングなど、アイデアや独自の視点が求められる業務では高い評価を受けやすくなります。
ルーティンワークが少なく、新しいことに挑戦できる職場環境がADHDの方の力を引き出します。
営業職・接客業
ADHDの方の社交性や行動力は、営業や接客の場で活かされることが多いです。人と接する機会が多く、成果が自分の努力や工夫に直結するような仕事は、大きなモチベーションにつながります。
特に、自らの裁量で動ける営業職や、自分のペースで顧客対応ができる接客業はストレスが少なく、活躍しやすい傾向があります。
技術職・専門職(ITエンジニア、プログラマー、研究職など)
特定の分野に集中できる特性は、ITや研究開発の分野で強みとなります。プログラミング、システム設計、データ分析、研究などの業務では、高度な集中力が求められ、ADHDの方が能力を発揮しやすい環境です。
興味のあるテーマに没頭できる仕事であれば、大きな成果をあげることも可能です。
配送・ドライバー、作業現場での業務
長時間座り続ける必要がない、適度に体を動かせる仕事も向いています。例えば、配送ドライバー、倉庫作業、工事現場での仕事などは、体を使って働くことで集中力を維持しやすく、落ち着いて業務に取り組めることがあります。
一方で、安全管理が重要な職場では、特性に合わせたサポートが求められる場合もあります。
起業・フリーランス
自分で仕事の進め方やペースを決めたいというADHDの方にとって、起業やフリーランスという働き方は適していることがあります。新しいことに挑戦し、裁量権を持って柔軟に働くスタイルは、特性をプラスに活かしやすい環境です。
ただし、自己管理が課題になることもあるため、外部のサポートやアシスタントを活用するなどの工夫が必要です。
ADHDの方が苦手とされやすい仕事・業務例
ADHDの特性が負担になりやすい仕事には、次のような特徴が見られます。ただし、これらの仕事が絶対に向かないというわけではなく、適切な配慮や支援があれば力を発揮できる場合もあります。
長時間のデスクワークや細かい事務作業
単調で同じ姿勢を続ける必要がある業務、細かなミスが許されない事務作業などは、ADHDの方にとって集中力の維持が難しい場面が多く、ストレスや疲労につながりやすいです。
マルチタスクを強く求められる業務
複数の業務を同時進行でこなし、優先順位を瞬時に判断しながら進めるような業務は、混乱を招きやすくなります。急な予定変更や割り込み業務が多い職場では、過剰なストレスを感じやすい傾向があります。
厳格なルールや手順が求められる業務
ルール通りに正確さが求められる仕事では、衝動性や注意の散漫さが課題となりやすいです。工程の正確性が重視される製造ラインや、高い正確性が求められる経理業務などでは、特性との相性を考慮した配慮が必要になります。
長期間の計画性や事務処理能力が問われる業務
先々までの長期的な計画を立て、コツコツと管理・調整を続ける業務では、負担感を抱きやすくなります。たとえばプロジェクトの進行管理や、複雑な事務手続きの担当では、外部サポートやチームでの役割分担が効果的です。
ADHDの方が安定して働くために企業が行うべき合理的配慮
ADHDの方が職場で力を発揮し、安定して働き続けるためには、企業による「合理的配慮」が重要です。合理的配慮とは、本人の特性に応じて業務や職場環境を調整し、不必要な困難を取り除くことで、安心して能力を発揮できるようにする取り組みです。以下は、厚生労働省の指針および職場での実践事例(合理的配慮指針事例集【第五版】厚生労働省)をもとにした具体的な配慮の例です。
作業手順やスケジュールの可視化
ADHDの方は、業務手順や優先順位が不明確な状態では混乱や不安を感じやすい傾向があります。
具体策
- 作業手順書を図や写真付きで用意し、持ち歩ける形にする
- ホワイトボードやタスク管理ツールで進捗を見える化
- チェックリストやタイマーを活用し、抜け漏れや時間管理を補助
静かな作業環境の確保
周囲の音や視覚的刺激が集中の妨げになることがあるため、環境の整備が効果的です。
具体策
- パーテーションや個別スペースの設置
- 必要に応じてイヤホンやノイズキャンセリング機器の利用を許可
- 机や備品の配置を整理し、視覚情報の過剰さを軽減
定期的な面談・フィードバック
定期的に本人の状況を確認し、困りごとを共有することで、課題の早期発見や改善につながります。
具体策
- メンターやジョブコーチ、管理職が面談を担当し、日常的に声をかける
- 進捗や困りごとの振り返りを定期化し、安心感を持てる環境にする
柔軟な勤務形態の導入
ADHDの方の特性や体調に合わせ、柔軟な働き方を認めることで負担を軽減できます。
具体策
- フレックスタイム制やリモートワークの活用
- 通院や体調管理のための短時間勤務や休暇制度
- 休憩の取り方を本人のペースに合わせる(短時間の小休憩の許可など)
マルチタスクを避け、業務の分担を工夫
複数の業務を同時に進める状況では、混乱やミスが生じやすくなります。
具体策
- 役割を明確化し、1つの業務に集中できる環境を整える
- 突発業務の頻度を減らし、計画的に業務を割り振る
- 優先順位の高い業務から順に指示し、混乱を防ぐ
社内理解と協力体制の構築
ADHDの方への配慮は、チーム全体の理解と協力があってこそ実現します。
具体策
- 特性や支援の必要性を、本人の同意を得た上でチームに共有
- 管理職・同僚向けに発達障害の理解促進研修を実施
- 支援内容をチーム内で共有し、誰もがサポートに関わる体制をつくる
おわりに
ADHDの方は、特性を正しく理解し、その強みを活かせる環境でこそ、真の力を発揮できます。企業が合理的配慮を適切に行うことで、ADHDの方が安定して働けるだけでなく、組織全体の生産性や多様性も高まります。大切なのは「困りごと」に目を向けるだけでなく、「強み」に着目し、個々の力を引き出す職場環境を作ることです。
これからの時代、多様な人材が活躍する職場づくりは企業の持続的成長に直結します。ADHDをはじめ、さまざまな特性を持つ方々が能力を発揮できるよう、企業の積極的な取り組みが求められています。