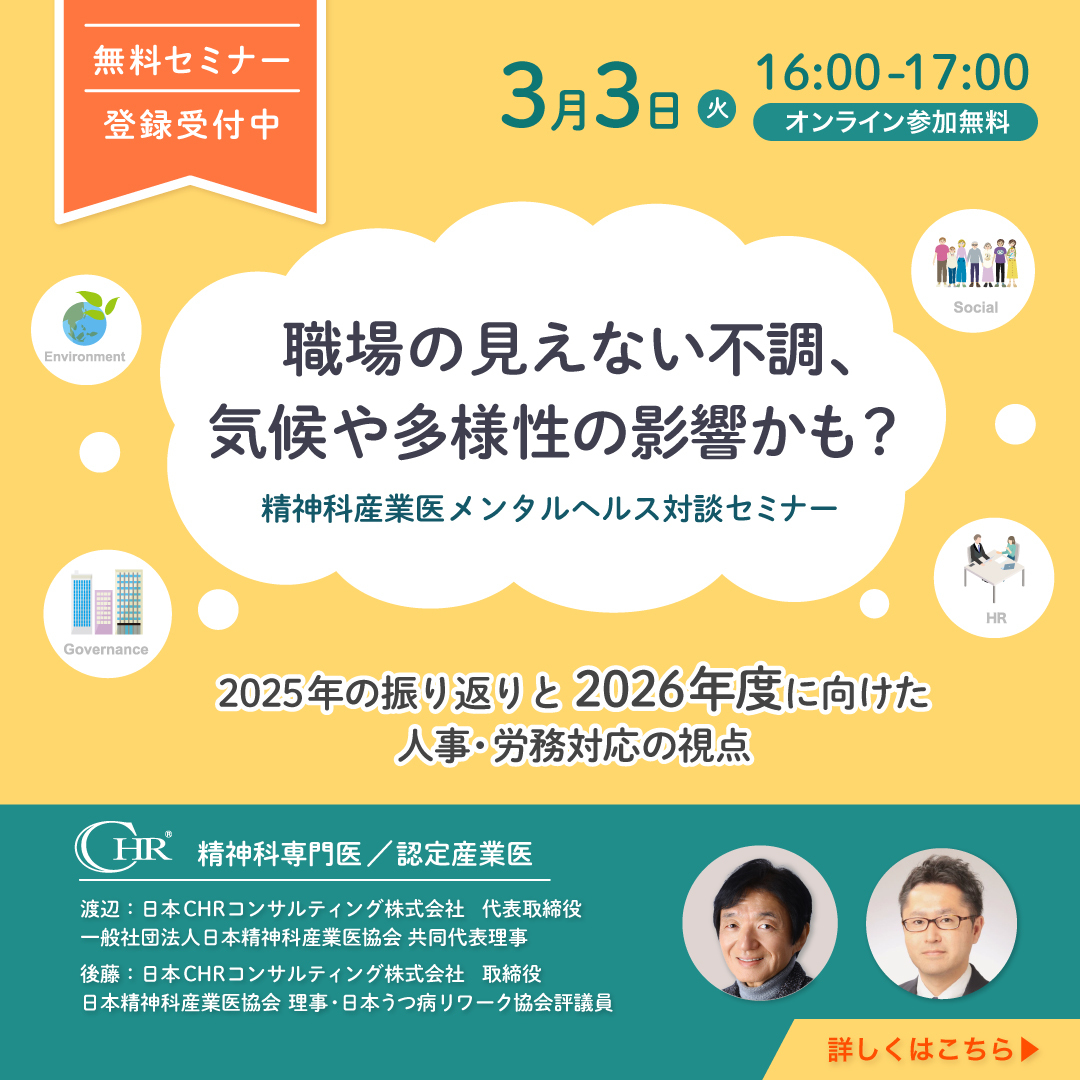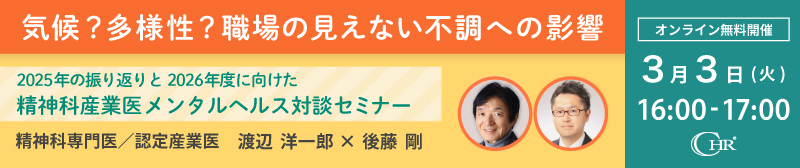ハラスメントハラスメントとは、業務上正当な指導や通常のコミュニケーションに対して「それはハラスメントだ」と不当に主張されることで生じる新たな摩擦のことを指します。
現代の職場では、ハラスメント防止意識が高まる一方で、必要な対応や改善指導までが「パワハラ」「セクハラ」と誤解されるケースが見られます。その結果、上司が指導をためらったり、組織全体が萎縮したりするという副作用が起きています。
今回は、ハラスメントハラスメントの定義から具体例、背景、そして個人と企業それぞれが取り組むべき対策を解説します。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは?
ハラスメント防止への意識が高まる一方で、職場では「これはハラスメントではないか」と過剰に反応してしまうケースも増えています。
業務上正当な注意や配慮までもが「パワハラ」「セクハラ」などと主張される現象が、近年「ハラスメントハラスメント(ハラハラ)」と呼ばれるようになりました。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)の定義
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは、本来であれば業務上必要で正当な行為に対して、不当に「ハラスメントだ」とレッテルを貼ることを指します。
例えば、上司が部下に提出期限を守るよう注意するのは、業務の進行において当然の行為です。
しかし、これをパワハラだと決めつけてしまうと、正しい指導まで否定されてしまいます。
この現象が厄介なのは、「不快に感じた=ハラスメント」という誤解を生む点です。
不快感は主観的なものですが、業務上の必要性まで否定してしまうと、職場でのコミュニケーションや指導が成り立たなくなります。
・上司が部下を育てるための正しい指導ができなくなる
・部下が本当に必要な改善点に気づけなくなる
・職場全体が「何も言えない雰囲気」に包まれる
つまり、ハラスメントハラスメントは単なる誤解ではなく、職場の信頼関係を壊し、組織の成長を妨げる深刻なリスクを伴うのです。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)と誤解されやすい具体例
実際の職場でのシーンをイメージしやすいように、具体的なケースを見てみましょう。
パワハラに見える指導
部下が報告の締め切りを守らなかったため、上司が「報告の締め切りは必ず守ってほしい」と注意した場面。内容は業務上当然の指導であり、声を荒げたわけでもありません。
ところが部下は「強く責められた」「怒鳴られた」と受け取り、人事に訴える事態に発展しました。 業務上必要なフィードバックでも、伝え方やタイミング次第で「攻撃された」と誤解されやすいのが実情です。
特に、部下がストレスを抱えている時期や、人間関係に不安がある状況では、指導の言葉が過度にネガティブに受け取られる可能性があります。
このような場合には、指導の理由や背景を具体的に説明し、相手に理解を促すことが大切です。業務の効率を高めるために、ミスを減らすためにという目的を明示することで、不必要な誤解を減らせます。冷静なトーンで伝え、相手の意見を聞く余地を残すことも、パワハラと誤解されないための工夫になります。
マリッジハラスメント(マリハラ)に見える雑談
職場の雑談の中で、上司が「週末は家族と出かけるんだ」と話した場面。
本人にとっては単なる日常会話であり、悪意や押しつけの意図はありません。しかし未婚の部下はこれを結婚や家庭を持つことを当然とする価値観の押しつけと感じ、マリッジハラスメント(マリハラ)ではないかと受け止めました。 ライフスタイルや価値観に関わる話題は、相手の立場によって敏感に受け取られることがあります。たとえ世間話のつもりでも、無神経だと誤解されるリスクがあるのです。
こうした雑談を避けるのではなく、「休日はゆっくり休めそうですか?」など、相手が話しやすい範囲に配慮した問いかけにすると、自然に会話を広げられます。また、相手の反応を見て深追いせず、軽い話題にとどめることで、不要な誤解を減らせます。
マタハラと捉えられる可能性がある配慮
妊娠した社員の体調を考えて、夜間シフトから外した場面。本来は母子の健康を守るための配慮ですが、本人によっては「昇進や経験の機会を奪われた」と受け止められることがあります。
意図は善意でも、伝え方や背景次第でマタハラと主張される可能性があります。
こうしたケースでは、事前に面談などで本人と十分に話し合い、合意形成をしておくことが重要です。配慮の理由や意図を明確に伝え、本人の希望も尊重することで誤解を防げます。
モラハラに見える注意
会議中に同僚の資料の誤りを指摘し、「次回から気をつけようね」と軽く声をかけた場面。改善を促す意図だったのに、相手から「みんなの前で恥をかかされた」と感じられてしまう場合があります。
公の場での発言は特に、モラハラだと受け止められやすい可能性があります。
このように、同じ行為でも「伝え方」「タイミング」「話し合いの有無」によって、ハラスメントと受け止められるかどうかは大きく変わります。意図を正しく伝え、相手の理解を得る工夫が欠かせません。
厚生労働省によるパワハラの定義
厚生労働省によれば、ハラスメントに該当するかどうかの判断基準として、業務上必要かつ適正な範囲であるかどうかが明示されています。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
引用:ハラスメントの定義(厚生労働省)
つまり、 業務の円滑な遂行に必要な行為である 指導や注意の方法が社会的に見て適正である この2点を満たす場合は、ハラスメントには当たりません。
逆に言えば、社員が「嫌だった」「不快だった」と感じただけで自動的にハラスメントと認定されるわけではない、ということです。厚労省の見解は、正当な指導や注意が不当にハラスメントとされないようにするための重要な指針になっています。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)が起こる背景
なぜ正当な指導や配慮がハラスメントと受け取られてしまうのでしょうか。その裏には、職場特有の雰囲気や人間関係、そして社会全体の変化が大きく関係しています。
ここでは、ハラスメントハラスメントが生まれやすい背景を整理し、なぜこうした誤解や摩擦が生じるのかをわかりやすく解説します。
職場環境の影響
「何を言ってもパワハラになるのでは」と上司が感じてしまうような雰囲気の職場では、ハラスメントハラスメントが生じやすくなります。
特に、上司と部下の間に信頼関係が築かれていない場合、指導の一言ひとことが攻撃として受け止められてしまうのです。
例えば、普段からコミュニケーションが少なく、業務連絡が必要最低限しか行われていない職場では、「注意=否定された」「叱られた=人格を否定された」と感じやすくなります。
逆に、日常的に雑談や相談ができる関係性があると、同じ言葉でも自分の成長を考えてくれていると受け止められやすくなります。 つまり、職場に漂う空気感や人間関係の質が、ハラスメントハラスメントの発生リスクを大きく左右するのです。
個人のリテラシーの不足
もうひとつの背景は、従業員一人ひとりのハラスメントに関するリテラシー不足です。 ハラスメントには明確な定義や基準がありますが、それを正しく理解していないと自分が嫌だと感じた=ハラスメントと短絡的に結びつけてしまうことがあります。
たとえば、上司が業務改善のために指導したにもかかわらず、自分の気分を害されたという理由だけでパワハラだと訴えてしまうケースです。もちろん不快な感情も大切なシグナルですが、それとハラスメントとして成立するかどうかは別問題です。
こうした誤解は、会社全体に何も言えない空気を生み、結果的に組織の健全な成長を阻害してしまいます。 知識不足が、職場全体に過剰反応や摩擦を引き起こす火種になるといえるでしょう。
法律と社会的認識の変化
さらに大きな背景として、社会全体のハラスメントに対する意識変化があります。
2020年に施行されたパワハラ防止法をはじめ、企業に対してハラスメント対策を義務づける法制度が整備されました。これによりハラスメントは許されないという認識が社会に広まり、被害の声を上げやすい風土ができたこと自体は非常に前向きな変化です。
しかし一方で、「ちょっとでも不快ならハラスメントでは?」という過剰な意識も同時に広がっています。SNSやニュースでハラスメント問題が大きく取り上げられることで、従業員が過敏になりやすく、必要な指導や注意までが疑いの目で見られることも度々あるようです。
つまり、社会的認識が進んだこと自体は良いことですが、その反動としてハラスメントハラスメントという新しい課題が生まれているのです。
このように、ハラスメントハラスメントは、職場の空気・個人の知識不足・社会の変化という複数の要因が絡み合って起こる現象です。防止するためには、これらの背景を理解したうえで、組織と個人の双方が冷静な視点を持つことが欠かせません。
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)の対策
ハラスメントハラスメントは、個人の受け止め方や誤解、そして企業文化のあり方から生まれる現象です。 そのため、解決のためには個人の姿勢と企業の取り組みの両方が欠かせません。 ここでは、従業員一人ひとりができる対策と、組織として取り組むべき施策を分けて解説します。
個人でできる対策
従業員自身が正しい知識と冷静な対応力を持つことで、不要な摩擦を防ぐことができます。
正しい知識を身につける
まず大切なのは、ハラスメントの定義を正しく理解することです。厚生労働省の指針では、 「業務上必要かつ適正な範囲で行われる注意や指導はハラスメントにあたらない」 とされています。知識があいまいなままでは、必要な指導まで攻撃されたと感じてしまう恐れがあります。 正しい線引きを学ぶことで、過剰反応を避け、冷静に判断できるようになります。
相手の意図を確認する
不快に感じる言葉を受けたときに、すぐ「ハラスメントだ」と決めつけるのは危険です。 誤解が原因である場合も多くあります。たとえば、 「どういう意図でそのように言われましたか?」と落ち着いて尋ねるだけで、相手の意図を理解し、 無用な対立を避けられることがあります。確認の一歩が、相互理解につながります。
感情と事実を分けて考える
「嫌だった」「不快だった」という感情は自然なものです。 ただし、その感情と業務上必要かどうかという事実を混同してしまうと、冷静な判断が難しくなります。 感情は感情、事実は事実と切り分ける習慣を持つことで、 状況をこじらせず、正しい対応を取れるようになります。
企業による対策
組織としては、制度と風土の両面からアプローチすることが重要です。
教育研修の実施
従業員が「何が適正な指導で、どこからがハラスメントか」を共通認識として持つことは不可欠です。 座学だけでなく、実際の事例を使ったケーススタディ形式の研修を行うと、現場に即した判断力が養われます。 また、管理職だけでなく全社員が対象となる研修が効果的です。
相談窓口・第三者機関の設置
相談を公平に扱える仕組みを整えることも大切です。社内に相談窓口を設けるだけでなく、 外部の専門機関と連携することで、中立的な立場からの判断が可能になります。 これにより、不当な主張や誤解が生じた場合にも、冷静かつ公正に対応できます。
コミュニケーション文化の醸成
ハラスメントハラスメントを防ぐには、日常的なコミュニケーションの質を高めることが何より効果的です。 上司と部下が率直に意見交換できる関係性を築いていれば、 指導=攻撃 という誤解は起きにくくなります。 定期的な1on1やフィードバックの場を設け、安心して話せる職場文化を育てることが求められます。
おわりに
ハラスメントハラスメント(ハラハラ)は、まだ新しい言葉ですが、多くの職場で現実の課題となっています。 不快だから=ハラスメントという短絡的な発想を避け、意図と背景を丁寧に確認する姿勢が不可欠です。
個人は冷静なリテラシーを持ち、企業は制度と文化を整える。
その両輪が揃ってはじめて、健全で安心できる職場が実現します。