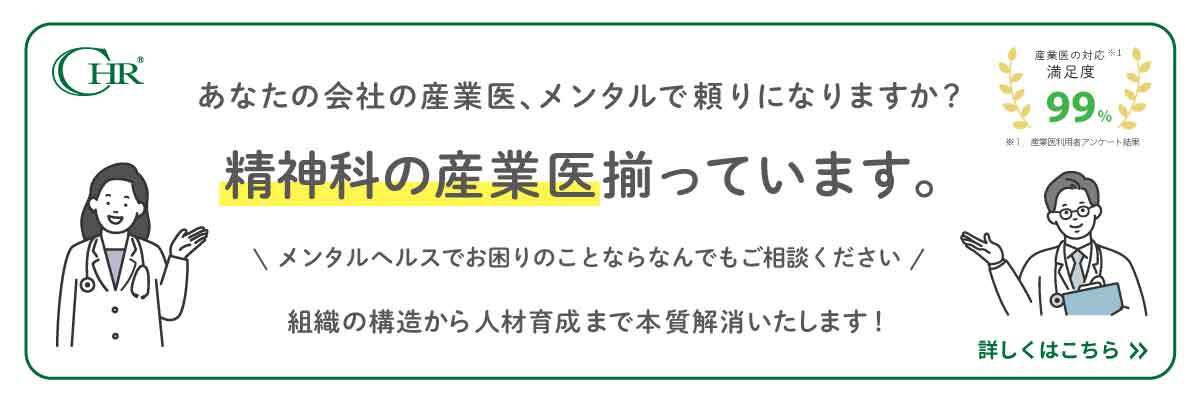「安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会は似たような名前だけど、実際どう違うの?」「設置しなかったら罰則はあるの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
企業においては、事業場の規模や業種によって、労働者の安全や健康を守るための委員会の設置が『労働安全衛生法』第17条・第18条において義務づけられています。
これらの委員会は、職場で起こりうる事故や健康被害を未然に防ぐために、従業員の意見を反映しながら、必要な対策や取り組みについて話し合う場です。
安全と衛生、両方のテーマを一括して扱う「安全衛生委員会」として開催されるケースもありますが、それぞれに設置基準や役割、話し合う内容には違いがあります。
この記事では、3つの委員会の違いや設置義務のある事業場の条件、委員の構成、開催ルールについてわかりやすく解説していきます。
安全衛生委員会・安全委員会・衛生委員会の目的と役割の違い
企業における「安全委員会」「衛生委員会」「安全衛生委員会」は、いずれも働く人たちの安全や健康を守るために設けられている大切な組織です。
しかし、それぞれの委員会には守備範囲の違いがあり、会社の業種やリスクの種類によって求められる内容も異なります。
まずは、3つの委員会がそれぞれ何のために存在しているのか?という基本的な違いを押さえておきましょう。
● 衛生委員会の立ち上げ・体制再構築サポートプラン
これから衛生委員会を設置したいとお考えの事業所様、または既存の体制を見直してより効果的に運用したい企業様に向けた、
年間を通じて体制整備から実務運営までトータルで支援するプランです。
● 衛生委員会運営サポートプラン
すでに衛生管理体制が整っている企業様を対象に、
月1回の定例開催を中心とした運営支援に特化したシンプルなプランもご用意しています。
安全委員会|ケガや事故を未然に防ぐための委員会
「安全委員会」は、常時50人以上の労働者がいる事業場で、主に製造業・建設業・運送業など危険を伴う職場で設置が義務付けられている委員会です。
機械の取り扱いや重い物の搬送、高所作業など、物理的なリスクが高い職場環境において、従業員がケガや事故を起こさないための対策を話し合う場です。
たとえばこんなことを話し合います
- 機械・設備の点検や更新の必要性
- 危険な作業エリアでの安全対策
- ヒヤリハット事例の共有と改善
詳細については下記の通りとなります。
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
- 安全に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育の実施計画の作成に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
引用:「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」(厚生労働省)
衛生委員会:職場の健康とメンタルを守る委員会
「衛生委員会」は、すべての業種で、常時50人以上の労働者がいる会社に設置が義務づけられています。
肉体的なケガではなく、健康障害やメンタルヘルスの悪化を防ぐことが主な目的です。
近年では、長時間労働やストレスによるメンタル不調、感染症対策などが注目され、衛生委員会の重要性はますます高まっています。
たとえばこんなことを話し合います
- ストレスチェックの実施とその結果の活用
- 過重労働の防止策(時間外労働の実態把握など)
- インフルエンザやコロナ等の感染症対策
詳細については下記の通りとなります。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 定期健康診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
引用:「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」(厚生労働省)
安全衛生委員会|安全委員会と衛生委員会を統合した委員会
「安全衛生委員会」は、安全委員会と衛生委員会を統合した委員会です。
両方の委員会の設置が義務付けられている事業場では、それぞれを別々に開催する代わりに、「安全衛生委員会」を1つ設置することで両方の役割を兼ねることが可能です。
つまり、安全面と健康面の両方の課題を同時に話し合える場であり、事業者にとっても労働者にとっても、効率的かつ包括的な取り組みが可能になります。
たとえばこんなことを話し合います
- 高所作業や危険機械の対策と作業者のメンタルケアを同時に検討
- 労災リスクと職場環境(照明・換気など)の改善案
- 安全教育と健康診断の年間計画づくり
このように、それぞれの委員会は職場におけるリスクの種類に応じて役割が明確に分かれており、事業所の特性に合わせて適切に設置・運営することが求められます。
安全衛生委員会・安全委員会・衛生委員会の設置基準
安全委員会は、一定の業種に該当し、かつ従業員数が基準を満たす場合に設ける必要があります。一方、衛生委員会については業種を問わず、従業員が50人以上の事業場で設置が求められます。
両方の委員会を設置しなければならない場合には、これらを一本化し、安全衛生委員会として運営することも可能です。以下に、その基準を整理しました。
| 区分 | 業種の例 | 事業場の規模 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、清掃業 | 50人以上 | 必要 | 必要 |
| 2 | 製造業(1以外)、運送業(1以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | 必要 | 必要 |
| 2-補足 | 上記と同様の業種 | 50人以上100人未満 | 義務なし | 必要 |
| 3 | 上記1・2に該当しない業種 | 50人以上 | 義務なし | 必要 |
安全委員会・衛生委員会のメンバー構成
安全委員会および衛生委員会には、それぞれ以下のようなメンバーが必要です。
安全委員会の構成メンバー
- 委員長(1名)
総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する者(またはこれに準ずる者) - 安全管理者(事業者が指名)
- 安全に関する経験を有する労働者(労働者側の推薦が必要)
衛生委員会の構成メンバー
- 委員長(1名)
総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する者(またはこれに準ずる者) - 衛生管理者(事業者が指名)
- 産業医(事業者が指名)
- 衛生に関する経験を有する労働者(労働者側の推薦が必要)
メンバーの選出に関するルール
- 委員長(1名)以外の委員は、事業者が指名します。
- ただし、半数以上の委員は、労働者の推薦に基づき指名する必要があります。
- 労働組合がある場合:過半数で組織された労働組合の推薦による
- 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者の推薦による
おわりに
安全委員会・衛生委員会、そして安全衛生委員会は、職場で働く人の安全と健康を守るために、法律で定められた大切な仕組みです。
設置が必要かどうかは、業種や従業員数によって異なりますが、どの事業場であっても労働者の声に耳を傾け、安全・衛生について共に考えることが基本です。
義務だから形式的に設けるのではなく、実際に職場の課題を共有し、改善につなげていくための場として委員会を活用していくことが、結果として働きやすく健全な職場づくりにつながります。
また、50人以上の従業員がいる事業場では、衛生委員会のメンバーとして必要とされる産業医の選任も求められます。
このように、法令を満たすだけでなく、実際の職場状況に合った運営をするには、専門的なサポートが有効な場面も多くあります。
「どの委員会が必要なのか判断に迷っている」「産業医の選任や委員会の立ち上げに不安がある」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の状況に応じたサポートをご提案いたします。
参照
安全衛生委員会を設置しましょう(厚生労働省)
安全委員会、衛生委員会について教えてください。(厚生労働省)