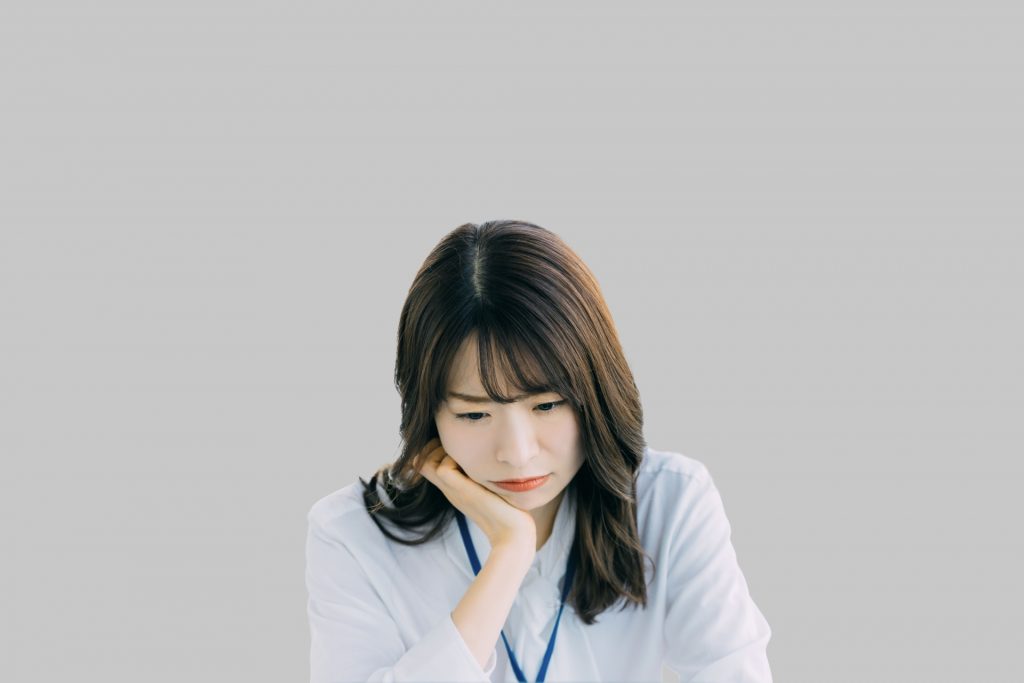ストレッサーとは、ストレスの原因となる刺激や出来事のことを指します。たとえば上司に叱られる、納期に追われる、暑さや寒さがつらいといった状況はすべてストレッサーです。そして、そのストレッサーに反応して心や体に起こる変化をストレスと呼びます。
つまり、ストレッサーがきっかけであり、ストレスはその結果と考えるとわかりやすいでしょう。今回は、ストレッサーの意味や種類、具体例、対処法を簡単に解説します。
ストレッサーとは?基本的な意味をわかりやすく解説
ストレッサーとは、心や体に負担をかけ、ストレス反応を引き起こす要因のことです。
大きく分けると、外部から働きかけるものと、内面から生じるものの二種類があります。
外部的なストレッサーには、暑さや寒さ、騒音などの環境条件、仕事や人間関係のトラブルなどが含まれます。一方、内的なストレッサーは、自分の考え方や感じ方から生じる不安、将来への心配などが代表的です。
このように、ストレッサーは形も内容も多様であり、日常生活のあらゆる場面に潜んでいます。自分にとってどのようなものがストレッサーとなりやすいかを知ることは、ストレス対策を考えるうえで欠かせません。
ストレスとは
ストレスとは、ストレッサーによって心や体に生じる反応や状態を意味します。強い緊張感、落ち込み、イライラといった心理的な変化から、頭痛や胃痛、肩こりなどの身体的な症状まで、その現れ方はさまざまです。
ストレスは必ずしも悪いものとは限りません。適度なストレスは集中力を高めたり、行動を促したりする働きがあります。しかし、長期間にわたって強いストレッサーにさらされ続けると、心身のバランスを崩し、不調につながるリスクが高まります。そのため、自分がどのようなストレス反応を示しやすいかを理解しておくことが大切です。
ストレッサーとストレスとの違い
ストレッサーは原因であり、ストレスはその結果です。たとえば、上司から厳しく注意を受けるという出来事がストレッサーであり、その出来事を受けて緊張や不安、疲労感といった反応が生じるのがストレスです。
この違いを理解せずにストレスを減らしたいと考えると、結果としてのストレス反応にしか対処できず、原因となるストレッサーが放置される恐れがあります。原因であるストレッサーを取り除くのか、それとも結果としてのストレス反応を和らげるのかによって、必要なアプローチは異なります。まずは両者の関係を正しく理解することが、効果的なストレスマネジメントの第一歩となります。
ストレッサーの主な種類
ストレッサーは大きく4つの種類に分けられます。
物理的ストレッサー(温度・騒音など)
 物理的ストレッサーとは、暑さ、寒さ、騒音、強い光など、外部環境が体に直接負荷をかける要因です。
物理的ストレッサーとは、暑さ、寒さ、騒音、強い光など、外部環境が体に直接負荷をかける要因です。
例えば、夏場の工場での高温環境、空調が不十分なオフィスなどは物理的ストレッサーとなりえます。こうした環境が長時間続くと、体温調節や集中力の維持が難しくなり、疲労感が増します。
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では、以下のような作業環境基準が定められています。
- 気積・換気:労働者1人あたり10㎥以上の気積を確保し、十分な換気を行うこと(第2条・第3条)
- 温度:室温はおおむね 17〜28℃ を基準とする(第5条)
- 照明:作業面の照度は 300ルクス以上を基準とする(第10条)
これらは作業効率を維持するだけでなく、心身の健康を守るための必須条件とされています。
生理的ストレッサー(病気・睡眠不足など)
 体の不調や睡眠不足、過労などがこれにあたります。職場では、長時間労働やシフト勤務、不規則な生活習慣が要因となることが多いです。
体の不調や睡眠不足、過労などがこれにあたります。職場では、長時間労働やシフト勤務、不規則な生活習慣が要因となることが多いです。
例えば、夜勤と日勤が交互にある交代勤務では、体内リズムが乱れて慢性的な睡眠不足を引き起こしやすくなります。また、過度の残業で休養が取れない状態も、生理的ストレッサーが強まる典型例です。
心理的ストレッサー(不安・人間関係の葛藤など)
 不安や恐れ、怒りといった感情が引き起こすものです。特に人間関係の問題や将来への心配は、多くの労働者にとって大きな心理的ストレッサーになります。
不安や恐れ、怒りといった感情が引き起こすものです。特に人間関係の問題や将来への心配は、多くの労働者にとって大きな心理的ストレッサーになります。
例えば、上司の期待に応えられないのではないかという不安、同僚との対立やコミュニケーション不足による緊張感、キャリアへの将来的な不安などです。
厚生労働省の「令和5年度 労働安全衛生調査」では、労働者の8割以上が「仕事や職業生活に関する強い不安やストレスを感じている」と回答しており、その要因の多くが人間関係や仕事の量・質に関わる心理的ストレッサーであることが分かっています。
社会的ストレッサー(職場環境・経済状況など)
 失業、転勤、経済的困難、家庭内での役割期待など、社会生活に由来する要因です。職場においては、人員削減による業務負荷の増大、不公平な評価制度、異動・転勤、育児や介護との両立困難などが代表的です。
失業、転勤、経済的困難、家庭内での役割期待など、社会生活に由来する要因です。職場においては、人員削減による業務負荷の増大、不公平な評価制度、異動・転勤、育児や介護との両立困難などが代表的です。
例えば、育児と仕事の両立を求められる中で制度や支援が十分でない場合、大きな社会的ストレッサーとなります。また、会社の経営不振による人員削減やリストラの不安も同様です。

このようにストレッサーは、身体的な負担から人間関係・社会的背景まで多岐にわたります。自分がどのタイプのストレッサーに影響を受けやすいかを意識することが、適切な対処法を見つける第一歩となります。
職場におけるストレッサーの具体例
職場では、組織で役割を担うことや人間関係、日々の業務遂行、さらには将来のキャリア形成など、さまざまな場面でストレッサーが発生します。
しかも、同じ出来事でも立場や状況によって受け止め方が変わるため、性質の異なるストレッサーに悩まされることがあります。
ここでは代表的な4つのストレッサーを整理し、従業員のストレス軽減を考える際の参考にしていただけるよう解説します。
役割や指示があいまい
部署内での役割や責任が大きすぎる場合や、逆に責任範囲が曖昧な場合、従業員は心理的な負荷を抱えやすくなります。
とくに上司からの指示があいまいで何を優先すべきかわからない状況は大きなストレッサーとなり、業務効率の低下や不安感を招きます。
人間関係
上司や同僚、部下とのコミュニケーションの不和は、職場で最も一般的なストレッサーのひとつです。上司の過度な叱責や部下の指導への不安、同僚間の対立や孤立など、人間関係の摩擦は心身に大きな影響を与えます。
業務量や進め方
業務量の過多、短納期、必要な情報の不足など、仕事の進め方そのものがストレッサーになる場合があります。とくにタスクの割り振りが不公平であったり、必要なサポートが得られなかったりすると、従業員は大きなプレッシャーを感じます。
将来のキャリアや評価への不安や不満
昇進や異動、将来のキャリアパスへの不安などもストレッサーとなります。自分の希望が反映されない人事異動や評価制度の不透明さは、長期的にモチベーション低下や離職意向の高まりにつながる可能性があります。
職場におけるストレッサーへの対処法
職場のストレッサーは完全になくすことが難しい場合が多くあります。しかし、負担を軽減し心身の安定を保つためには、状況に応じた対処法を知っておくことが有効です。ここでは、職場で活用できる実践的な方法を4つの観点から整理します。
ストレッサーを認識する
まずは自分にとって何がストレッサーになっているのかを把握することが重要です。
例えば、上司の叱責で強く緊張しているのか、納期に追われて疲弊しているのかを明確にすることで、対策の方向性が見えやすくなります。職場で実施されるストレスチェックや面談を活用すれば、主観だけでなく客観的に自分の状態を確認できます。
対処できるストレッサーとできないストレッサーを区別する
業務量や作業環境の改善は、上司に相談して調整できる場合があります。例えば担当業務の優先順位を明確にしたい、納期の調整を依頼したいと具体的に伝えることは効果的です。
一方で、人間関係の相性や組織文化のようにすぐに変えられないストレッサーも存在します。その場合は、割り切りや受け止め方の工夫が必要です。
対処できる部分とできない部分を整理することで、過度に抱え込まずに済みます。
セルフケアでストレス反応を和らげる
業務が立て込みやすい職場では、こまめな休憩や深呼吸、ストレッチを取り入れるだけでも反応を和らげることができます。
また、勤務後には睡眠の質を高めたり、適度な運動を行ったりすることで回復力を養えます。趣味やリラックスできる時間を持つことも、翌日のパフォーマンスを維持するために大切です。
支援制度を活用する
社内にある人事・労務相談窓口、産業医、メンタルヘルス相談員などを積極的に利用しましょう。外部EAP(従業員支援プログラム)のように、社外の専門家に気軽に相談できる仕組みを整えている企業もあります。
上司がストレッサーとなる場合の対応策
職場におけるストレッサーの中でも、人間関係は大きな割合を占めています。その中でも上司との関係は、立場や評価権限がある分、強いストレスにつながりやすい要因とされています。
日常的な指導の仕方やコミュニケーションの取り方によって、従業員の心理的負担は大きく変わります。ここでは、上司がストレッサーとなる場合に実践できる具体的な対応策を紹介します。
コミュニケーションを工夫する
上司とのやり取りでは、感情的にならず事実ベースで伝えることが大切です。
例えば「業務が多すぎてつらい」と言うよりも、「来週の納期が3件重なっており、残業が続いています。このままでは品質に影響する可能性があります」と状況を具体的に説明した方が、冷静かつ建設的に受け止められやすくなります。また、単なる要望ではなく相談という姿勢で臨むと、相手も受け入れやすくなります。
境界線を引く
過剰な干渉や要求に対しては、自分の業務範囲や優先順位を明確に伝えることが有効です。「この作業はAプロジェクトに影響があるため、まずはこちらを優先したい」といったように、合理的な理由を添えて説明することで、対立を避けつつ心理的な境界線を守ることができます。
第三者・制度を活用する
上司との直接のやり取りで改善が難しい場合は、人事や労務部門、産業医などの第三者に相談する方法があります。
中立的な立場を介すことで、問題が個人の不満ではなく組織全体の課題として扱われやすくなります。また、ストレスチェックの集団分析結果を活用すれば、部署全体の働き方を見直す契機につなげることも可能です。
自分自身の健康を守るための選択
努力しても改善が見込めない場合には、異動や転職を検討することも必要です。上司との関係に強いストレスを抱え続けることは、心身の不調を引き起こすリスクがあります。長期的に働き続けるためには、環境を変えることも前向きな選択肢のひとつと捉えるべきでしょう。
おわりに
ストレッサーとは、ストレスを生み出す原因そのものであり、私たちの働く環境には多種多様な形で存在しています。温度や騒音といった物理的要因から、人間関係やキャリアへの不安に至るまで、ストレッサーの影響は避けることができません。しかし、重要なのは自分にとってどのような状況が負担になりやすいのかを認識し、適切な方法で向き合うことです。
本記事で紹介したように、ストレッサーには調整できるものとすぐには変えにくいものがあり、セルフケアや相談体制の活用、さらには環境を変える選択など、対応の幅は一つではありません。特に上司との関係が大きなストレッサーとなる場合もありますが、冷静なコミュニケーションや第三者の支援を活用することで改善の糸口を見出せる可能性があります。
働く上でストレッサーを完全になくすことはできませんが、正しい理解と工夫によって、その影響を和らげることは可能です。日々の取り組みの中で、適切なメンタルヘルス対策やストレスマネジメントを実践していきましょう。