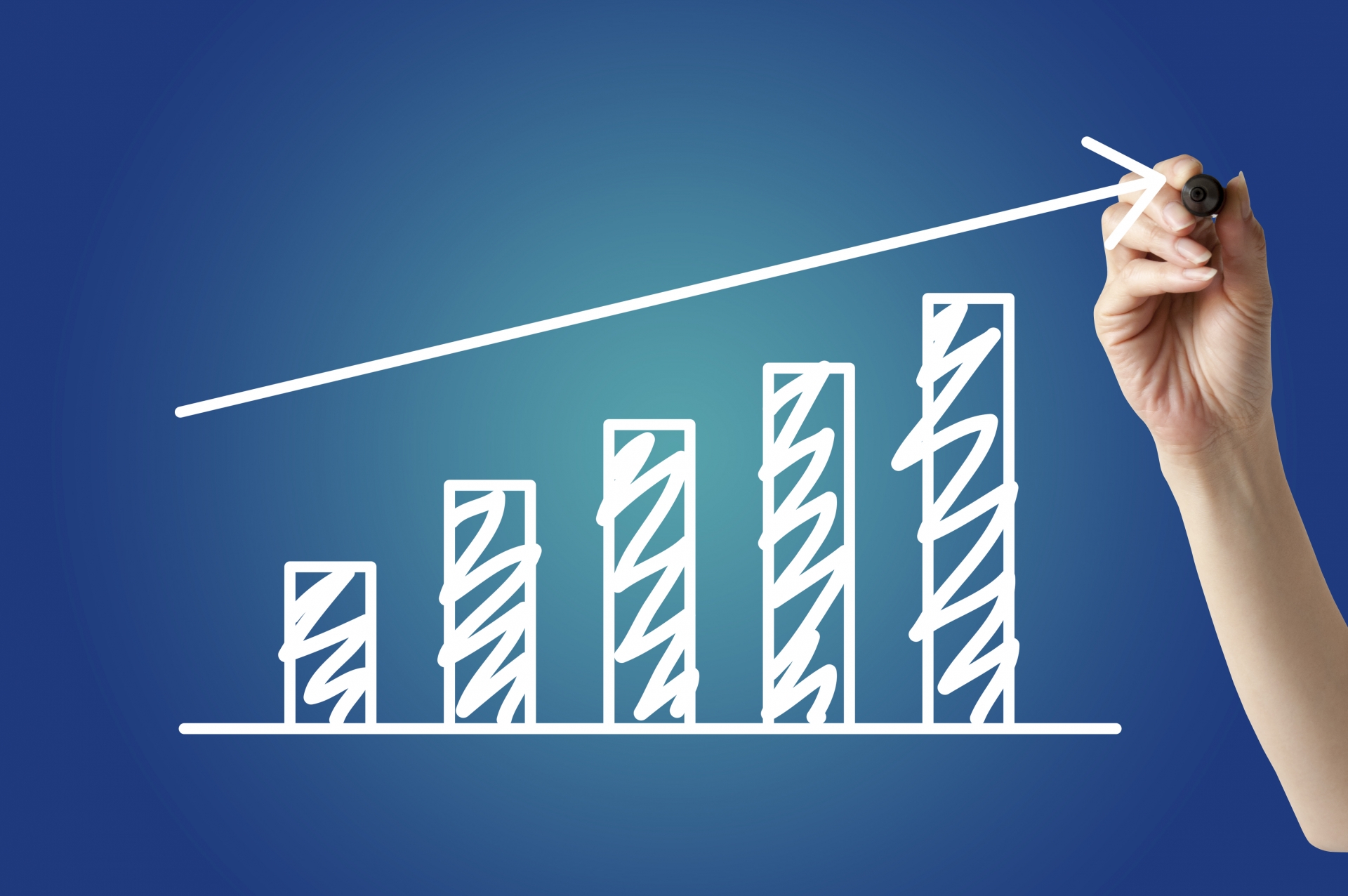厚生労働省は令和6年度(2024年度)の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。
厚生労働省の統計によると、業務による精神障害の労災補償請求件数、決定件数、そして支給決定件数はいずれも増加傾向にあり、職場の心の健康問題が深刻化している現状が浮き彫りになっています。EAP(従業員支援プログラム)を提供する企業として、このデータが示す意味と、企業が従業員の心の健康問題に対してどのような対策を検討しうるか、その選択肢の一つとしてEAP(従業員支援プログラム)の役割に焦点を当てて解説します。
精神障害に係る労災補償状況の推移
令和2年度から令和6年度にかけてのデータを見ると、精神障害による労災請求件数は2,051件から3,780件へと大幅に増加しています。これに伴い、決定件数も1,906件から3,494件に、支給決定件数も608件から1,055件へと増加の一途をたどっています。これは、職場で精神的な不調を訴える従業員が増えているだけでなく、それが業務に起因すると認められるケースが増加していることを明らかにしています。
| 区分 / 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神障害 | 請求件数注2 | 2051 ( 999 ) | 2346 ( 1185 ) | 2683 ( 1301 ) | 3575 ( 1850 ) | 3780 ( 1963 ) |
| 決定件数注3 | 1906 ( 887 ) | 1953 ( 985 ) | 1986 ( 966 ) | 2583 ( 1283 ) | 3494 ( 1784 ) | |
| うち支給決定件数注4 [認定率]注5 |
608 ( 256 ) [31.9%] ( 28.9% ) |
629 ( 277 ) [32.2%] ( 28.1% ) |
710 ( 317 ) [35.8%] ( 32.8% ) |
883 ( 412 ) [34.2%] ( 32.1% ) |
1055 ( 503 ) [30.2%] ( 28.2% ) |
|
| うち 自殺注6 |
請求件数 | 155 ( 20 ) | 171 ( 15 ) | 183 ( 29 ) | 212 ( 24 ) | 202 ( 33 ) |
| 決定件数 | 179 ( 17 ) | 167 ( 20 ) | 155 ( 20 ) | 170 ( 23 ) | 215 ( 27 ) | |
| うち支給決定件数 [認定率] |
81 ( 4 ) [45.3%] ( 23.5% ) |
79 ( 4 ) [47.3%] ( 20.0% ) |
67 ( 6 ) [43.2%] ( 30.0% ) |
79 ( 7 ) [46.5%] ( 30.4% ) |
88 ( 7 ) [40.9%] ( 25.9% ) |
|
※()内は、全体の件数のうちの女性の件数。なお認定率の()内は、女性の決定件数に占める支給決定件数。
1 本表は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に係る精神障害について集計したものである。
2 請求件数は、当該年度中の労災保険給付の請求件数であるが、必ずしも同年度中に決定(支給・不支給)されているものではない。
3 決定件数は、当該年度中の支給・不支給決定件数の計であり、前年度以前に請求されたものについて決定した件数を含んでいる。
4 支給決定件数は、決定件数のうち「業務災害」と認定した件数である。
5 認定率は、決定件数に占める支給決定件数の件数の割合である。
6 自殺は、未遂を含む件数である。
精神障害発症につながる主な「出来事」の傾向
精神障害の発病に関与したと考えられる事象は、労災認定基準において「出来事」として類型化され、その心理的負荷の強度が評価されます。 支給決定された事案を「出来事」別に見てみると、特に以下の傾向が顕著に現れています。
-
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」:224(101)件
-
「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」:119(40)件
-
「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」:108(78)件
※令和6年度支給決定件数より。()内は、全体の件数のうちの女性の件数。
厚生労働省の調査によると、職場におけるストレスの原因として、パワーハラスメントが224件(うち女性101件)と最も多く報告されています。これは、上司などからの身体的または精神的な攻撃が、依然として多くの従業員にとって深刻な問題であることを示しています。
次に多いのが、「仕事内容・仕事量の大きな変化」で119件(うち女性40件)です。これは、配置転換や業務量の急激な増減など、仕事環境の大きな変化が従業員にストレスを与えていることを示唆しています。変化への適応は誰にとっても負担となることがあり、適切なサポート体制の重要性が浮き彫りになります。
そして、「顧客や取引先、施設利用者等からの著しい迷惑行為」が108件(うち女性78件)と続いています。これは、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)が職場における大きなストレス要因となっていることを示しています。特に、女性の支給決定件数が約7割を占めている点は注目すべきです。対人業務が多い職種、例えばサービス業はもちろんのこと、医療、介護といった分野においても、女性従業員が不当な要求や言動に晒されるケースが多く、それに伴う精神的なダメージも深刻であることがうかがえます。
EAPの視点からの課題
これらのデータから見えてくるのは、以下のような現状と課題です。
メンタルヘルス不調の顕在化
請求件数の増加は、従業員が自身の心の不調を認識し、支援を求める意識が高まっていること、それに伴い企業がメンタルヘルス問題に直面する機会が増えていることを示しています。
職場環境のストレス要因
パワーハラスメントやカスタマーハラスメント、大きな環境変化、長時間労働など、精神的な負荷を高める特定の要因が明確になっています。これらは、職場環境の改善において優先的に取り組むべき具体的な課題と言えるでしょう。
労災認定リスクの増加
企業にとっては、精神障害による労災認定が増えることで、経済的な負担だけでなく、企業イメージや従業員のエンゲージメントへの影響といった潜在的なリスクが生じ得ます。
EAPの役割【予防から職場復帰支援まで】
このような状況において、EAPは企業の心の健康対策を支える選択肢の一つとなり得ます。EAPが提供できる支援としては、以下のような点が挙げられます。
早期発見・早期対応
従業員が心の不調を感じた際に、気軽に相談できる窓口を提供することで、問題が深刻化する前に早期に発見し、適切な支援につなげることができます。これは、労災請求に至る前に問題を解決するための重要なステップです。
予防的アプローチ
ストレスチェック後の高ストレス者への面談、管理職向けのラインケア研修、従業員向けのセルフケア研修などを通じて、メンタルヘルス不調の予防に取り組みます。これにより、職場全体のストレス耐性を高め、健康的な職場環境の整備をサポートします。
複雑なケースへの対応
対応が難しい、複雑なケースに対してのカウンセリング、危機介入、専門機関への紹介など専門的な知見に基づいたサポートを提供します。※EAP提供会社によってカバー範囲・対応の質・専門性は異なります。
より良い職場環境への提言
相談内容や傾向を分析し、匿名化されたデータとして企業にフィードバックすることで、組織全体の課題を特定し、職場環境改善に向けた具体的な提言を行います。これにより、企業の健康経営を支援し、持続可能な組織運営に貢献します。
まとめ
精神障害による労災の増加は、企業にとって「心の健康」が経営上の重要な課題であることを明確に表しています。従業員のウェルビーイング向上や企業のレジリエンス強化を目指す上で、EAPのような外部の専門的な支援プログラムの活用も、職場環境づくりの一助となるかもしれません。
【参考資料 】厚生労働省 業務災害に係る精神障害の労災補償状況