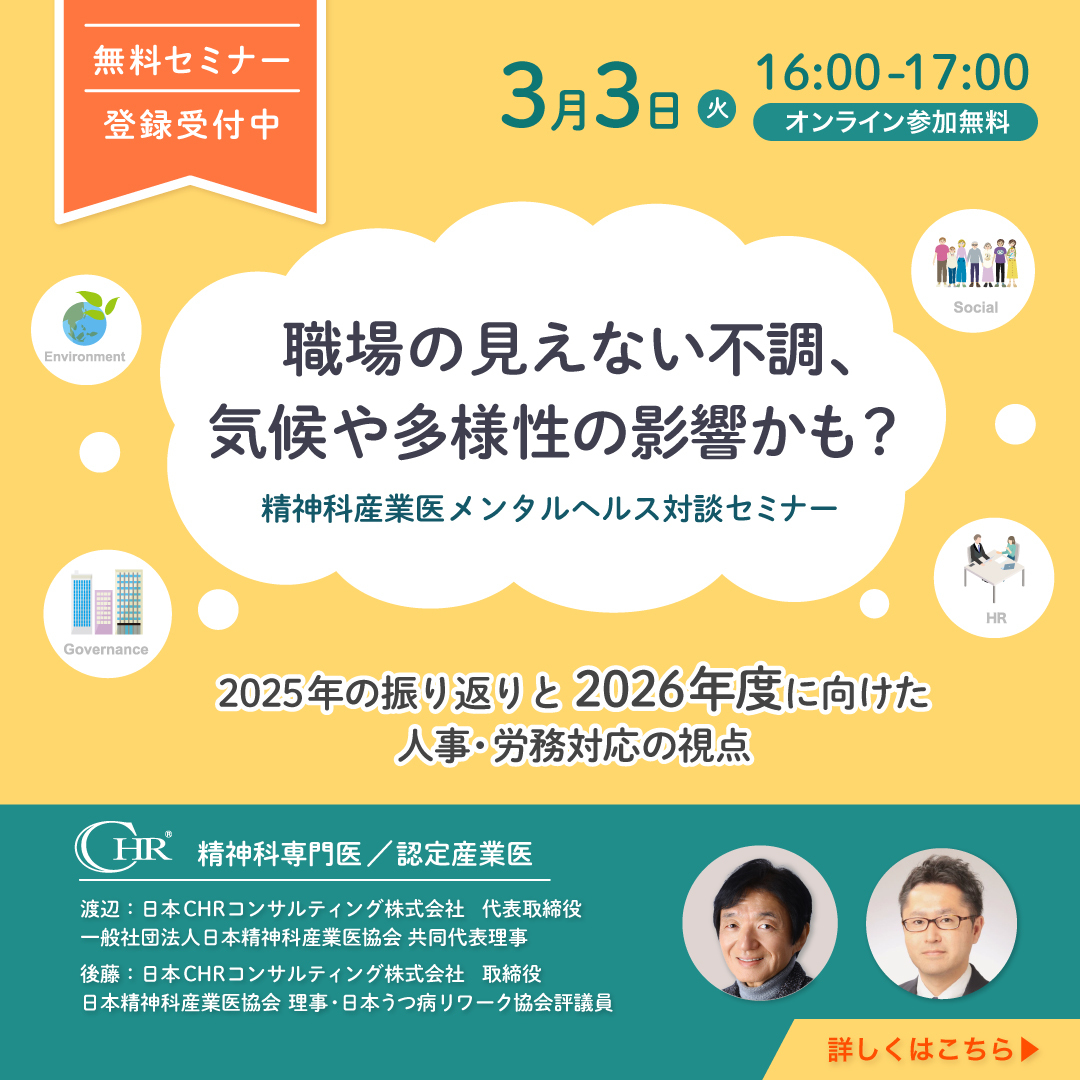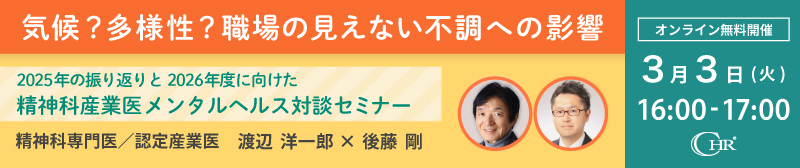EAP(従業員支援プログラム)のなかに、従業員が相談できる窓口の設置があります。メンタルヘルスの問題を抱えたとき、だれかに相談できるということは「心の健康」を保つために有効な手段です。
この相談窓口で行われるのがカウンセリングであり、専門資格を持つ心理の専門家によって対応されます。
EAPの相談員としてメンタルヘルス不調に対してアドバイスやフォローを行う公認心理師、臨床心理士、そして産業カウンセラーは、それぞれ異なる専門性を持ちながらも、従業員の「心の健康」を支えるために重要な役割を果たしています。
カウンセリングとは
EAPの一環として、従業員が相談できる窓口の設置があり、専門の資格を持ったカウンセラーによるカウンセリングが行われます。
厚生労働省はカウンセリングを以下のように定義しています。
カウンセリングは、主に心理の専門家がクライエントや患者の話を傾聴したり受容したりしながら、クライエントや患者の心情や状況の理解に努めることによって、主体的に問題の解決を行っていけるようにサポートすることを指します。
カウンセリングとは、相談者が自分自身の課題を乗り越え、自己を受け入れ、新しい自分に生まれ変わる過程を、心理の専門家が対話を通じてサポートする取り組みといえます。
カウンセリングに関して、多くの人がカウンセラーがアドバイスを行っていると思っているかもしれませんが、実際にはカウンセラーはアドバイスをしないのです。主な役割は、相談者の悩みをじっくりと聞き、対話を通じて相談者が自らの心を整理し、新たな「気づき」を得る手助けをすることです。
では、どのような心理の専門家がカウンセリングを行うのでしょうか?
EAPにおけるカウンセラーの役割とカウンセリングとは
EAP(従業員支援プログラム)では、従業員のメンタルヘルスをサポートするために、専門のカウンセラーによる「カウンセリング」が提供されています。
カウンセリングは、単なる悩み相談ではなく、相談者が自らの課題や感情に気づき、前向きな一歩を踏み出すためのプロセスです。
EAPにおけるカウンセリングでは、職場におけるストレスや人間関係、キャリアに関する悩みなどに対して、心理的専門性を持つカウンセラーが対応します。
こうしたカウンセリングを実施するのが、公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーといった専門職です。
それぞれの専門家は異なる資格や背景を持ちながらも、EAPの現場で従業員の「心の健康」を支える重要な役割を担っています。
以下では、EAPにおけるカウンセリングの実際と、それを担う専門家の役割・違いについて解説します。
公認心理師
公認心理師は2017年施行の公認心理師法で定められた、日本で初めての心理に関する国家資格です。従業員個々の心の問題に寄り添い、カウンセリングや心理療法を通して解決をサポートする専門家です。
公認心理士の定義
公認心理師については、厚生労働省のホームページでは以下のように定義されています。
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
※引用元:公認心理師 |厚生労働省
具体的には、以下のような業務を行います。※()内の数字は上記に対応しています。
(1)面接や観察、各種の心理検査等を通して、対象者の心理状態を幅広い方向から捉えます(心理アセスメント)。このアセスメントが、その人自身の支援や関係者への援助、他職種との連携にも大きく役立つことになります。
(2)心理アセスメントを基に、カウンセリングや相談者に合った心理支援を行います。
(3)心理アセスメントを基に、必要に応じ相談者の関係者(家族や上司など)への援助を行います。
(4)心の健康に関する教育や情報提供を行うことが求められています。
これらが公認心理師の主な仕事内容と定義されています。
公認心理師は、心理アセスメントを軸として、従業員が抱える心の問題に専門的な知識と技術を用いて対応します。また、EAPにおいては従業員との面談やカウンセリングの実施を通じて、問題の早期発見・解決を図る役割も担っています。
さらに公認心理師は、労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を修了することで、ストレスチェックの実施者となることができます。
臨床心理士
臨床心理士は1988年に資格認定が開始された心理系の民間資格ですが、公認心理師制度ができる前は心理士の最も代表的な資格とされていました。
臨床心理士になるためには、臨床心理士の養成を行う専門職大学院を修了するか、指定の大学院を卒業終了する必要があります。その後、日本臨床心理士資格認定協会が実施する試験に合格すれば、臨床心理士として活動を始めることができます。
「臨床心理士」は、臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、メンタルヘルス支援専門家の一員として職場での面談などの心理的援助を行っています。
臨床心理士の専門業務
臨床心理士に求められる業務内容は下記の4種があげられます。
| (1)臨床心理査定 | 種々の心理テストや観察面接を通じて、個々人の独自性、個別性の固有な特徴や問題点の所在を明らかにします。また同時に、心の問題で悩む人々をどのような方法で援助するのが望ましいか明らかにしようとします。 |
|---|---|
| (2)臨床心理面接 | クライエントの特徴に応じて、さまざまな臨床心理学的技法を用いて、クライエントの問題解決に資する心理支援を行います。 |
| (3)臨床心理的地域援助 | 特定のクライエントのみならず、地域住民や団体に属する人々に向けて支援活動を行います。また、一般的な生活環境の健全な発展のために、心理的情報を提供したり提言する活動も地域援助の業務に含まれます。 |
| (4)上記3つの要素に関する調査・研究 | 心の問題への支援を行ううえで、知識や技術をより確実なものとするために、基礎となる臨床心理的調査・研究活動を実施します。 |
(引用:公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理士とは」)
臨床心理士は、対話をベースに、精神分析や心理療法を使って問題の解決をサポートします。産業・労働領域においては、労働者に対するカウンセリングやメンタルヘルスに関する研修の実施、職場内でのコンサルテーション、職業適性に関する支援を担います。
産業カウンセラー
産業カウンセラーとは、働く人たちや組織が抱える問題を自らの力で解決できるよう、心理的な手法を用いて支援することを目的とする、民間資格とその有資格者のことを指します。1992年から資格の認定が開始されました。産業カウンセラーを名乗るには、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格を取得する必要があります。
産業カウンセラーの3つの活動領域
| (1)メンタルヘルス対策への支援 | メンタルヘルス不調の予防や危機への介入、職場復帰の支援、ストレスチェック後のフォローなど、個人および組織を対象とした幅広い支援を行います。 |
|---|---|
| (2)キャリア形成への支援 |
人生の転機における悩み相談や、実際の仕事選びに関するアドバイス、研修など、個人のキャリア形成を支援するニーズが高まっているため、働く人のキャリア教育やキャリア・カウンセリングを行います。 |
| (3)職場における人間関係開発・職場環境改善への支援 |
働きがいや働きやすさを実現するためには、個々のコミュニケーション能力の向上だけでなく、職場環境の改善も重要です。産業カウンセラーは、人や組織と連携し、グループファシリテーション能力の向上を目的とした研修を行うほか、組織診断を通じて職場環境の改善提案なども行います。 |
主に企業内においては、メンタルヘルスに関する様々な教育・研修や、職場における人間関係やキャリアに悩む方のカウンセリングとケアを行います。また職場の人間関係や職場環境の改善に向けて取り組みます。
まとめ
職場は、従業員にとって人生の大部分を過ごす場所です。そこでの人間関係や仕事のプレッシャーは時に大きなストレスとなり、心身の健康に影響を及ぼすことがあります。
職場におけるメンタルヘルス問題は、その原因も症状も人それぞれ、人間関係や働き方の変化によって悩みは多様化しています。そのため、一辺倒ではなく、状況に応じた柔軟なサポートが求められています。
公認心理師、臨床心理士、産業カウンセラーなどの、EAP(従業員支援プログラム)の相談窓口でカウンセリングを行う専門家は、それまで培った経験をもとにしながら従業員一人ひとりの心に寄り添い、メンタルヘルス不調の早期発見や解決を支援します。従業員が心身の健康を維持しながら、良好なコンディションでパフォーマンスを発揮し続けるために、企業と専門家が連携することが重要です。
CHRでは企業の従業員様向けの24時間365日相談受付の専門相談窓口サービス『ハートの窓』を提供しています。(ご契約者は企業、従業員様のご利用は無料です)
従業員の方には、
●職場・仕事の悩み、家庭からの悩み
●健康(精神面)の悩み、健康(身体面)の悩み
●消費者問題、借金問題 等など、従業員の方からのあらゆる問題解決をサポート。
管理監督者の方には、
●部下のメンタルヘルス対応
●職場環境改善についての悩み
●安全配慮義務
●部下とのコミュニケーション など管理監督者の方のあらゆる悩みをサポート。
人事労務ご担当者の方には、
●従業員の健康管理対策
●職場のメンタルヘルス対応
●相談システムの構築
●場環境改善のきっかけ 等など、人事労務ご担当者の方からのあらゆる問題解決をサポートします。
「メンタルヘルス予防」+「ラインケア支援」で職場環境改善につながる健康経営時代の新しい外部相談窓口『ハートの窓』の導入について、どんなことでもお気軽にご相談ください。