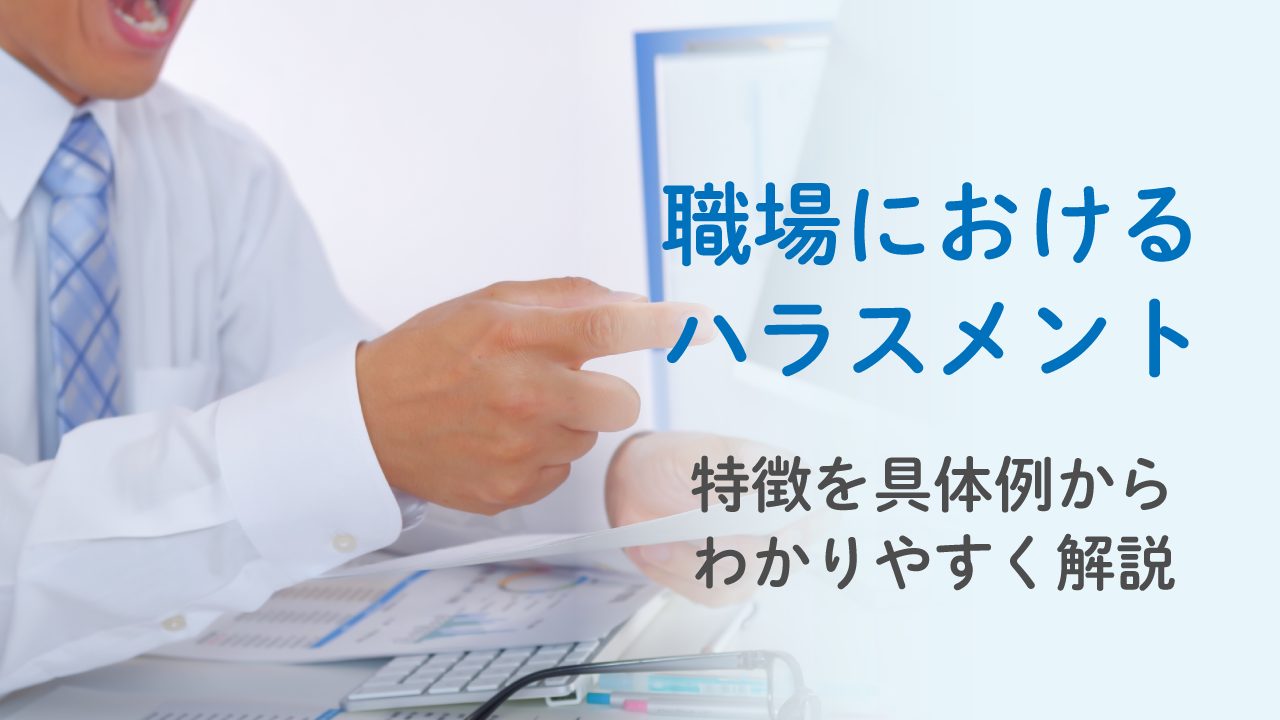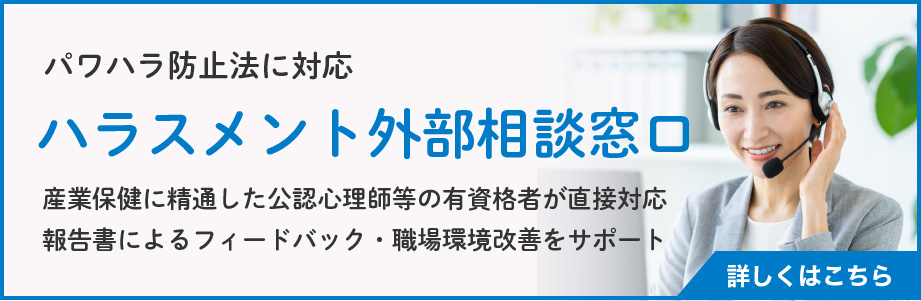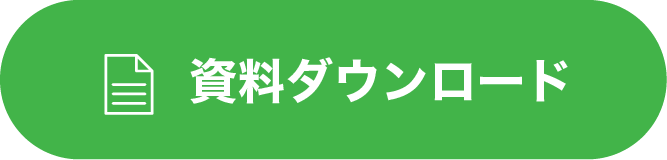ハラスメントとは、相手に対して言動や行動などで嫌がらせを行うことをいいます。
上司が部下に対してなど上下関係を利用して嫌がらせをするパワハラ(パワーハラスメント)や、性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)などがあります。
特に職場におけるパワハラは社会問題となり、「パワハラ防止対策関連法(ハラスメント規制法・パワハラ防止法)」が制定され、2020年6月1日から施行されました。2022年4月から、それまで大企業を対象としていた制度が、中小企業にも適用されています。
今回は職場におけるハラスメントはどのようなものがあるのか、具体例とともわかりやすくお伝えします。
ハラスメントとは?
ハラスメント(Harassment)とは、相手の意に反する行為によって不快にさせたり、相手の人間としての尊厳を傷づけたり、脅したりするようなことを指します。
ハラスメントは「いじめ」や「嫌がらせ」と同じような意味と捉えてもよいでしょう。
一般的にハラスメントは、職場だけではなく家族、学校、友達同士など人間関係があるところではどこでも生じる可能性があります。
職場におけるハラスメントの定義とは?
職場におけるハラスメントとは、上司と部下など上下関係を利用して行われるハラスメントのことをいい、次の3つの要素を全て満たすものを言います。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるものである
① 優越的な関係を背景とした言動
「優越的な関係を背景とした言動」とは、言動を受ける労働者が、その行為者に対して、抵抗や拒絶をすることが難しい関係を背景として行われるものです。
具体的な例としては、上司と部下、先輩と後輩などが挙げられます。
「優越的な関係を背景とした言動」というと、立場が上である上司による言動に限られると思われるかもしれませんが、同僚や部下からの集団的な行動なども「優越的な関係を背景とした言動」に当てはまる場合があります。
ハラスメントは直接的な言動だけでなく、間接的な影響を及ぼす行為も含まれます。例えば、以下のような行為が挙げられます
権威を振りかざす行為
部下の意見を無視し、自分の意見だけを押し付ける。また、部下の意見を聞くふりをして実際には考慮しないケースも該当します。
無視や孤立させる行為
特定の従業員をミーティングから除外する。さらに、重要な情報を意図的に共有しないことで孤立を助長する場合もあります。
過剰な監視
業務内容や勤務態度を執拗に監視し、不必要なプレッシャーをかける。
これらの行動は、従業員間の信頼を損ない、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。特に長期間にわたり続く場合、心理的な負担が蓄積し、職場離脱や健康問題を引き起こすリスクが高まります。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、常識的に考えて業務上明らかに必要のない言動のことを示します。職場の指導や指示が必要以上に厳しかったり、不適切な方法で行われると、それはハラスメントと見なされることがあります。
例えば⋯
- 業務上、必要性がないと認められる行為や発言
- 業務の目的から大きく逸脱している行為や発言
- 業務遂行の手段として不適切な行為や発言
- 行為の頻度や行為者の数など、社会通念を超える行為や発言
これらを判断する際には、幅広い視点で状況を分析することが求められます。具体的には、次のようなことを総合的に考慮することが重要です。
- 問題となる行為や発言の目的
- それを受けた労働者に問題行動があったかどうか、またその内容や程度
- 行為や発言が行われた背景や状況
- 業種や業態、業務内容やその特性
- 行為や発言の状態、頻度、継続性
- 労働者の個人的な特性や心身の状態
- 行為者との関係性
さらに、個別のケースで労働者の行動が問題視される場合、なぜそのような行動に至ったのか、どのような背景があるのか冷静に確認することが重要です。
たとえ労働者に問題行動があったとしても、その人間性を否定するような言動や、業務上必要かつ適切な範囲を超える行為があった場合、それは職場におけるパワーハラスメントとみなされる可能性があります。
③労働者の就業環境が害される
「労働者の就業環境が害されるもの」とは、暴力や、人格や名誉を傷つけるような言動等により身体的精神的な苦痛から、職場での能力の発揮を阻害されることです。
(例)
- 暴力により傷害を負わせる
- 何度も大声で怒鳴る
- 厳しい叱責を執拗に繰り返すなどにより、恐怖を感じさせる行為
- 長期にわたる無視や能力に相応しくない仕事を与え、就労意欲を低下させる行為
このように、職場におけるハラスメントとは、① 優越的な関係を背景とした言動であって② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③ 労働者の就業環境が害されるものである、この①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
それでは職場のハラスメントは具体的にどのようなものなのでしょうか。
厚生労働省では、具体的な言動の類型を6つ挙げています。
職場におけるパワーハラスメントの具体的な言動
厚生労働省が定義づける職場のパワーハラスメントの具体的な言動の類型は次の6つです。
- 身体的な攻撃:暴行・傷害など
- 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・ひどい暴言など
- 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視など
- 過大な要求: 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
それぞれの具体的な言動と、それには当てはまらないものについては次の通りです。
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
【具体例】
- 殴打、足蹴りを行う。
- 相手に物を投げつける。
【該当しない例】
- 誤ってぶつかる。
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
【具体例】
- 人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
- 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。
- 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。
- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信する。
【該当しない例】
- 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意する。
- その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする。
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
【具体例】
- 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
【該当しない例】
- 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する。
- 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる。
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
【具体例】
- 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。
- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。
- 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる。
【該当しない例】
- 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
- 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる。
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
【具体例】
- 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
- 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
【該当しない例】
- 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する。
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
【具体例】
- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
【該当しない例】
- 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う。
- 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す。
以上、パワーハラスメントの具体例について見てきました。
しかし、職場におけるハラスメントは、パワーハラスメントに限りません。その他の職場で発生しうるハラスメントについて確認していきましょう。
職場のハラスメント|セクシャルハラスメント
セクシュアルハラスメン卜とは、職場において行われる労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によって、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることをいいます。
セクシャルハラスメントの行為者になるのは、職場における上司や同僚に限りません。
取引先、顧客、患者、学校での生徒や学生などもセクシャルハラスメントの行為者になりえます。
セクシャルハラスメントの分類
セクシャルハラスメントは、「対価型」と「環境型」に分類されます。
対価型セクシャルハラスメント
【具体例】
- 事業主が従業員に性的な関係を要求したが拒絶されたため、その従業員を解雇すること。
- 出張中の車内で上司が従業員の腰・胸などに触ったが、抵抗されたため、不利益な配置転換を行うこと。
環境型セクシャルハラスメント
【具体例】
- 事務所内で上司が従業員の肩・腰などにたびたび触ったため、従業員が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
- 同僚が取引先に「性的にふしだらである」などの噂を流したため、 従業員が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
- 事務所内にヌードポスターを掲示しているため、従業員が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
職場のハラスメント|マタニティハラスメント
マタニティハラスメントとは、職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントのことです。
職場において上司・同僚から、妊娠や出産したこと、育児休業制度を利用していることについての言動により、妊娠・出産した女性従業員や、育児休業の取得・申請した従業員の就業環境が害されることをいいます。
マタニティハラスメントの類型
マタニティハラスメントには、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」があります。
制度等の利用への嫌がらせ型
【具体例】
- 産前休業の取得を上司に相談したところ、「休みをとるならやめてもらう」と言われた。
- 軽易な業務への転換を上司に相談したところ、「そういうことをされると迷惑だ」と言われ、請求をあきらめざるを得ない状況になっている。
- 制度等を利用したことで上司から「時間外労働ができない人には大した仕事を任せられない」と継続的に言われ、雑務のみさせられる状況となる。
制度等の利用への嫌がらせ型
【具体例】
- 上司に妊娠を報告したところ、「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。
- 職場の先輩から「就職したばかりのくせに妊娠するなんて図々しい」と何度も言われ、就業意欲が低下している。
まとめ
職場においてハラスメントを予防するためには、まずは経営者も従業員も「ハラスメントとはどのようなものなのか」ということを正しく理解することが大切です。
相手が不快に感じない言葉はどのようなものか想像力を働かせ、お互いに尊重しあうコミュニケーションをとること、は生産性の高い職場環境づくりにも繋がります。
参照:職場におけるハラスメント防止ハンドブック(厚生労働省)