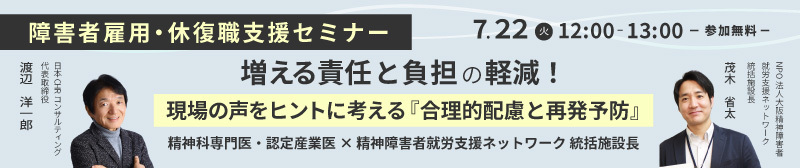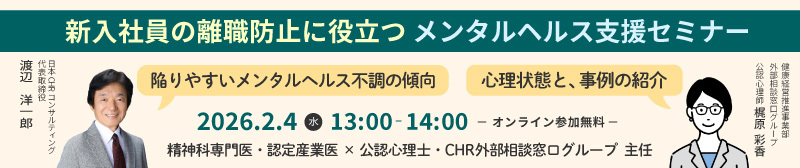社会のグローバル化や価値観の多様化が進む中、企業では性別や年齢、国籍、障がいの有無、働き方の志向など、さまざまな違いを持つ人材を受け入れ、その力を活かすことがますます重要になっています。
「ダイバーシティ(多様性)」や「インクルージョン(包摂)」といった言葉も、ニュースやビジネスの場でよく目にするようになりました。
でも、いざ「具体的にどんな意味なのか」「どう違うのか」となると、はっきり説明するのは意外と難しいものです。今回は、インクルージョンの意味やダイバーシティとの違い、企業が直面する課題、具体的な事例、成功のポイントまで、幅広く解説していきます。
インクルージョンとは?
インクルージョンという言葉は、ダイバーシティと並んでよく使われるようになりましたが、具体的にどんな意味なのか、何を指すのかは意外と知られていないかもしれません。
ここでは、インクルージョンの基本的な意味や定義を、ダイバーシティとの関係性も含めてわかりやすく整理します。
インクルージョンの基本的な意味とは
インクルージョン(Inclusion)は、日本語では「包含」「包摂」などと訳され、単に多様な人材を受け入れるだけでなく、それぞれの個性や特性を組織の中で活かし、誰もが安心して力を発揮できる状態を指します。
つまり、インクルージョンは多様な人材が存在するだけでなく、その多様性が組織の力や価値につながっている状態です。
職場の例でいえば、性別、年齢、国籍、障がいの有無、価値観の違いなどにかかわらず、全員が意見を出し合い、尊重されている環境がインクルージョンの実現例です。表面的な多様性ではなく、内面の充実につながる働きやすさや活躍しやすさを生み出す土台となる概念です。
厚生労働省が示すインクルージョンの定義
厚生労働省では、ダイバーシティ&インクルージョンを「年齢や性別、国籍、学歴、特性、趣味嗜好、宗教などにとらわれない多種多様な人材が、お互いに認め合い、自らの能力を最大限発揮し活躍できること」と位置づけています。この考え方は、さまざまな違いを持つ人々が、安心して暮らし働ける社会の実現を目指すものです。
厚生労働省の資料では、ダイバーシティとインクルージョンは相互に関連するものとして捉えられています。多様な人材を受け入れるだけでなく、その多様性が職場や社会の力となるよう、誰もが活躍できる環境づくりの重要性が示されています。
また、D&Iの推進は、少子高齢化による労働力人口の減少、働き方改革、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営への対応といった社会課題への解決策としても重要なテーマとされています。厚生労働省は、企業や地域社会がこうした視点を持ち、持続可能で誰もが活躍できる環境づくりを進めることを求めています。
参照
ダイバーシティ&インクルージョンの時代に 治療と仕事の両立で自分らしく働く(厚生労働省)
インクルージョンの広がりの背景
なぜ今、インクルージョンが重視されるようになったのでしょうか。
背景には、少子高齢化や労働力不足、価値観の多様化といった社会課題があります。こうした中、企業が持続的に成長するには、多様な人材の力を最大限に引き出し、柔軟で強い組織を作ることが必要不可欠です。
また、グローバル化やテクノロジーの進展によって、従来の画一的な組織運営では新たな価値を生み出しにくくなってきており、インクルージョンの視点がますます重要になっています。
インクルージョンとダイバーシティの違い
「ダイバーシティ(多様性)」と「インクルージョン(包摂)」は、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)のようにビジネスの場や社会でよく一緒に使われる言葉です。
しかし、それぞれが持つ意味や役割には明確な違いがあります。ここでは、その違いと両者の関係性について詳しく解説します。
ダイバーシティの意味〜多様な人材を受け入れること
ダイバーシティとは、性別、年齢、国籍、障がいの有無、性的指向、宗教、価値観など、人が持つさまざまな違いを尊重し、多様な人材を組織や社会に受け入れることを意味します。
ダイバーシティは違いがあることそのものを前向きに認める姿勢であり、組織にとって多様な視点や考え方を取り入れる第一歩です。
インクルージョンの意味〜多様性を活かし合う環境づくり
インクルージョンは、受け入れた多様な人材が安心して意見を言い、能力を発揮し、組織の力に変えていくための環境づくりを意味します。単に人が多様である状態にとどまらず、その多様性が組織の成長や価値創造につながっている状態を目指すものです。
例えば、ダイバーシティが進んでいても、少数派の意見が黙殺されたり、形だけの多様化で終わっていたりするケースでは、インクルージョンが不十分だと言えます。インクルージョンは、多様性を活かすことに焦点を当てた次のステップなのです。
ダイバーシティとインクルージョンの違いを正しく理解する重要性
ダイバーシティが多様な人材を受け入れることであるのに対し、インクルージョンはその多様性を力に変えることです。この違いを正しく理解しないと、形だけの多様性推進に終わってしまうリスクがあります。
組織に多様な人材を迎えるだけでなく、その人たちが公平に意見を表明し、成長できる文化や仕組みがあってこそ、ダイバーシティの効果が十分に発揮されます。D&Iの取り組みは、両者を一体で推進することが重要です。
ダイバーシティだけでは不十分な理由
多様な人材を集めただけでは、組織内に摩擦が生じたり、少数派が孤立したりする可能性があります。こうした状態では多様性が逆に組織の一体感を損なうこともあります。そのため、インクルージョンの視点で、互いの違いを尊重し合い、共に力を発揮できる環境づくりが求められます。
D&Iは両輪で進めるべきもの
ダイバーシティとインクルージョンは、どちらか一方だけでは効果が十分とはいえません。多様な人材が安心して働き、力を発揮できるインクルーシブな文化があってこそ、ダイバーシティのメリットが生まれます。企業はD&Iをセットで推進することで、イノベーションの創出や組織の持続的成長を実現することができます。
なぜインクルージョンが企業に必要なのか
インクルージョンは、単に多様な人材を集めるだけでなく、その多様性を活かして組織の力に変えていくための土台です。近年、企業がインクルージョンを重視する理由は、社会の変化や経営環境の課題と深く関わっています。ここでは、その背景と企業にとってのメリットについて解説します。
社会的背景〜多様性を活かす必要性が高まる時代
少子高齢化や労働力人口の減少、グローバル化の進展など、現代の企業を取り巻く環境は大きく変わっています。こうした中で、従来の画一的な人材戦略だけでは持続的な成長は難しくなり、さまざまな背景や価値観を持つ人材の力を引き出すことが不可欠になっています。
さらに、働き方改革やESG(環境・社会・ガバナンス)経営の推進といった社会的要請も、インクルージョンの必要性を後押ししています。企業は社会的責任を果たすとともに、持続可能な成長を実現するために、多様性と包摂の視点を組織づくりに取り入れることが求められています。
企業にとってのメリット〜インクルージョンがもたらすプラス効果
インクルージョンが実現されることで、企業にはさまざまなメリットがあります。まず、社員一人ひとりが尊重され、安心して意見を出せる環境は、創造性や問題解決力の向上につながります。異なる価値観や視点が交わることで、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなるのです。
また、インクルージョンは従業員のエンゲージメントや働きがいの向上、離職防止にも効果を発揮します。社員が自分の居場所があると感じられる職場は、定着率の向上や生産性の向上にも直結します。
インクルージョン・ダイバーシティの問題点と課題
ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)は、多様な人材を活かし、組織の力に変えるための重要な取り組みです。しかし、実際の企業活動の中では、理念だけではうまくいかない現実的な問題や課題に直面することも少なくありません。
ここでは、D&I推進において企業が陥りやすい問題点と、その背景について詳しく解説します。
形骸化したダイバーシティ施策のリスク
ダイバーシティを多様な人材を採用することと狭く捉えてしまい、実態が伴わないケースは少なくありません。
例えば、女性管理職比率の目標設定や障がい者雇用率の達成など、数値目標にばかり注目が集まり、本質的な職場の文化改善や活躍支援が後回しになると、形骸化した取り組みになってしまいます。
多様性を受け入れるだけで終わり、実際には少数派の声が反映されない、または疎外感が残る職場環境になってしまうこともあります。このような状況では、D&Iの本来の目的である多様な力を組織の成長に活かすことは難しくなります。
無意識のバイアスとその影響
D&Iを阻む大きな要因の一つが、無意識の偏見・思い込み(アンコンシャス・バイアス)です。
無意識のうちに「女性だから管理職は難しいのでは」「外国人だから日本の職場に馴染めないのでは」といった偏見を持ち、それが人事評価や職場内の人間関係に影響してしまうことがあります。
このようなバイアスは本人が自覚していないため、取り除くのが難しいという特徴があります。結果として、表面的にはダイバーシティが進んでいても、当事者が不公平感や働きづらさを感じる温床になりかねません。
企業が直面するインクルージョン推進の課題
インクルージョンは文化や風土の変革が求められる取り組みです。そのため、一部の部署や担当者だけで進めようとしても全社的な定着は難しく、経営層の強いコミットメントが必要です。また、D&Iを一過性のプロジェクトとして終わらせず、長期的に推進するための仕組みや効果測定の仕組みが整っていない企業も少なくありません。
さらに、異なる価値観やバックグラウンドを持つ人材が増えることで、職場内のコミュニケーションや意思決定の難易度が上がるという声もあります。こうした課題を乗り越えるためには、単なる制度整備だけでなく、日常的な相互理解や対話の機会を増やすことが不可欠です。
企業がインクルージョンを推進するための具体的施策
インクルージョンは、単に多様な人材が集まるだけではなく、その一人ひとりが安心して能力を発揮できる環境をつくる取り組みです。ここでは、企業がインクルージョンを推進するために実践できる具体的施策を紹介します。
経営層のリーダーシップとインクルージョン文化の醸成
経営層や管理職が率先してインクルージョンの価値を発信し、自ら実践することが重要です。具体的には、次のようなアクションが挙げられます。
- D&Iに関する経営ビジョンや方針を社内外に発信する
- 経営会議や部門会議でインクルージョンのテーマを定期的に議論する
- 経営層自らがインクルーシブな言動や意思決定を意識する
無意識バイアスへの気づきを促す教育・研修
インクルージョンを妨げる要因の一つが、無意識の偏見・思い込み(アンコンシャス・バイアス)です。これを克服するために、次のような教育機会を設けることが効果的です。
- 全社員向けに無意識バイアス研修を実施
- 管理職向けにインクルーシブ・マネジメント研修を実施
- 多様な価値観を理解するワークショップや社内イベント
公平な評価とキャリア形成の仕組み
インクルージョンの実現には、あらゆる社員が公平に評価され、キャリアを築ける仕組みづくりが必要です。取り組み例は次のとおりです。
- 評価基準の透明化と、バイアスの入りにくい評価プロセスの整備
- メンター制度やキャリア面談の実施
- 少数派社員や多様な属性の社員のキャリア形成支援プログラム
意見を言いやすい風土と相談体制の整備
誰もが安心して意見を表明し、課題を相談できる仕組みはインクルージョンの土台です。次のような施策が考えられます。
- 意見交換会や部門横断ミーティングの定期開催
- 社内アンケートや意識調査による職場の声の把握
- 相談窓口やハラスメント防止体制の整備
多様な働き方の柔軟な選択肢の提供
インクルージョンを支えるためには、従業員の事情や希望に応じた働き方の選択肢を用意することが有効です。
- テレワークやフレックスタイム、副業・兼業制度の導入
- 育児・介護と両立しやすい短時間勤務・時差出勤の制度
- 治療や障がいへの配慮を反映した個別対応
取り組みの継続的な見直し・改善
インクルージョン推進は、一度の施策で終わるものではなく、組織の変化に応じて見直しと改善を続けていくことが重要です。目に見える成果だけでなく、現場の声や小さな変化にも丁寧に向き合いながら、持続可能な仕組みとして根づかせていく姿勢が求められます。
- D&Iの浸透状況を可視化し、定期的に社内で振り返る機会を設ける
- 現場の声をもとに、制度や施策を柔軟に見直す
- 他企業や団体の先進的な取り組み事例から学び、自社に合う形で取り入れる
インクルーシブな企業の具体的取り組み事例
インクルーシブな職場づくりに成功している企業では、理念の掲げ方だけでなく、実際の制度や文化づくり、日々の運用において具体的な工夫を重ねています。以下は、複数の企業事例や公的資料をもとに編集・再構成したインクルーシブな取り組みの具体例です。
多様なキャリア支援プログラム
性別、国籍、年齢、障がいの有無、個々の価値観やライフスタイルなどに関わらず、すべての従業員が公平に成長機会を得て、自分らしいキャリアを築けるようにする取り組みです。特定の層に偏ることなく、あらゆる人材が自らの力を発揮し、チャレンジできる環境づくりを目的としています。
課題
一部の社員が管理職や専門職は特定の属性に適したものという固定観念により、キャリアの選択肢を狭めてしまう風土があった。また、成長を後押しする仕組みが十分でなく、社員全体にキャリア形成への不安があった。
施策
社内外の研修費用補助、キャリア公募制度、メンター制度を組み合わせた支援プログラムを整備。希望するすべての社員を対象にキャリア面談を定期実施し、職務や役割に関わらずキャリアの選択肢を広げる機会を提供した。
成果
多様な属性・背景を持つ社員が管理職や専門職にチャレンジする動きが広がり、社員アンケートでは「キャリア形成に前向きになれた」「挑戦しやすくなった」という声が多数寄せられた。職場全体でキャリア支援の重要性への意識が高まった。
アンコンシャス・バイアス対策の教育と風土づくり
誰もが公平に意見を言え、評価される職場にするための取り組みです。特に、無意識の偏見や思い込みに気づき、職場文化を変えていくことを目的としています。
課題
無意識のバイアスにより、「管理職は男性が向いている」「外国籍社員はリーダーにしづらい」といった思い込みが存在し、少数派社員の活躍や発言機会が制限される雰囲気があった。
施策
全社員向けに無意識バイアス研修を実施。管理職にはケーススタディを用いた追加研修を実施し、評価や会議運営でのバイアスの排除に取り組んだ。さらに研修後、小グループでの対話会を開催し、日常業務での具体的行動を共有した。
成果
社員アンケートで「職場で意見を言いやすくなった」と回答する割合が増加。評価・昇進において少数派社員が公平に取り扱われる事例が増え、管理職候補層の多様化が進んだ。
柔軟な働き方の推進
一人ひとりの事情に合わせ、働きやすさを高める制度や運用を強化した取り組みです。ライフステージや個別の事情に応じて選択肢を広げることを狙いました。
課題
育児や介護、持病の治療と仕事を両立する社員が制度面・運用面で十分な支援を得られず、離職や休職につながるケースがあった。
施策
テレワーク、フレックスタイム、副業・兼業制度を全社員に適用。短時間勤務、時差出勤、治療と仕事の両立支援制度を整備し、運用ルールを明文化して周知徹底した。
成果
制度利用者が増加し、育児・介護・治療と仕事を両立する社員の定着率が向上。「制度を使いやすくなった」「職場の理解が進んだ」との声が寄せられた。
相談・サポート体制の強化
従業員が不安や課題を安心して相談できる体制をつくることで、インクルーシブな職場づくりを支える取り組みです。
課題
ハラスメントや不公平感、働きづらさを感じても「どこに相談すればいいかわからない」「声を上げにくい」という声があった。
施策
社内相談窓口の整備に加え、外部専門機関と連携した匿名相談窓口を導入。相談対応の事例を(個人が特定されない形で)社内共有し、全社で再発防止に役立てた。
成果
相談件数が増加し、課題が早期に発見・対応されるようになった。従業員の安心感が高まり、職場の心理的安全性向上に寄与した。
おわりに
インクルージョンは単なる流行語ではなく、これからの企業が持続的に成長するための土台です。多様な人材が能力を発揮し、誰もが安心して働ける職場づくりに向け、ぜひ自社でも取り組みを進めていきましょう。