

ストレスチェックの実施が、50人未満の事業所にも義務付けられることが決まり、「どのように対応すればよいのか分からない」と戸惑う中小企業の声が多く聞かれます。
コストや人員体制、実施方法に対する不安が、対応の大きなハードルとなっているのが現実です。
そこで今回は、義務化対象となる50人以下の事業場では何を準備したらいいのか、引き続き制度の専門家であり、厚生労働省の関連委員も務めた弊社代表で精神科産業医である渡辺に話を聞きました。
── 中小企業にとって、ストレスチェックの義務化はやはりハードルが高いと感じる場面が多いようです。どのあたりが一番の課題だと感じていますか?
渡辺 課題の一つは体制面です。50人以上の事業場では産業医の選任が義務付けられていますが、50人未満の事業場では産業医がいないケースが一般的です。ストレスチェックの運用を統括する「実施者」には、産業医や保健師などの有資格者が必要なため、外部から適任者を確保しなければならない状況が出てきます。また、事務作業を担当する「実施事務従事者」についても、人手が限られている中で対応するのは難しい場合が多いでしょう。こうしたことから、外部の専門機関をうまく活用することが、現実的な対応策だと考えられます。
── ストレスチェックの実施を外部に委託するというのは、現実的な選択肢なのでしょうか?
渡辺 はい、特に小規模な事業所にとっては非常に有効な方法だと思います。ストレスチェックの受検から集計、結果のフィードバックまでを一括で担ってくれる外部機関を利用すれば、事業所の負担は大きく軽減されます。
── 実務的な負担が軽くなるという点はわかりやすいですね。他にも外部委託のメリットはありますか?
渡辺 最近では「プライバシーの保護」という観点からも、外注化は重要な意味を持ちます。
たとえば、社内の人数が数名しかいないような小規模な職場では、その少人数の中にストレスチェックの事務を担当する「実施事務従事者」が含まれていること自体が受検者からは懸念点となり得ます。誰がどんな回答をしたのかが推測されやすく、「見られてしまうかも」という不安から、従業員が本音で回答できなくなるんです。
── 本音で答えられなければ、制度の意味がなくなってしまいますよね。
渡辺 まさにその通りです。そのため、実施事務そのものを外部に委託するという選択肢は、プライバシーを守るうえでも非常に有効です。制度の見直しを検討する委員会の中でも、「小規模事業場では、実施事務のすべてを外部に委託できる形が望ましいのではないか」といった意見が出ており、今後マニュアルにもそうした方向性が反映されていく可能性があります。
── 外注化を進めるうえで、注意しておくべき点はありますか?
渡辺 重要なのはやって終わりにしないことです。単にストレスチェックを実施して結果を返すだけではなく、「その結果をどう活かすか」「職場の改善につなげるか」までサポートしてくれる外部機関を選ぶことがポイントです。結果の活用まで一貫して支援できる業者を選定することが、制度を意味あるものにしていく鍵になると思います。
── 結果を活かすという点では、どのようなサポートが求められますか?
渡辺 たとえば、集団分析の結果をもとに「この部署にはこういう支援が必要かもしれない」といった示唆を与えてくれるような分析レポート。あるいは、従業員向けに簡単な説明資料を作成してくれる、相談対応を受けてくれるなど、アフターフォローまで含めた体制があると非常に心強いです。
── 価格面での不安を感じている企業も多いようです。導入にあたって、どのような配慮が求められるのでしょうか?
渡辺 小規模な事業所にとっては、コスト面が大きなハードルになるのは確かです。ストレスチェックは、一回の実施でも専門的な運用や事務作業が伴うため、一定のコストがかかります。ただ、近年では事業所の規模やニーズに応じた柔軟な料金プランを用意する支援企業も増えてきました。
たとえば、数万円〜の基本料金に加え、従業員数に応じた従量課金制が一般的ですが、これも今後さらに見直しや簡便化が進んでいく可能性があります。
── 制度側としても、価格設定の工夫や支援が今後の課題になるということですね。
渡辺 そうですね。国の支援制度や助成金の活用、あるいはスマートフォン等を活用した低コストな受検方法など、工夫の余地はまだまだあると思います。制度を根付かせるためには、続けられる仕組みにしていくことが重要ではないでしょうか。
── 高ストレス者対応や産業医面談などは職場環境改善にとって重要ですが、小規模な事業所の場合実施が難しい印象もありますが。
渡辺 50人未満の小規模事業場については、地域産業保健センター(地さんぽ)が産業医面談などの実施機関として対応しています。ただし、対応できる人数や時間には限りがあるのが実情です。
高ストレス者への面談は、本人のメンタルケアという意味でも重要ですが、同時に「職場で何が起きているのか」を産業医が把握する手掛かりにもなります。面談を通じて、ストレスの要因が職場環境にあるのかどうかを確認し、必要があれば環境改善に向けた提言を行う、この流れが非常に大切なんです。
ただ、それを地域産業保健センターだけでカバーするのは、現実的には難しい面があります。たとえば、週に1回しか医師や心理職が配置されていない場合もあり、相談対応にも限界があります。だからこそ、支援企業との連携や、地域の専門職とつながるネットワークを構築していくことが、今後ますます重要になると考えています。
── この3年間の準備期間で、企業がやっておくべきことをあらためて教えてください。
渡辺 まず大事なのは、従業員にとって安心して受けられる制度にすることです。「プライバシーは守られる」「受検によって不利益を受けることはない」といったことを、きちんと伝える必要があります。そのうえで、制度のメリットをきちんと実感してもらうことも重要です。
ストレスチェックは、個人のストレス状態の把握だけでなく、集団分析を通じて職場全体の課題を可視化できる仕組みです。これを活用すれば、個人への支援だけでなく、職場環境の改善にもつなげることができます。
── 「安心感」と「メリットの共有」、この2つが準備の要ということですね。
渡辺 そうですね。そしてもう一つ大切なのは、制度の目的や意義を社内で丁寧に共有しておくことです。「なぜやるのか」が十分に理解されていないと、どうしても形だけの対応になってしまいがちですから。
実際、50人未満の事業場については義務化されるという方針が出たばかりで、具体的な実施方法やマニュアルはこれから整理されていく段階です。ですので、現時点で急いで準備を進める必要はありません。
ただ、制度の本格運用が始まる頃に向けて、「ストレスチェックってしっかり活用すれば意味があるんだよ」「やれば職場が良くなるかもしれない」という前向きな意識を、少しずつ社内に広げておくことは、将来に向けた良い準備になると思います。
── 外部委託についても触れていましたが、今後の制度運用では外部機関との連携がますます重要になりそうですね。
渡辺 はい、基本的には今後、外部委託(外注)を前提とした運用が主流になっていくと思います。とはいえ、外注もデータ処理をして終わりという形では意味がありません。
大事なのは、ストレスチェックの結果をどう活かすか。そのためには、結果を返して終わりではなく、「じゃあこの結果をもとに、どのように職場環境を改善していくか」までしっかりと支援できる外部機関と連携していくことが必要です。
今回のシリーズでは、ストレスチェック制度の義務化をきっかけに、「制度の背景」「本来の意義」「具体的な導入方法」について、現場目線でお届けしてきました。
制度そのものは今まさに整備が進められている段階ですが、ストレスチェックの結果をうまく活用すれば、職場環境の改善に大きく貢献することができます。
私たちCHRでは、制度を義務だからやるのではなく、現場の役に立つしくみにするための、実践的な支援を行っています。
「まず何から始めればいいのか知りたい」「自社に合った進め方を相談したい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
参考図書
PR|ストレスチェック書籍紹介 (弊社代表・医師 渡辺洋一郎 著)
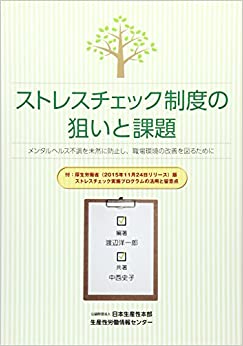
ストレスチェック制度の狙いと課題: メンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境の改善を図るために
渡辺洋一郎 (著), 中西史子 (著)
出版社 : 公益財団法人日本生産性本部 労働情報センター
ストレスチェックを成功させるために知っておくべき正しい知識と運用方法が一冊に
複雑な制度のポイントがすっきり!
◎ストレスチェックの「本当の狙い」を知っていますか?
◎精神科産業医が指南、「安全・確実な」ストレスチェックの中身
◎「高ストレス者」への対応方法
※クリックするとAmazonに飛びます。




